- 方向的な隠喩(orientational metaphors)、それは主に空間的な機構と関連している(up/down,in/out,front/back,on/off,near/far,deep/shallow and central/peripheral);
- 存在論的隠喩(ontological metaphors)、それは存在や実体と、活動、感情や観念とを連合させる(隠喩が擬人化を含むのは、すぐ分かる);
- 構造的隠喩(structual metaphors):アーチ型をなす隠喩(他の二つのタイプの上に構築される)、それによって、我々はもう一つの他の用語を用いて一つの概念を構築できる(例、理性的な議論は戦争である(rational argument is war)または時は金なり(time is a resource))。
- 原因に対して結果(‘怒るな’に対して‘そんなにカッカするな(Don't get hot under the collar)’);
- 人(または関連する団体)に対して物体(君主国に対して‘王冠’、劇場に対して‘ステージ’そしてジャーナリストに対して‘プレス:press、印刷機’);
- 外見に対して材料(‘クレジットカード’に対して‘プラスチック’、‘弾丸’に対して‘鉛’);
- 事象に対して場所(‘チェルノブイリは原子力発電に対する態度を変えた’);
- 人物に対して場所(英国の首相に対して‘10番街’);
- 団体に対して場所(‘ホワイトホール(英国政府)はなにも発言していない’);
- 人々に対して団体、機関(‘政府は、退かない’)。
- 製品に対して生産者(‘彼女はピカソを持っている’);
- 使用者に対して物体(‘ハムサンドイッチ(を買った人)が、勘定書を待っている');
- 管理される人に対して管理者(‘ニクソンはハノイを爆撃した')。
- 全体に対して部分(‘私は煤煙[ロンドン]から逃れた';‘もう少し手[作業者]が要る';‘一つの頭脳より、二つの頭脳の方が良い’;‘一組の車輪[車?]を手に入れた'、アメリカ的表現‘君の尻を向こうにやれ(get your butt over here)')
- 種に対する類 -クラス全体(superordinate)を指すためにクラスの一つの要素(hyponym)を使用する(例えば、母性に対して母親、‘食料'に対して‘パン'、‘掃除機'に対して‘Hoover');
- 類に対して種 -クラスの一つの要素を指すのにクラスの名称を使用する(例えば、‘自動車’に対して‘乗り物'、‘コンピュータ'に対して‘マシン')。
-
修辞的な言葉のあや(Rhetorical Tropes)
現代の記号学者は、レトリック(修辞学)(または少なくとも、そのような相)は記号論の範疇に入ると考えている(Noth 1990, 338)。ソシュールが‘社会生活の要素としての記号の役割’と呼んだものの研究から、説得術という昔からの技術を除くことはできない。修辞学に関する概説はこの教科書の範囲を越えているが、主要な言葉のあや(tropes)(または比喩(figures of speech))に関する関心は、記号論の研究の中で非常に高いので、このテーマに関してある程度理解がないと、記号論の探求に入っていけない。
レトリック(修辞学)またはある比喩の認識論的暗示に関する学術的な興味は、20世紀の後半に構造主義者であるC・レヴィ=ストロースやローマン・ヤコブソン、自称フォーマリストのHayden White、ポスト構造主義者のジャック・デリダやジャック・ラカン、認識的意味論者のG・レイコフやM・ジョンソンなどによって復活した。多くの分野で目立つ、学術的言説の大きな変化は‘修辞的方向転換’または‘とりとめもない方向転換’と呼ばれている。それは、言語の‘科学的’利用を確立するための17世紀の探求から導かれた客観主義的言語学に対する急進的な挑戦である。この現代の傾向の中心的な主張は、修辞的な形体は実在の形成の中に深く、また不可避的に埋め込まれている、ということである。言語は中性的な媒体ではない。普通の使い方の中で、我々は知らず知らずのうちに、‘熱した修辞’、‘空の修辞’そして‘単なる修辞’を使っている。レトリックは文体上の飾りではなく、説得力のある談話である。全ての談話は不可避的にレトリック的であるが、特に学術的な著者は書いたものの中にレトリックがあることをめったに認めないし、またしばしば否定する。レトリックはしばしば合理性と対比され、急進的な相対主義やニヒリズムと連合する。勿論、そのような主張はレトリックが使われていることを表す(科学の‘堅固さ’が人間性の‘柔らかさ’と対比されるように)。レトリックは、単に思想の表現方法ではなく、思考の方法への影響であり、それは真剣に注意する必要がある。学術的な書物の著者は、特定の実在と理解の様態を規定するテクストを構築するBazerman 1981; Hansen 1988)。‘事実’は‘それ自体で語る’ことはない:学術的な著者は、それらの存在を主張しなければならない。学術的な論文は、知識の提示に関して問題がないわけでなく、認識論的な暗示を含む巧妙な修辞的な構築物である。修辞学に参加することは、我々があらゆる種類の談話を脱構築することを支援する。
Terence Hawkesは我々に以下のように語っている。‘比喩的な言語(figurative language)は、それが言っていることを意味しない言語である’ -それは、純粋に指示義的 であろうとする、またはそう考えられている散文的な言語(literal language)と対照的である(Hawkes 1972, 1)。これは、古典主義時代までさかのぼる区分であるが、一方、ポスト構造主義者によって問題視されている(これについては、すぐあとで触れる)。そんなに問題ではないにしろ、言葉のあや(tropes)は、‘これはあれだ(またはあれのようだ)’と言うのに、いろいろな方法を提供するものだと見ることができる。もし、比喩が、あまり知らないものを慣れ親しんだものにする過程と捉えるなら、比喩は理解にとって必須のものである。しかも、どのように定義されるにせよ、比喩的な言語という習慣はレトリック的なコードを構成し、このコードを理解することは、それを採用している文化の成員であることの一部分となる。他のコードと同様、比喩的な言語は、ある文化またはサブ-カルチャーでの実在を保持するシステムの一部分である。それは、なにが表現されるかよりも、ものごとがどのように表現されるかに表面上関係するコードである。たまたま、日常生活では、我々は目新しい隠喩(メタファーmetaphor)に引き付けられる -例えば、自動トースターも持っていない保証人というきわどい皮肉。しかし、多くの場合 -‘詩的’文脈以外でも- 気づかないで話しているとき、多くの比喩を使うしまた出会う -それらは‘透明性’の中に退避している。そのような透明性のために、文化的に蓄積されている比喩は、我々の社会の中で主流となっている考え方へ我々を結びつける錨として働いていることに気づかない(Lakoff & Johnson 1980)。そのような話し言葉のあやを繰り返し受け取ることや使うことにより、社会に共有された仮定に関する暗黙の了解が巧妙に維持される。
比喩は、‘字義的な’意味の上に、またそれを越えて共示義 を伴う‘心象’を生み出す。いったん、比喩を用いると、話された言葉は、制御できない連想というより大きな体系の部分となる。例えば、隠喩的に、‘事物を言葉に注入する(putting things into word)’と言うとき、言語は‘容器’であるという考えを共示する傾向にある -それは、言語に対するある意味を持つ特定の視点である(Reddy 1979))。しかし、比喩の使用は不可避である。比喩的な言語を、詩的表現もっと一般的には‘文学的な’書物のもっともはっきりした特徴と我々は考えるかもしれないが、Terry Eagletonが注意しているように、‘素晴らしいこと(Marvell)の中よりも、マンチェスター(Manchester)に、より隠喩がある’(Eagleton 1983, 6)。ローマン・ヤコブソンによれば、隠喩と換喩は意味を伝達する二つの基本的なモードであり、 -G・レイコフとM・ジョンソンによれば- 日常生活における色々な理解の基礎でもある(Jakobson & Halle 1956; Lakoff & Johnson 1980)。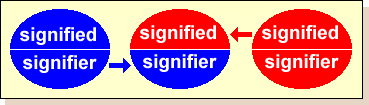 ロラン・バルトは‘形式は、それがあるものに似ているに違いないとなると、すぐに理解される:人類は相似性に運命付けられているように思える’と宣言している(Silverman & Torode 1980, 248で述べられている)。話す形式と同様に、視覚形式においても比喩が至るところに見られることは、我々が基本的に実在を関係付けによって理解するということを反映していると考えられる。実在は、相似というシステムの中で枠組みがなされる。言葉のあやは、あることをもう一つの用語で理解するすることを可能にする。範列や統語体と同様に、比喩は談話において、‘記号表現と記号内容の相互干渉を編曲する’(Silverman 1983, 87)。隠喩のような比喩は、一つの記号の記号表現ともう一つの記号の記号内容から形成される新しい記号と考えられる。その記号表現は、異なる記号内容を表す;新しい記号内容は、通常のそれに取って代わる。これから説明するように、比喩によってこれらの代入の性質が異なる。
ロラン・バルトは‘形式は、それがあるものに似ているに違いないとなると、すぐに理解される:人類は相似性に運命付けられているように思える’と宣言している(Silverman & Torode 1980, 248で述べられている)。話す形式と同様に、視覚形式においても比喩が至るところに見られることは、我々が基本的に実在を関係付けによって理解するということを反映していると考えられる。実在は、相似というシステムの中で枠組みがなされる。言葉のあやは、あることをもう一つの用語で理解するすることを可能にする。範列や統語体と同様に、比喩は談話において、‘記号表現と記号内容の相互干渉を編曲する’(Silverman 1983, 87)。隠喩のような比喩は、一つの記号の記号表現ともう一つの記号の記号内容から形成される新しい記号と考えられる。その記号表現は、異なる記号内容を表す;新しい記号内容は、通常のそれに取って代わる。これから説明するように、比喩によってこれらの代入の性質が異なる。
17世紀の英国では、王立協会の科学者達は、‘自然に関する知識をレトリックという色、空想という策略、神話という非常に楽しい偽りから分離’しようとしていた(Thomas Sprat,1667: The History of the Royal Society of London for the Improving of Natural Knowledge);彼らは、‘隠喩のトリック’は実在を歪めると見ていた。リヴァイアサン(Leviathan,1651)で、トーマス・ホッブスは‘正しい言葉の代わりに隠喩、比喩そして他のレトリック的なかたちを使うことを、退けている。普通に話す時には、例えば道は進む(the way goeth)、またはここやあそこに通じる(leadeth hither,or thither)と言うのは許される;またことわざはあれやこれや言う、のも許される。しかし、道は進まないし、ことわざは話さない;また、計算や真理の探究では、そのような話し言葉は認められない’(Leviathan,Part 1,Chapter 5)。ジョン・ロックも1690年に、同様なことを書いている。
-
もし、事物をありのままに話したいなら、レトリックの技術はすべて、秩序と明確さに反することを認めなければならない;修辞法が作り出した、言葉の人工的かつ比喩的な応用法は悪い言葉をだらしなく引き入れ、激情を揺り動かし、それによって判断を誤らせる;そして、まったくペテンである:賞賛に値するまたは正当な雄弁術により、それらが熱弁や広く受け入れられる話し方になったとしても、知らせたり、教えたりするように装った全ての説話において、全体的に避けられるべきである;真理や知識に関連するところでは、言葉の人工的かつ比喩的な応用法は言語やそれらを使う人の大きな過失としか考えられない。(Essay Concerning Human Understanding,Book 3,Chapter 10)
修辞的な言語を避ける試みは、客観主義という実在主義者のイデオロギーと密接に連合している。実在主義者にとって、言語と実在(reality)、思想と言語、そして形式と内容は別のものであるかまたは分離できるものと見做されている。実在主義者は、‘事実’を正確にかつ正しく記述するために、‘もっとも明確’で、もっと‘透明な’言語を使用することを好む。しかし、言語は(清澄や透明に関する隠喩的な参照が示唆しているような)‘ガラス’ではなく、世界を我々が知っているように構築することと係わりあうのは避けがたいことである。隠喩を追放するのは、それが言語にとって重要だからである。皮肉にも、Hobbes、ロックやSpratの書いたものは、それ自身、隠喩的である。詩人Wallac Stevensは挑発的に、次のように嘲弄している。‘実在は、隠喩によって逃れる決まり文句である’(Hawkes 1972, 57で記述)。哲学的な観念主義に向かう人たちは、全ての言語は隠喩であるか、または‘実在’は単に隠喩の産物であるとさえ主張する。そのような立場は、‘字義的’と‘隠喩的’の指示的な違いを明確に否定する。ニーチェは宣言している:‘何が‥‥真理か?隠喩、換喩、神人同形同性論(anthropomorphisms)の機動軍隊’(Spivak 1976, xxiiに記述)。ニーチェ(Nietzsche)にとっては、真理または実在は、単に昔の隠喩の凝固にすぎない。
ポスト構造主義者達(彼ら自身の言語の使い方は、典型的に、また高度に隠喩的である)は、‘言おうとしていることを意味する’(しばしば、それは‘散文的な’言語が決定される方法である)テクストはありえないと主張する。構築主義者達は、次のように主張することに甘んじるかもしれない。隠喩は広く行き渡っており、文化やサブカルチャーの中ではほとんど認識されていない、そしてそれらに焦点をあてることは、そのような隠喩がだれの実在が優先されているかを明確にするための主要な要因である。テクストや実践における比喩をはっきりさせることは、主題の枠組みに焦点をあてることの助けになる;記号論的なテクスト分析は、しばしば、‘アーチ型をなす(または‘根本’の)隠喩’、または‘主たる比喩’の同定を含む。例えば、デリダは、哲学者が伝統的に、精神や知性に、光の存在や不在を用いた比喩を使って、どのように言及してきたかを示している((Derrida 1974));日常の言葉には、思考と視覚的隠喩の連合の例が沢山ある(輝くbright、きらきらしたbrilliant、鈍いdull、啓発するenlighting、明らかにするilluminating、洞察力vision、明確clarity、熟慮reflection、他)。Kressとvan Leeuwenが言っているように:
-
我々の文化では、見ること(seeing)は理解すること(understanding)と同義語である。我々は、問題を‘調べる(looking at)’。我々は、ある‘視点(view point)’を採用する。あることに、‘注目する(focus)’。我々は、`ものごとをバランスよく判断する’。(‘知っているがまま’というより、また疑いもなく、‘聞いたまま’または‘感じたままでは’ではなく)‘我々が見たまま’の世界は、何が‘現実’でまた’真実’であるかの物差しとなっている (Kress and van Leeuwen 1996, 168)。
ミッシュル・フーコーは言語決定主義の立場を採り、特定の歴史的時代の談話の中での主要な比喩は、知りうること -それは、その時代の基本的な知の体系(エピステーメーepisteme)を構成する- を決定すると主張している。‘とりとめもない慣例’が‘匿名の歴史的規則の本体になる。それは、その時代を規定する時間と空間またそのときの社会的、経済的、地理的または言語的地域に対して宣言的機能が作用する条件によって決定される’(Foucault 1974, 117)。ある隠喩は自然なものとなり、我々は往々にしてその記号内容に関する思考とそれが示すものとの間の経路を開く方法に気が付かないので、慣習的でない比喩の慎重な使用は、現象を見る当たり前の方法を変質させる一助となる(Stern 1998, 165)。
隠喩は広く普及しているので、‘包括的(umbrella)’用語して使われ(これも、もう一つの隠喩であるが!)、狭義の使い方では技術的に区別できる他の言葉のあや(例えば、換喩)を含む。直喩(similes)は、隠喩の一形式と見ることができ、比較という比喩の状態が、‘~のように’('as','like')という言葉の使用を介して、明白になる。このように‘人生は、チョコレートの箱のようなものだ(life is like a box of chocolates)’(ホレスト ガンプForrest Gump,1994)。多くの場合、我々は、自分が隠喩を使っていることにまったく気が付かないし、しかもある研究では、英語を話す人々は1週間に平均3000個の新規な隠喩を作り出している、ことを見出されている(Pollio et al. 1977)。G・レイコフとM・ジョンソンは‘隠喩の真髄は、ある事物を、もう一つの事物に関する用語で理解し、経験することにある’と主張している(Lakoff & Johnson 1980, 5)。記号論の用語を使えば次のようになる。隠喩は、異なる記号内容を指す記号表現として作用する記号内容を含む。辞書的な用語では、隠喩は、‘比喩的な’第2の主題(または負荷体('vehicle'))で表される‘字義的な’第1の主題(または‘趣意(tenor)’)で構成される (Richards 1932)。例えば、‘経験は良い学校である、しかし代償は高い(Experiennce is good school, but the fees are high)’(Heinrich Heine)。この場合、経験という第1の主題は学校という第2の主題を用いて表現されている。隠喩はもっとよく定義されているモデルを用いて、抽象的なことを表現することに特色がある。
特定の趣意(tenor)と負荷体の結び付きは、普通なじみのないものである:我々は、新鮮な隠喩がほのめかす類似点を認識するために、想像力により跳躍をしなければならない。隠喩は最初慣習的でない、というのはそれは明らかに‘字義的な’または指示義的な相似点を無視するからである(しかし、その隠喩を、解釈者にとって理解できるようになるためには、ある種の類似点が明らかになる必要がある)。類似に根拠があることは、隠喩が類像的な様態を含んでいることを示唆している。しかし、そのような類似点が間接的であるならば、隠喩は象徴的であると考えても良い。字義的な記号表現を理解するよりも、隠喩を理解することは解釈のための努力が必要とするが、この解釈のための努力は愉快なものとして経験される。隠喩は、最初に用いられるときには(詩や視覚的芸術での審美的な使用のように)、想像上の飛躍を必要とするかもしれないが、習慣的に用いられるようになると、隠喩とはまったく認識されなくなる。
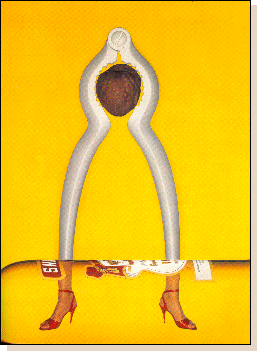 隠喩は、必ずしも言語だけではない。映画では、連続的な二つの映像(ショット)がそれとなく比較されている場合には、隠喩的となる。例えば、飛行機のショットに飛んでいる鳥のショットが続けば、それは隠喩的であり、飛行機は鳥で(または鳥のようで)あることをほのめかしている。また、空港の管制塔や飛行機のブレーキの音を伴った、鳥の着地のショットも、これはCharles Forcevilleによって記述されている航空会社の宣伝に見られるが、隠喩的である(Forceville 1996, 203)。多くの場合、文脈が第1の主題に関する手がかりを与える。航空会社の宣伝は、鳥が飛行機(のよう)であるというより、飛行機は鳥(のよう)であることを示唆する。言葉の隠喩と同じく、比較の要点に関する自分自身の結論に導かれる。広告者は、しばしば、視覚的隠喩を用いるが、それはスミノフSmirnoffのウオッカのこの宣伝に見られる。映像は主張しないというこれまでしばしば言われている考えに反して、隠喩的な映像はしばしば、広告者が言葉では表現しないであろうことをほのめかす。男性雑誌からのこの例では、隠喩は以下を示唆している。女性(または何人かの女性)はくるみ割りである(とスミノフは君に示している)(関連するスミノフの宣伝はこれをユーモアとして示している)。
隠喩は、必ずしも言語だけではない。映画では、連続的な二つの映像(ショット)がそれとなく比較されている場合には、隠喩的となる。例えば、飛行機のショットに飛んでいる鳥のショットが続けば、それは隠喩的であり、飛行機は鳥で(または鳥のようで)あることをほのめかしている。また、空港の管制塔や飛行機のブレーキの音を伴った、鳥の着地のショットも、これはCharles Forcevilleによって記述されている航空会社の宣伝に見られるが、隠喩的である(Forceville 1996, 203)。多くの場合、文脈が第1の主題に関する手がかりを与える。航空会社の宣伝は、鳥が飛行機(のよう)であるというより、飛行機は鳥(のよう)であることを示唆する。言葉の隠喩と同じく、比較の要点に関する自分自身の結論に導かれる。広告者は、しばしば、視覚的隠喩を用いるが、それはスミノフSmirnoffのウオッカのこの宣伝に見られる。映像は主張しないというこれまでしばしば言われている考えに反して、隠喩的な映像はしばしば、広告者が言葉では表現しないであろうことをほのめかす。男性雑誌からのこの例では、隠喩は以下を示唆している。女性(または何人かの女性)はくるみ割りである(とスミノフは君に示している)(関連するスミノフの宣伝はこれをユーモアとして示している)。
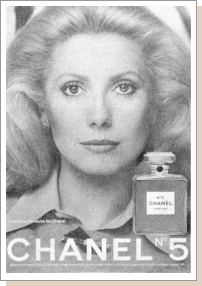 視覚的な隠喩は、また‘転送’の機能を含むことが可能であり、ある性質を一つの記号から他へ転送する。宣伝に関して、これがJudith Williamsonによって、Decoding Advertisementという彼女の本の中で研究されている(Williamson 1978)。もちろん、同じような商品を互いに差異化するのが広告企画者の役割であり、ある商品と特定の社会的価値を連合させることによりそれを行う -記号論的用語では、商品に対して別の記号内容を生成することになる。広告は‘新しい消費財の記号内容と記号表現を、我々に定常的に知らせ続ける一種の辞書’を供給していると示唆されるのも、もっともなことである(McCracken,Stern 1998, 292)で述べられている)。左の印刷された広告は、グラマーなフランスの女優、カトリーヌ・ドヌーブ(彼女の名前は小さな活字で記されている)の頭部と肩の、写真的なクローズアップの形体を採っている。広告の右下の部分に、シャネルの5番の壜が添えられれいる。この広告では、2つの主要な記号表現が並置されている。カトリーヌ・ドヌーブの写真は、フランス的な粋、洗練さ、エレガンス、美しさそしてグラマーを豊かに意味している。壜の淡白な像は、単純にシャネルの5番を表している。これは、実際には我々が香水の匂いをかげない、‘空’の記号表現である(雑誌などでの現在の広告には、香りをしみ込ませた紙が付いていることがある)。広告の下の部分には、大きな文字で香水の名前が独特の印刷スタイルで繰り返されており、それが2つの記号表現を結び付けている。もちろん、その目的は、女優によって意味されている特性を香水に転移することであり、このように一つの記号内容がもう一つの記号内容に代入され、シャネルの5番は美であり、エレガンスであるという意味を我々に提示する新しい隠喩的な記号を生成する(Williamson 1978, 25)。
視覚的な隠喩は、また‘転送’の機能を含むことが可能であり、ある性質を一つの記号から他へ転送する。宣伝に関して、これがJudith Williamsonによって、Decoding Advertisementという彼女の本の中で研究されている(Williamson 1978)。もちろん、同じような商品を互いに差異化するのが広告企画者の役割であり、ある商品と特定の社会的価値を連合させることによりそれを行う -記号論的用語では、商品に対して別の記号内容を生成することになる。広告は‘新しい消費財の記号内容と記号表現を、我々に定常的に知らせ続ける一種の辞書’を供給していると示唆されるのも、もっともなことである(McCracken,Stern 1998, 292)で述べられている)。左の印刷された広告は、グラマーなフランスの女優、カトリーヌ・ドヌーブ(彼女の名前は小さな活字で記されている)の頭部と肩の、写真的なクローズアップの形体を採っている。広告の右下の部分に、シャネルの5番の壜が添えられれいる。この広告では、2つの主要な記号表現が並置されている。カトリーヌ・ドヌーブの写真は、フランス的な粋、洗練さ、エレガンス、美しさそしてグラマーを豊かに意味している。壜の淡白な像は、単純にシャネルの5番を表している。これは、実際には我々が香水の匂いをかげない、‘空’の記号表現である(雑誌などでの現在の広告には、香りをしみ込ませた紙が付いていることがある)。広告の下の部分には、大きな文字で香水の名前が独特の印刷スタイルで繰り返されており、それが2つの記号表現を結び付けている。もちろん、その目的は、女優によって意味されている特性を香水に転移することであり、このように一つの記号内容がもう一つの記号内容に代入され、シャネルの5番は美であり、エレガンスであるという意味を我々に提示する新しい隠喩的な記号を生成する(Williamson 1978, 25)。
G・レイコフとM・ジョンソンは、我々の基本的な概念の下に潜むのは、何種類かの隠喩であると説明している。
G・レイコフとM・ジョンソンは、隠喩は文化によって変わることを記しているが、それらは恣意的でなく、最初は我々の物理的、社会的そして文化的経験から派生してきたと主張している。1744年に、Giambatgtista Vicoはその点を徹底している:‘全ての言語において、生物でないものに関連した表現の大部分は、人の体やその部分また人の感覚や情熱からの隠喩によって形成されている’。現代の彼の英語への翻訳者は、彼の次のようなリストの改作を提示している;
-
先端(top)や始まり(beginning)に対して、頭(head);丘の頂上(brow)と肩(shoulder);針やじゃがいもの目(eyes);なにか開いているもの全般に対する口(mouth);茶碗や水差しのへり(lip);くまで(rake)、のこぎり、くしの歯(teeth);小麦のパン(bread:生計という意味もある);靴の舌皮(tongue);地峡(a neck of land);入海(an arm of the sea);中心に対する心臓部(この意味では、ラテン語ではumbilicus、へそ(navel)を使っていた);
帆のはら(belly of a sail);末端や底に対する末席(foot);果肉(the flesh oh fruits);岩脈、鉱脈(a vein of rock or mineral);ワインに対するブドウの血;地球の内部(the bowels of the earth)。天国または海が微笑む、風がピューと吹く(the wind whistles)、波がささやく(the waves murmur);身体が重みに耐えかねている(a body graons under a great weight)。(Vico 1968, 129)
G・レイコフとM・ジョンソンは、次のように主張している。隠喩は、観念(または意味)は客体対象であり、言語的な表現は容器でありそしてコミュニケーションは導管であるというようなシステム的な群を形成する -これは、‘導管隠喩(the conduit metaphor)’に関するマイケル・レディの議論から引かれた一つの例である(Reddy 1979)。隠喩はこのようにして分節するだけでなく、神話にまで拡張する。G・レイコフとM・ジョンソンは、主流となる隠喩はある文化やサブ文化における価値を反映し、またそれに影響を与える傾向にあると主張している:例えば、知識は力であり、科学は自然を征服するという広く行き渡っている西欧的隠喩は、客観主義というイデオロギーの保持の中に含まれる(Lakoff & Johnson 1980)。これは、異なる言語は、言葉のあやを介して、経験に空間と時間的な関係に関する異なるシステムを付与すると言うウォーフ流の見方と一致する(Whorf 1956)。
隠喩が表面上の無関係性を基本にしているのに対して、換喩(metonymy)は一つの記号内容をそれに直接関係するか、またはなんらかの方法でそれと密接に関連するもう一つの記号内容の代わりに使用することを含む機能である。換喩は、記号内容間の種々の指標的関連に基づいており、その顕著なものが、原因に対する結果の代入である。これまで見たもっとも良い定義は、次のようなものである。‘換喩は、結びつきによる全体の喚起である。それは、物や関係に対して、ある属性、連想(suggested sense)、または密接に関連したあるものを使用することから成り立つ、たとえば原因に対して結果を用いる...つまり隣接の関係に帰せられるものである’ (Wilden 1987, 198)。それは、付属物(adjuncts、一緒に見出されるもの)や機能上の関連に基づくもの、と見ることができる。これらの形式の多くは、抽象的な指示物を著しく強固なものとするが、何人かの研究者は反対方向の代入(例えば、結果に対して原因)もこれに含めている。部分/全体の関係は、時には換喩の特殊なものまたは別の比喩として区分される。それについては、少し後で触れる。換喩は、次のような代入を含む。
G・レイコフとM・ジョンソンは、次のようなものを含む幾つかのタイプの換喩にも言及している。
彼らは、次のように主張している。(隠喩と同様に)特定の種類の換喩的代入は、我々の考え、態度や行動に影響を及ぼすが、それは概念のある側面を強調しまたその換喩と合わない別の側面を抑圧するためである:
-
ピカソのことを考えるとき、単に美術作品それ自体だけを思い浮かべるわけではない。我々はその美術家に関連したこと、つまり美術に対する彼の考え、彼の技術、美術史における彼の役割などでそれを考える。我々はピカソの作品、それがティーンエイジャーの時のスケッチであっても、ピカソと関連していることから、尊敬の念で接する。同様に、ウエイトレスが、‘あのハムサンドイッチが勘定書を待っています'と言う時も、彼女のその人への関心は、その人自体にある訳でなく、顧客としてだけであり、その文章から人間に関する言葉が消えてしまう。ニクソンは自分で爆弾をハノイに落とした訳でないが、管理される人に対しての管理者という換喩により、‘ニクソンがハノイを爆撃した'と言うだけでなく、爆撃を行っているニクソンを思い浮かべ、それに対して彼に責任があると考える。これは換喩的関連の持つ性質により可能となるが...、その果たす役割は何に焦点をあてるかによる。(Lakoff & Johnson 1980, 39)
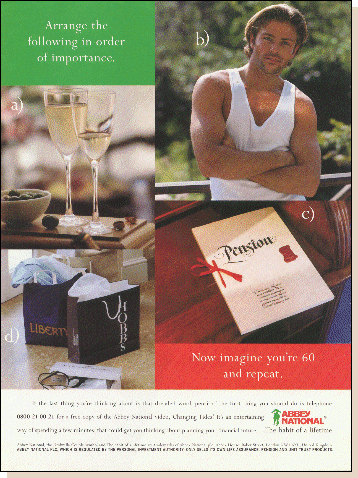 隠喩と同様、換喩も言語的であるとともに視覚的でもありえるかもしれない。ヤコブソンが基本的に換喩的とみなしていた映画では、‘換喩は、そこには存在しない物やそれに関連した主題を表す視覚的に存在する物に適用される’ (Hayward 1996, 217)。ある婦人雑誌のペンションの広告では、読者に4つの写真を重要と思う順序に並べるよう求めている:それぞれの写真は、関連した活動を表現する換喩である(例えば、ショッピングバッグは、商品を表している)。法律が煙草そのものや煙草を喫う人の絵や写真を禁じている国々では、換喩は煙草の宣伝に共通的に用いられる。ベンソン&ヘッジ(Benson and Hedge)やシルクカット(Silk Cut)の宣伝はその良い例である。
隠喩と同様、換喩も言語的であるとともに視覚的でもありえるかもしれない。ヤコブソンが基本的に換喩的とみなしていた映画では、‘換喩は、そこには存在しない物やそれに関連した主題を表す視覚的に存在する物に適用される’ (Hayward 1996, 217)。ある婦人雑誌のペンションの広告では、読者に4つの写真を重要と思う順序に並べるよう求めている:それぞれの写真は、関連した活動を表現する換喩である(例えば、ショッピングバッグは、商品を表している)。法律が煙草そのものや煙草を喫う人の絵や写真を禁じている国々では、換喩は煙草の宣伝に共通的に用いられる。ベンソン&ヘッジ(Benson and Hedge)やシルクカット(Silk Cut)の宣伝はその良い例である。
ヤコブソンは次のように主張している。隠喩的な項目は、相似性に基づいて代入された項目と結びついているのに対して、換喩は隣接や接近に基づいている(Jakobson & Halle 1956,91,95)。換喩の指標性はまた、隠喩の単なる類像性や象徴性とは対照的に、実在に‘直接、結び付いている’ことを示唆する傾向がある。換喩は、通常、直接的な連合を含むので、隠喩よりも明らかに’我々の経験に根ざしている’、と見られる(Lakoff & Johnson 1980, 39)。換喩は、隠喩のようなある領域から他の領域への転移(想像上の跳躍)を必要としない。この違いは、換喩は隠喩よりもより‘自然’であると思わせがちである -それは、換喩がまだ‘新鮮’であるときは文体上、もっと目立つ。換喩的な記号表現は記号内容を目立たせ、隠喩的記号表現は記号表現を目立たせる(Lodge 1977, xiv)。ヤコブソンは、換喩的な様態は散文で際立ち、隠喩的な様態は詩文で目立つ傾向にあることを示唆している(Jakobson & Halle 1956,95-969)。彼は、‘いわゆる現実的な文学’は‘密接に換喩的原理と結び付いている’と示唆している(Jakobson & Halle 1956, 95-96)。そのような文学では、行動は原因と結果に基づくように、また時間と空間が隣接しているように表現されている。換喩は実在主義と関連がある一方、隠喩はローマン主義や超現実主義(シュールレアリズム)と関連している(Jakobson & Halle 1956, 92)。
何人かの研究者は提喩(synecdoche)を別の比喩とみなし、別の研究者は提喩を換喩の特別な形と考え、さらに換喩の中にその機能をまったく含める研究者もいる。ヤコブソンは、換喩と提喩も、近接性(contiguity)に基づいていると記している(Jakobson & Halle 1956, 95)。提喩の定義は、研究者によって(時には大きく)変わる。レトリック学者のRichard Lanhamは、提喩を記述するもっとも共通的な傾向を、‘全体に対して部分を、種に対して類またはその反対を代入すること'として表現している(Lanham 1969, 97)。このように、一つの項が他のものより包括的である。学者の中には、適用の方向に制限を加える人もいる(例えば、全体に対する部分は良いが、部分に対する全体は許さない)。また、ある人は、一つの要素は物理的に他のものの部分である場合のように、提喩をより制限している。幾つかの例を以下に示す:
Stephen Pepperは四つの世界観 -形式論(formism)、機械論(mechanism)、文脈論(contextualism)、有機体論(organicism)であり、それぞれは異なる独自の‘根源的隠喩’を持っている- を、それぞれ相似性、単純機械、歴史的事象そして有機体と関連付けた(Pepper 1942, 84ff)。Meyer Abramsは、Pepperの考えた夫々の世界観は、実在の全体をその部分の用語で表そうとしており、提喩の応用であるとしている (Abrams 1971, 31)。
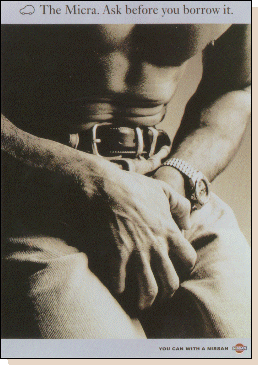 写真や映画というメディアでは、クローズアップは簡単な提喩である -部分が全体を表している(Jakobson & Halle 1956, 92)。まさに、どんな視覚的イメージの形式的枠組み(絵、図、写真、映画およびテレビの枠組み)も提喩として機能する。つまり、それにより提示されているものは、‘生活の断片(slice-of-life)'であり、枠組みの外の世界は枠組の中で描かれている世界と同じように営まれていることを示唆している。枠組が対象を全体的にかつ離散的な一個の実体として包むよりも、枠組みが対象の一部を切り取る方が顕著であることを、これは示している。提喩は、見る人に‘溝を埋める'ようにさせるかまたそれを期待する。そして宣伝では、この比喩をしばしば用いる。ここに示されている広告は、日産の、女性ドライバーを狙った新しいモデル(マーチ?the Micra)のキャンペーンの一部である。その宣伝は幾つかの点で提喩的である:それはクローズアップであり、そして我々は、心理的に枠組を広げることができる;それは‘隠蔽'であり、雑誌の読者は自分の想像力を用いることができる;それは凍結された瞬間であり、前に起こった出来事を推理することができる。
写真や映画というメディアでは、クローズアップは簡単な提喩である -部分が全体を表している(Jakobson & Halle 1956, 92)。まさに、どんな視覚的イメージの形式的枠組み(絵、図、写真、映画およびテレビの枠組み)も提喩として機能する。つまり、それにより提示されているものは、‘生活の断片(slice-of-life)'であり、枠組みの外の世界は枠組の中で描かれている世界と同じように営まれていることを示唆している。枠組が対象を全体的にかつ離散的な一個の実体として包むよりも、枠組みが対象の一部を切り取る方が顕著であることを、これは示している。提喩は、見る人に‘溝を埋める'ようにさせるかまたそれを期待する。そして宣伝では、この比喩をしばしば用いる。ここに示されている広告は、日産の、女性ドライバーを狙った新しいモデル(マーチ?the Micra)のキャンペーンの一部である。その宣伝は幾つかの点で提喩的である:それはクローズアップであり、そして我々は、心理的に枠組を広げることができる;それは‘隠蔽'であり、雑誌の読者は自分の想像力を用いることができる;それは凍結された瞬間であり、前に起こった出来事を推理することができる。
実在を表そうとすると、選択を含むことしかできないので、提喩を含むことになる(しかし、そのような選択は、我々に大きな枠組を直視させようとすることには役立つ)。一般に、指標的な関連は、記号表現が記号内容との間に持っていると見られる最も密接な結びつきを反映している一方、提喩の部分/全体の関連は全ての最も直接的な関連を反映する。より大きな全体の部分を形成すると見られることは、意味していることと実在論的に(existentially)結び付けられる -その存在にとって欠くことのできない部分のように。ヤコブソンは、実在主義的著者による‘提喩的詳細'の利用を記している(Jakobson & Halle 1956, 92)。‘事実に基づく(ノンフィクション)’分野には、‘換喩的虚偽'と呼ばれる危険が潜んでいる(もっと正確には‘提喩的虚偽'であるが)。そこでは、表現された部分が、それが代表している全体の正確な反映として捉えられてしまう -例えば、中流階級の白人女性が全ての女性を代表している(Barthes 1974, 162; Alcoff & Potter 1993, 14)。もちろん枠組は、高度にまた不可避的に選択的である。フィクションの分野では、‘実在主義'は見えなくなったものを、‘不在によって目立つもの'としてより‘なにも言わずに去ったもの(自然なこと)'として扱わせようとする。例えば、主流の映画やテレビドラマを見ている時、ステージの‘部屋’は三つの壁しかないということを知ろうとは望まない。
提喩が、換喩から一般的に分離可能であるかは、何人かの研究者によって議論されている(例えば、 Eco 1984)。提喩が構成することについて、同意しない人もいる。ローマン・ヤコブソンは換喩も提喩も部分によって全体を表すが、換喩は関係が内的であり(船に対して帆)、提喩は関係が外的である(作家に対してペン)、と主張している(Lechte 1994, 63)を見よ)。しかし、これは広く同意されている訳ではない -一般的な使い方として逆の場合も多い(提喩的な関係は、内的なこともしばしばである)。もし、区分が上記のようになされるなら(ヤコブソンには失礼ながら)、狭い意味での換喩は、因果関係のようなもっと抽象的な指標的関係にのみ基づくことになるだろう。提喩に別の地位が与えられたとしても、一般的な使い方を見れば、換喩は(提喩とは区分される)それ自身の狭い意味を持つとともに、指標的結びつきを指す包括的用語であり続けるだろう。
反語法(irony)は、四つの主な比喩のうちで最も過激である。隠喩と同じく、反語的記号表現はあることを意味しているように思えるが、もう一つの記号表現から、それが実際はまったく違ったことを意味していることを知る。(それが通常)言っていることとは反対のことを意味している場合、それは2項対立に基づいている。反語法は話す人や書く人の考えや感覚の反対のことを反映しているかもしれない(嫌悪している時に、‘好きだ'というようなものである)、または外部の実在のついての真実の反対を反映しているかもしれない(人がいないのに、‘人がいっぱいいるなあ’というようなものである)。それは、相違(dissimilarity)や分裂(disjunction)による置換と言える。反語的な陳述は、言葉どおりの意味の反対を意味するが、控えめに言うことや大げさに言うといった変化も反語法として認められる。ある点、誇張も反語法に入るかもしれない。
(皮肉っぽいイントネーションが反語であることを示しているような)反語的記号が話し言葉ではない場合、反語法的状態であるという目印は字義的な記号を越えたところから来る。‘知っているよ'と言う微笑は、手がかりを与える。英国では、1980年代の‘態度としての引用符(air quotes)'(身振りに転換された引用符)が1990年代にも、若い人々の間では、話し言葉としての反語法を目立たせるため、引き継がれている。それは、ちょっと間を置いて、‘違う(Not!)’と付け加える。例えば、‘彼は本当に肉の塊だ(hunk) -いや、違う!'。しかし、反語法は、それを明確にするは難しい。比喩は全て、通常の記号内容に新しいそれを代入し、記号内容を理解するためには言われている事と意味されていることを区別することが必要となる。このように、ある意味、それらは全て2重記号である。しかし他の比喩では、指している物事の中での入れ替えであるのに、反語法は様相(modality)の中での変化である。反語法的記号を評価するためには、その様式の状態に関して、その背後に至る考察が必要である。反語的役割に対する表面上字義的な記号を再評価するには、認識された意図と真理値状態への照会が必要となる。もちろん、反語法的言い方は、それが‘本当'ととられるようにと意図していないので、嘘と同じでない。反語法は、時には‘二重コード'とも言われる。
| 様式の状態 | 葉書のメッセージ | 真理値状態 | 認知された意図 |
| 散文的/事実の | "良い天気だ(The weather is wonderful)" | 真(the weather is wonderful) | 通知する |
| 反語的 | "良い天気だ" | 偽(ひどい天気だthe weather is dreadful) | 可笑しがらせる |
| 嘘 | "良い天気だ" | 偽(ひどい天気the weather is dreadful) | 誤解させる |
このように、反語法は、構造主義者や公式主義者の、意味は内在するという直訳主義者的立場に対してある問題を提示する -それはテキストの内部で嘘をつく。
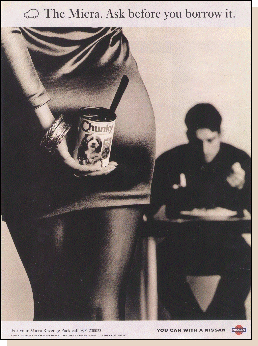 反語法は、記号表現を前面に出す有標の形式である。若い人たちは、自分達が洗練されており、無邪気でないことを示すため、反語法を時々用いる。狭い範囲の使用では、ユーモアの形式として意図される。大部分の使用は、再帰性、分離や懐疑論を伴う。それは、しばしば、人々が言ったことを決して意味せず、また実行しないことを仮定する懐疑的な立場を目立たせる。それを継続的に使用することは、ニヒリズムや相対主義を反映しているかもしれない(全て‘真'でない -またはすべて‘真'である)。反語法は長い由来を持つが、それを使うことは‘ポストモダン'テクストや美術活動の最も大きな特徴となっている。反語法が1対1のコミュニケーションで用いられる場合には、もちろん、それは文字通りの話でなく、反語的であると理解されていることが必須である。しかし、大勢の聴衆に対する場合、全ての人がそれが反語的であると分かっているわけでないので、それは‘きわどい役割(narrowcasting)'の形式となる。ドラマでの反語法は、ドラマの中の人が知らない何かを読者や視聴者が知っているという形式をとる。まえに説明したのと同じキャンペーンからのこの広告は、反語法を効果的に用いている。二人いるのが分かる:焦点が合っていないのが、テーブルで何か食べている男性である;鮮明なクローズアップは、背中にふたが開いた缶を隠した、彼に向かい合う女性である。ラベルを読むと、彼女は彼にドッグフードを与えたのが分かる(というのは、彼は彼女の車を借りる前に使ってよいか尋ねなかったからである -彼女にとって、それほど大事な車である)。
反語法は、記号表現を前面に出す有標の形式である。若い人たちは、自分達が洗練されており、無邪気でないことを示すため、反語法を時々用いる。狭い範囲の使用では、ユーモアの形式として意図される。大部分の使用は、再帰性、分離や懐疑論を伴う。それは、しばしば、人々が言ったことを決して意味せず、また実行しないことを仮定する懐疑的な立場を目立たせる。それを継続的に使用することは、ニヒリズムや相対主義を反映しているかもしれない(全て‘真'でない -またはすべて‘真'である)。反語法は長い由来を持つが、それを使うことは‘ポストモダン'テクストや美術活動の最も大きな特徴となっている。反語法が1対1のコミュニケーションで用いられる場合には、もちろん、それは文字通りの話でなく、反語的であると理解されていることが必須である。しかし、大勢の聴衆に対する場合、全ての人がそれが反語的であると分かっているわけでないので、それは‘きわどい役割(narrowcasting)'の形式となる。ドラマでの反語法は、ドラマの中の人が知らない何かを読者や視聴者が知っているという形式をとる。まえに説明したのと同じキャンペーンからのこの広告は、反語法を効果的に用いている。二人いるのが分かる:焦点が合っていないのが、テーブルで何か食べている男性である;鮮明なクローズアップは、背中にふたが開いた缶を隠した、彼に向かい合う女性である。ラベルを読むと、彼女は彼にドッグフードを与えたのが分かる(というのは、彼は彼女の車を借りる前に使ってよいか尋ねなかったからである -彼女にとって、それほど大事な車である)。
便宜のため、ここに4つの比喩の要約を、言語的な例を付けて示す。
| 比喩 | 基礎 | 言語的な例 | 意図された意味 |
| 隠喩 Metaphor | 差異をものともしない相似性 ( 直喩の場合、顕著) | 採炭切羽で働いた I work at the coalface | ここで、一生懸命働いた I do the hard work here |
| 換喩 Metonymy | 直接的な結合を介した関連付け | 私は背広組みの一人だ I'm one of the suits | 私は管理者の一人だ I'm one of the managers |
| 提喩 Synecdoche | 明白な階層性を介した関連付け | 一般大衆と取引している I deal with the general public | 顧客と取引している I deal with customers |
| 反語法 Irony | 表には出ない直接的な対立 (more explicit in 風刺の場合、もっとはっきりしている) | ここで働くのが好きだ I love working here | ここで働くのは嫌いだ I hate working here |
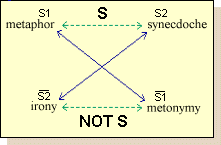 Giambattista Vico(1668-1744)は、通常、(他の比喩が全て、それに還元できる)4つの基本的な比喩として、隠喩、換喩、提喩と反語法を明確にした最初の人物であると信じられている。しかし、区分はPeter Ramus(1515-1572)のRhetoricaにその起源を持つとも言われている(Vico 1968, 129-131)。このように4つの比喩に還元することは、20世紀にアメリカの修辞学者Kenneth Burke(1897-1993)によって、一般に知られるようになった。彼は、それを4つの‘支配的な比喩(master tropes)'と呼んだ(Burke 1969, 503-17)。これらの4つの比喩は、それぞれ、記号表現と記号内容の異なる関係を表している;Hayden Whiteは、これらの関係は、次のことから構成されていると示唆している:類似(隠喩)、近接性(換喩)、重要性(提喩)、‘折り重ね'(反語法)((White 1979, 97))。これらの比喩は至るところにあるので、Jonathan Cullerは(Hans Kellnerに続いて)、‘それらはシステムといえるものまさに固有のシステムを形成し、それにより心が言語で世界を概念的に捉えるようになる’と示唆している((Culler 1981, 65))。記号論的四角形をFredric Jamesonが使ったが、それはこれらの比喩の有用な位置づけを与えてくれる(Greimas 1987, xixにおけるJameson)。ただし、そのような枠組は換喩と提喩の区分に依存するが、そのような用語の定義はバラバラであるか、まったく定義されていないことに注意しよう。Metahistoryという本の中で、Whiteは、4つの‘支配的な比喩'はいろいろな歴史編集スタイルの底に潜む‘深い構造'の役割を果たしていると見ている((White 1973, ix))。それ自身、相似という修辞的行為であるが、Whiteは隠喩、換喩、提喩、反語法を4つの文学分野、Pepperの世界観や4つの基本的思想と結び付けている。C・レヴィ=ストロース流のレトリックを使えば、彼はこれらのいろいろを分類システムを‘構造的には互いに同質'と見ていた。
Giambattista Vico(1668-1744)は、通常、(他の比喩が全て、それに還元できる)4つの基本的な比喩として、隠喩、換喩、提喩と反語法を明確にした最初の人物であると信じられている。しかし、区分はPeter Ramus(1515-1572)のRhetoricaにその起源を持つとも言われている(Vico 1968, 129-131)。このように4つの比喩に還元することは、20世紀にアメリカの修辞学者Kenneth Burke(1897-1993)によって、一般に知られるようになった。彼は、それを4つの‘支配的な比喩(master tropes)'と呼んだ(Burke 1969, 503-17)。これらの4つの比喩は、それぞれ、記号表現と記号内容の異なる関係を表している;Hayden Whiteは、これらの関係は、次のことから構成されていると示唆している:類似(隠喩)、近接性(換喩)、重要性(提喩)、‘折り重ね'(反語法)((White 1979, 97))。これらの比喩は至るところにあるので、Jonathan Cullerは(Hans Kellnerに続いて)、‘それらはシステムといえるものまさに固有のシステムを形成し、それにより心が言語で世界を概念的に捉えるようになる’と示唆している((Culler 1981, 65))。記号論的四角形をFredric Jamesonが使ったが、それはこれらの比喩の有用な位置づけを与えてくれる(Greimas 1987, xixにおけるJameson)。ただし、そのような枠組は換喩と提喩の区分に依存するが、そのような用語の定義はバラバラであるか、まったく定義されていないことに注意しよう。Metahistoryという本の中で、Whiteは、4つの‘支配的な比喩'はいろいろな歴史編集スタイルの底に潜む‘深い構造'の役割を果たしていると見ている((White 1973, ix))。それ自身、相似という修辞的行為であるが、Whiteは隠喩、換喩、提喩、反語法を4つの文学分野、Pepperの世界観や4つの基本的思想と結び付けている。C・レヴィ=ストロース流のレトリックを使えば、彼はこれらのいろいろを分類システムを‘構造的には互いに同質'と見ていた。
| 比喩 | 分野 (‘使用の様相’) | 世界観 (‘プロットの様相’) | 思想 (‘思想的暗示の様相’) |
| 隠喩 | 物語 | 形式主義 | 虚無主義 |
| 換喩 | 喜劇 | 組織主義 | 保守主義 |
| 提喩 | 悲劇 | 機構主義 | 急進主義 |
| 反語法 | 風刺文学 | 文脈主義 | 自由主義 |
Hayden Whiteは西欧の言説(最初は、歴史的書物に基づいていた)において、比喩が用いられていった順序を示唆した。そこでは、主要な比喩はある時代から次の時代へと変化していった -隠喩から換喩、提喩、反語法へと(White 1973)。彼は、Vicoがこの特定の順序の元祖だと解釈しているが、4つの主要な比喩の発達に関するVicoの仮説的歴史的順序は、それは換喩から、提喩、隠喩、反語法へという解釈に対しても開かれているようにも思われる(White 1978, 9)。Whiteは、彼の提示した比喩の発展順序が、認知の発展に関するピアジェ(Piaget)の4段階と、平行線にあることを示唆している。しかし、彼はそのような発展形態における初期の様相が、いかなる意味でも‘劣っている'という暗示を否定している(White 1978, 9)。この推測的な相似性は、子供によるこれらの比喩の獲得が、下に示されている年齢の段階と関連しているという示唆と同じだとと考えられるべきでない。
| Hayden Whiteの比喩の発展順序 | ピアジェ流の認知の発展順序 | フーコーの歴史上の時代に関するWhiteの配置 |
| 隠喩 | 感覚駆動(sensorimotor) 段階(生まれてから約2才まで) | ルネッサンス 時代(16世紀) |
| 換喩 | 前行動(pre-operational)段階(2~6,7才) | 古典主義 時代(17、18世紀) |
| 提喩 | 具体的行動(concrete operations) 段階(6,7才~11,12才) | 近代 (18世紀後半 ~20世紀前半) |
| 反語法 | 形式的行動(formal operations) 段階( 11,12才~大人) | ポストモダン時代 |
ミシェル・フーコーは、次のような大まかに決めた3つの時代について、‘考古学的'研究を行った:‘ルネッサンス'時代、‘古典主義'時代そして‘近代'。彼は、それぞれの時代の底に、認識論(epistemology)があったと論じた。Whiteは次のように示唆している。フーコーが書いたこれらの時代は、ポストモダン時代と合わせると、Whiteが示唆した順序での4つの支配的な比喩を反映している (White 1978, 230-60)。その他、Whiteは次のようにも論じている。フーコーの研究においては、‘全ての“推論の形式”は、その作用を是認する知の体系(エピステーメーepiteme)の限界に至る前に有限回数の転移を経ている。この回数は、比喩を用いること(tropology)の研究で明らかにされた比喩的表現の基本的様相に対応している:隠喩、換喩、提喩そして反語法(それは、ここでは自意識的カテクレシス(catechresis)として理解されている)' (White 1979, 95)。カテクレシスはいろいろ定義されているが、悪口の比喩という定義に基づいている。
フーコー自身も、比喩が用いられていった順序について思索しているが、それはWhiteによって提示された順序と同じものではない。彼は、提喩から換喩へ、カテクレシスまたは隠喩へという3段階の順序で、これを書物や言語の発達と関連付けている。これは、指標的および類像的から象徴的へという言語の進化に関するパースの思索を思い出させる(Peirce 1931-58, 2.299, 2.92, 2.90, 2.280, 2.302)。
-
真の著述は、もはや物自体でなく、それを構成する要素の一つ、またはそれにいつも加わる状況の一つ、またはそれが似ている他の物...を表現しようと試みたとき、始まった。これらの3つの方法は3つの技法を作り出した:エジプト人のキュリオロジック的な書き方(curiological writing)...それは‘全体の代わりに主要な周囲条件を採用している’(戦闘に対して弓、城砦への包囲攻撃に対してはしご);次は‘比喩的(トローパルtropal)’な象形文字文書...それはある顕著な環境条件を採用している(神は全能であり、臣民のすることを全て知っている:彼は目として表現されている);最後は、象徴的な書き方であり、多かれ少なかれ、隠された相似性を利用している(朝日は、その丸い目が水面と同じ高さにあるわにの頭によって表現されている)。ここで、我々は修辞に関する3つの大きな比喩を認識できる:提喩、換喩、カタクレシス。これらの比喩によって敷かれた葉脈を辿ることにより、書くことの象徴的な形式と平行して、これらの言語は進化が可能になった...。
-
どんな表現においても、心は、その表現の1要素へ、それに加えられている環境へ、他のもの、ないもの、それに似ているものやそれを考えた時に記憶に呼び起こされる物に、その表現自体また言語的記号を付け加えることができる。これが言語を発達させ、最初の命名から次第に、漂流させて(drift)させていることは疑いない。最初は、全ての物が名前を持っていた -固有の名前か特殊な名前を。次に、名前はその物の一つの要素に付けられるようになり、その要素を持つ全ての他の個別の物に適用されるようになった:木と呼ばれるのは特定のオークではなく、幹と枝を持つ全ての物である。名前は、はっきりと分かる環境にも付けられるようになった:夜は、この特定の日の終わりを表すのではなく、全ての夜明けから全ての日没を分ける暗い時間を指すようになった。ついには、それはそれ自身を似た物にも付けるようになった:木の葉として薄く、柔らかいものは全て葉と呼ばれるようになった。言語の進歩的な分析とより進んだ分節は、我々が単一の名前を幾つかの物に付けることを可能にしたものであるが、修辞学にとってよく知られている3つの基本的な比喩の方向に沿って発展してきた:提喩、換喩そしてカタクレシス(catachresis)(または、もしすぐに認識できる相似性が少ないなら、隠喩)...。話し言葉の基本で、我々が発見したのは、書き物と同じように、言葉の修辞的次元である:表現の分析により、記号の自由度は、ある内部要素上に、ある隣接点上に、ある似たような比喩の上に整列している(Foucault 1970, 110-11; 113-4) 。
Hayden Whiteの4つの部分からなる比喩を用いるシステムは、彼が最初にそれを使った歴史編集的文脈を越え引用されまた応用されている。そして、そのような枠組の適用は、しばしば啓発的なものである。しかし、その利用には注意が要る。カタクレシス(catachresis)は、全ての比喩的枠組の適用に含まれるか知れない。White自身、‘比喩の配置によって示唆される分野、世界観や思想との親和性’は特定の歴史家における様相の必要な組み合わせと考えるべきでない、と記している。反対に、全ての主要な歴史家の業績を特徴付ける弁証法的力は、筋立て(emplotment)の様相と、議論の様相またはプロットと調和しない思想的意味を結合させようとする努力から生じてくる(White 1973, 29)。三重、四重の区分が生じ、相似によって関連付けられる時、系統化し過ぎる危険が生じてくる。極端な相対論では、全てのものが他の全てのものに似ていると考えられるようになる。現象は、我々の分類システムのように整然としたものではない。システムは、常に漏れるものである(そして、鉛管工事を詩で置き換えることは良いことではない)。自然を科学的に統治しようとした、かのフランシス・ベーコンでさえ、‘自然というものの精妙さは、論理の精妙さに数倍優っている’と見ていた(Bacon 1620, 261-2)。個々の読者が、そのような体系(scheme)の適用がいかに説明のために役に立つか -そして、そのような相似性の限界はなにか- を評価するのは、それを使う状況による。それらは、異常に興味をそそることもあり得るので、それらが記述しようとしたこと以上に‘現実的’にはならないということを強調しておく必要がある。
Whiteは、‘比喩的な言語の四重の分析は、表現法に関して、必然的な二元論的概念に落ち込むことを防ぐという更なる利点を有する’、と論じている。ローマン・ヤコブソンは、基本として、4つより2つを採用している -隠喩と換喩である。Whiteは、ヤコブソンの接近法は、19世紀の文学を‘ロマンチックな -詩的- 隠喩的伝統’と‘現実的な -散文的- 換喩的手法’に分割する還元的二分法を生み出したと感じている(White 1973, 33n)。しかし、ヤコブソンの、2つの極という考えは、大きな影響を与えた。彼は、言語障害の中に、隠喩と換喩が言語と思考にとって基本であるという証拠を見出した。‘言語の2つの側面と失語症2つの型(Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances)’という論文で、彼は、二つのタイプの失語症に関する現存するデータを基に、それらを‘相似性の不調’と‘隣接性の不調’として理解できることを示して見せた(Jakobson & Halle 1956, 67-96)。相似性の不調(similarity disorder)の失語症では、言いたい言葉を選ぶのが困難になり、近接と構造に頼るようになり換喩的(または提喩的)誤りをするようになる -例えば、‘ナイフ’と言いたい時‘鉛筆削り’、または‘フォーク’と言いたい時、‘ナイフ’と言う(Jakobson & Halle 1956,79,83)。隣接性の不調の失語症では、言葉を正しく組み合わせることが難しくなり、隠喩に近い表現を使うようになる -顕微鏡(microscope)を‘スパイの眼鏡(spy-glass)’と呼ぶようになる(同上,86)。
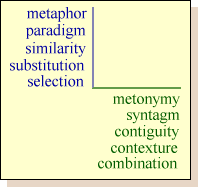 ヤコブソンは、隠喩と換喩または選択と組合せは言語とコミュニケーションの2つの基本軸である、と論じている。隠喩は、範列的次元(選択、換入、相似性に基づく縦軸)であり、換喩は統語的次元(組合せ、構造、近接性に基づく水平軸)である(Jakobson & Halle 1956, 90-96)。C・レヴィ=ストロースのような多くの研究者が、ヤコブソンの枠組を採用したし、また採用している(Levi-Strauss 1974)。ヤコブソンは、フロイトの‘圧縮’を提喩、‘転置’を換喩とみなすように、比喩をフロイトの夢分析に結び付けている (Jakobson & Halle 1956, 95)。ジャック・ラカンは隠喩を圧縮に、換喩を転置に結び付けている(White 1978, 13-14)。Hayden Whiteは、ラカンと同じような関連付けを行うとともに、提喩はは表現に、反語法は第2次性(secondary revision)に結び付けられるとも示唆している (White 1978, 13-14)。映画分析家のChristian Metzは、説話と指示を軸としているが、両者とも相似性と近接性の関係を含んでいる。説話の機能は範列と統語の形で記号表現のレベルで作用し、指示機能は隠喩と換喩の形で記号内容のレベルで作用する(Metz 1982; Silverman 1983, 288)。
ヤコブソンは、隠喩と換喩または選択と組合せは言語とコミュニケーションの2つの基本軸である、と論じている。隠喩は、範列的次元(選択、換入、相似性に基づく縦軸)であり、換喩は統語的次元(組合せ、構造、近接性に基づく水平軸)である(Jakobson & Halle 1956, 90-96)。C・レヴィ=ストロースのような多くの研究者が、ヤコブソンの枠組を採用したし、また採用している(Levi-Strauss 1974)。ヤコブソンは、フロイトの‘圧縮’を提喩、‘転置’を換喩とみなすように、比喩をフロイトの夢分析に結び付けている (Jakobson & Halle 1956, 95)。ジャック・ラカンは隠喩を圧縮に、換喩を転置に結び付けている(White 1978, 13-14)。Hayden Whiteは、ラカンと同じような関連付けを行うとともに、提喩はは表現に、反語法は第2次性(secondary revision)に結び付けられるとも示唆している (White 1978, 13-14)。映画分析家のChristian Metzは、説話と指示を軸としているが、両者とも相似性と近接性の関係を含んでいる。説話の機能は範列と統語の形で記号表現のレベルで作用し、指示機能は隠喩と換喩の形で記号内容のレベルで作用する(Metz 1982; Silverman 1983, 288)。
もっと気軽な雰囲気では、デヴィッド・ロッジ(David Lodge)の小説、素敵な仕事(Nice Work)の中での、隠喩と換喩に関する面白い言い争いがある (Lodge 1988)。
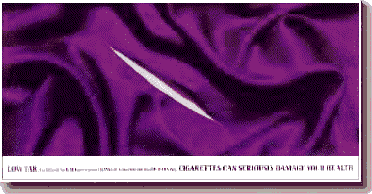 これの典型的な例は、シルクカット(The Silk Cut)の宣伝に関する彼らの騒々しい議論であった...。数マイルごとに道路脇にある掲示板の上に、同じ大きなポスターがあった。それは、小さく波打つ紫色の絹で、あたかもかみそりで切られたような一つの割れ目が入っている写真である。その広告には、喫煙が健康に与える影響に関する政府の警告以外の言葉はなかった。一定の時間ごとに過ぎ去っていく、このよく見かけるイメージは、ロビンをイライラさせまた興味をそそった。彼女は、口当たりの良い表面の下に隠されている深層構造に関する、彼女の記号論的仕事を始めた。
これの典型的な例は、シルクカット(The Silk Cut)の宣伝に関する彼らの騒々しい議論であった...。数マイルごとに道路脇にある掲示板の上に、同じ大きなポスターがあった。それは、小さく波打つ紫色の絹で、あたかもかみそりで切られたような一つの割れ目が入っている写真である。その広告には、喫煙が健康に与える影響に関する政府の警告以外の言葉はなかった。一定の時間ごとに過ぎ去っていく、このよく見かけるイメージは、ロビンをイライラさせまた興味をそそった。彼女は、口当たりの良い表面の下に隠されている深層構造に関する、彼女の記号論的仕事を始めた。
最初、それは判じ物のようだった。つまり、それを解読するためには、シルクカットという銘柄の煙草があることを知らなければならない。そのポスターは、判じ絵のように、そこにない名前の類像的表現である。しかし、類像は、隠喩である。艶めかしくうねり、美しい織物の、かすかに光る絹は、明らかに女性の身体を象徴しており、楕円形の切れ目はそれを通ってくる明るい光により浮き上がってくるが、それはさらにあからさまに女性性器を象徴している。このように、この広告は官能的かつ加虐的(サド的)刺激、女性の身体に入り込みたい欲望とそれを切断したいという欲望に訴えている。 ヴィク・ウイルコックスは、彼女がこの解釈を説明すると、嘲笑を交えて、早口に話し始めた。彼自身は他の銘柄を吸っていたが、それは、ロビンの広告の分析によって、彼の生活態度全てが、脅かされたようであった。‘君はねじれた心をしているに違いない。それは、何の問題もない一片の布だよ'と彼は言った。 ‘じゃあ、これはどう’ロビンは彼を挑発した。‘なぜ、煙草の宣伝に布を使うの' ‘それが煙草の名前だからだろう。シルクカット。それは、その名前の絵であり、それ以上、それ以下でもないよ' ‘もし、カットが半分だったら、どう?’ ‘同じように思うよ、なぜ違うんだい?' ‘カットが半分だと、男性性器のようだからよ' 彼は、当惑を隠すため、無理に笑った。‘なぜ、君は、人々が表面上の価値で物事を理解すると思わないのかね' ‘どのような人たちを指すの?' ‘知識人。インテリ。君は、いつも物事に隠された意味を見つけようとしている。なぜ?煙草は煙草だよ。絹の布は、絹の布だよ。どうして、そのままにして置かないのかね?' ‘何かが表現されたら、それは意味を獲得するのよ、'とロビンは言った‘記号は無害ではない。記号論がそれを教えてくれるわ' ‘記号なんだって' ‘記号論。記号の研究' ‘私は、それは曲がった心を我々に植え付けると思うね' ‘なぜ、ひどくまずい煙草がまず第一にシルクカットと呼ばれるようになったと思います?' ‘知らない。単なる名前だよ。他と同じだ。' ‘“カット(Cut)"は煙草を処理する何かを意味しているんじゃないの?煙草の葉をカットする方法。“プレーヤーの海軍刈り(Player's Navy Cut)” -叔父のウォルターはいつもそれを喫っていたわ' ‘だから、何だと言うんだい?’ヴィクは用心しながら、言った。 ‘しかし、絹(シルク)は煙草になにも作用しない。それは隠喩であり、“絹のように滑らかな”なにかを意味するの。広告代理店の誰かが、のどに悪くない、咳も出ない、また肺癌の原因とならない煙草のイメージとして、“シルクカット(Silk Cut)”という名前を思い付いたんでしょうね。しかし、しばらく経つと、人々はその名前に慣れ、“シルク”という言葉は、意味が無くなってきた。そこで、煙草会社はその銘柄に、再び高級イメージを与えるため、広告キャンペーンを行うことにしたのでしょう。代理店で、切れ目のある小さく波打つ絹(シルク)のアイデアが閃いたのでしょう。最初の隠喩は、文字通り表現されています。彼らが意識的に意図したかどうかは、問題でありません。それは、記号表現の下に、記号内容が滑り込む良い例です’ ウイルコックスは、これについて少し黙って考えそして言った。‘ご婦人方はどうして、それを喫うのかね?’彼の勝ち誇ったような言い方から、これで相手をノックアウトできると考えていることが分かった。‘もし、シルクカットを喫うことが、一種のレイプなら、なんでご婦人方はそれを喫うのだろうかね’ ‘多くのご婦人方は、被虐的(マゾ的)な気質を持っているからよ’とロビンが言った。‘彼女達は、族長世界では何が彼女達に期待されているか、学習してきたの’ ‘はっ!’彼は、頭を後ろに投げ出してうめいた。‘君が馬鹿なことを答えると、知るべきだった。’ ‘貴方が、なんでそんなに興奮するのか分からないわ’とロビンが言った。‘あなた自身は、シルクカットを喫っていないんでしょう’
‘それは、一人ぼっちのカウボーイの広告のそれよね’ ‘私が本当は同性愛者なのだ、とも言うんではないだろうね’ ‘いいえ、それは直接的な、換喩的メッセージです。’ ‘換喩だって?’ ‘換喩的です。記号論の基本的な道具の一つは、隠喩と換喩の区分です。それを、説明しましょうか?’ ‘説明してよ’と彼は言った。 ‘隠喩は、相似性に基づく言葉のあや、換喩は近接性に基づく言葉のあやです。隠喩では、そのこと自体の代わりに意味したい言葉を用い、換喩ではそのこと自体の代わりにその性質または、原因または結果を用います’ ‘一言も分からないよ’ ‘貴方の会社で作っている鋳型を例にとりましょう。底の部分を引かれる物(drag)と言っているのは、それが床の上を引きずられるからです(dragged)。上の部分は、下の部分を覆うので、肩衣(かたぎぬcope)です。’ ‘それは、私が言ったことだ。’ ‘そうですよ。貴方が言わなかったことは、“引かれる物(drag)”は換喩で、“肩衣(cope)”は隠喩、ということよ’ ヴィクは、ぶつぶつ言った。‘どう違うんだい?’ ‘言語がどのように働くかを理解する問題よ。貴方は、物がどのように働くかに興味を引かれているように思いますが’ ‘それが、煙草とどう関係しているか分からないよ’ ‘シルクカットの場合、その写真は、隠喩的に、女性の身体を表現しています:絹の割れ目は、女性性器のようです-’ ヴィクは、その言葉にしり込みした。‘きみが言っているだけだよ’ ‘穴、くぼ地、割れ目そして折れ目は全て、女性の生殖器を表します’ ‘証明してみろよ。’ ‘フロイトが、夢分析によって、それを証明しました’とロビンが言った。‘しかし、マルボローの広告は、隠喩を使っていません。多分、それが貴方がマルボローを喫っている理由でしょう’ ‘何を言ってるんだい’と彼は疑わしげに言った。 ‘貴方は、ものを隠喩的に見ることはあまりしません。貴方にとって、煙草は煙草です’ ‘その通り’ ‘マルボローの宣伝は、記号内容の中に存在する素朴な信用を乱しません。それは、その特定の銘柄と、カウボーイの健康的であり、英雄的である野外生活との間に換喩的な関係 -もちろん完全に見せかけであるが、まことにもっともらしい- を確立します。煙草を買うことによって、その生活スタイルまたはそのように生活するという幻想を買うのです’ ‘くだらん’とウィルコックスは言った。‘田舎と野外は嫌いだ。牛のいるところに行くのは怖いよ’ ‘いいですか、貴方に訴えるのは、宣伝の中のカウボーイの孤独なのよ。独立独歩、自立、男らしさ’ ‘これまでの人生で、そんなに沢山の馬鹿げたこと(balls)を聞いたことがないよ、’とヴィク・ウィルコックスが言った、それは彼から出た強い言葉だった。 ‘馬鹿げたこと(balls)-それは興味深い表現ね...。’ロビンが驚いた。 ‘あ!しまった’彼はうめいた。 ‘貴方が、ある人が“玉を持っている”と肯定的に言う時、それは換喩ですし、あるものが“大変馬鹿げている(lot of balls)”または“混乱している(a balls-up)”と言う時、それは一種の隠喩です。換喩は睾丸に価値を与え、隠喩はそれらをなにか他のものに格下げするのよ’ ‘こんなことは続けられらないよ、’ヴィクは言った。‘煙草を喫って構わないかね?ありふれた、普通の煙草を?’
|
 ‘喫っていないよ。マルボローだよ。奇妙なことだが、その味が気に入っているよ’
‘喫っていないよ。マルボローだよ。奇妙なことだが、その味が気に入っているよ’


