- 意味論:記号とそれが代わりに表現していることとの関係;
- 結合論(または統語論):記号間の形式的または構造的関係;
- 語用論:記号と解釈者との関係 (Morris 1938,6-7)。
-
はじめに(Introduction)
あなたが本屋に行き、記号論の本は何処かと聞いたら、ぽかんとした表情に出会うことになるだろう(訳者:日本では、社会科学の本をおいてある本屋なら、そのようなことはありません)。もっと悪いことに、記号論とはなにかと聞かれるだろう。その質問は、初心者用の手引書を探しているあなたにとっては、少々厄介なものになる。もし、記号論について多少知っていたとしても、事態は少しも良くならない。というのは書店で使われているような簡単な定義を与えることは難しいからである。もし、そのような状況を経験したことがあるなら、聞かない方が賢明であることに納得するだろう。記号論はどのようにも定義できる。最も短い定義は、記号の研究である。それは、質問者にとって納得できるものにはならない。通常、‘記号とはどうゆう意味?’ と聞くだろう。記号と聞いてすぐ心に浮かぶのは、道路記号、パブの記号や星印などの日常生活で見かける ‘記号’ であり、もし、記号論がそれやこれやのすべての記号の研究であると言えば、世間一般の人は記号論が‘見える記号’に関するものだと思うだろう。記号は図面、絵画、写真でもありえると言えば、彼らの思いを確実なものにし、いまや熱心にあなたの注意を美術や写真の部門に向けることになる。もし厚かましく、記号論は言葉や音や ‘身体言語’も含 むと言えば、彼らはこれらのことに共通なものはなんだろう、まただれがどうやってこのようにぜんぜん違った現象を研究できるのだろう、と不思議に思うようになる。もし、あなたが彼らをこれ以上困らせるなら、あなたが変人かきちがいじみた人であることを示唆する記号を読み取り、コミュニケーションは成り立たなくなる。
あなたが、困った質問で本屋の店員さんを悩ませるつもりがないなら、記号論の本は言語の分野から探し始めるのが効率的である(日本では、哲学の書棚にあることが多い)。
 社会生活の一部分としての記号の役割を研究する科学を想定することができる。それは、社会心理学また一般心理学の一部分を形成するだろう。それを、記号学と呼ぼう(ギリシャ語のセミオン'記号’から)。それは、記号の本質とそれを支配する法則を研究する。それは、まだ存在しないので、確かに存在するとは言えない。しかし、それは存在する権利を有し、将来その居場所も用意されている。言語学がその一分野となる記号学が見出す法則は、言語学に適用可能であり、このようにして言語学は人文科学分野に明確な位置を占めるであろう (Saussure 1983, 15-16; Saussure 1974, 16) 社会生活の一部分としての記号の役割を研究する科学を想定することができる。それは、社会心理学また一般心理学の一部分を形成するだろう。それを、記号学と呼ぼう(ギリシャ語のセミオン'記号’から)。それは、記号の本質とそれを支配する法則を研究する。それは、まだ存在しないので、確かに存在するとは言えない。しかし、それは存在する権利を有し、将来その居場所も用意されている。言語学がその一分野となる記号学が見出す法則は、言語学に適用可能であり、このようにして言語学は人文科学分野に明確な位置を占めるであろう (Saussure 1983, 15-16; Saussure 1974, 16)
|
スイスの言語学者の フェルディナン・ド・ソシュール (1857-1913) は、このように記した。彼は言語学だけでなく、記号論と呼ばれているものの創立者でもある(一般言語学講義、1916)。ソシュール(通常はこのように簡略化)の他に、記号論の開発初期の主要な人物としてチャールズ・サンダース・パース (1839-1914) とそのあとのチャールズ・ウイリアム・モリス (1901-1979)がおり、行動主義的(behaviourist)記号論を開発した。現代記号論をリードしている理論家としてロラン・バルト (1915-1985)、アルジルダス・グレマス (1917-1992)、ユーリー・ロットマン (1922-1993)、クリスチャン・メッツ (1931-1993)、ウンベルト・エーコ (1932年生まれ)、ジュリア・クリステヴァ (1941年生まれ) が挙げられる。ソシュールの他にも、多くの言語学者が記号論の枠内で研究を進めた。そのような学者としてルイス・イエルムスレウやローマン・ヤコブソンがいる。ヨーロッパの記号論はもともと構造主義と切り離すことが難しく、そのような構造主義者としてはソシュールの他に、人類学では(研究テーマを記号論の一分野と見ていた)クラード・レビィ=ストロース (1908-2009)、心理分析では ジャック・ラカン (1901-1980) などがいる。構造主義は多くの記号学者が用いた分析手法であり、ソシュールの言語モデルが基になっている。構造主義者は記号システムの全体構造を‘言語’として記述しようとする。クラード・レビィ=ストロースによる神話、婚姻規則とトーテイズム、ラカンによる無意識、バルトとグリマスによる物語の‘文法’などがある。彼らは、現象の‘皮相的な特徴’の下にある‘深層構造’を探ることに努力してきた。しかし、現在の社会記号論は、自己充足的システムの中に存在する部分の内部的関係という構造主義者の関心を超えて、特定の社会状況における記号の使用法の探求に移ってきている。現代記号論は時には、イデオロギーの役割を強調するマルクス主義的研究法と関連付けられている。
全てではないがロラン・バルトの活動の結果、1960年代後半には、記号論は文化研究の主要な方法の一つになり始めた。神話集 (Mythologies)(Barthes 1957) というよく知られたエッセイの英語訳や、それに続く1970年代や1980年代の多くの著作によって、この方法は学問的に良く知られるようになった。1964年の著作により、バルトは次のように宣言している。‘記号学は、記号のどんなシステムも、その内容や範囲がどうであれ、取り入れる:教会、会議や市民ホールで用いられる画像、身振り、音楽、物体やそれら全ての複合体:これらは言語でなくても、少なくとも記号表現システムを構成する’(Barthes 1967,9)。英国において記号論が認知されるようになったのは University of Birmingham の現代文化研究センター CCCS (Center for Contemporary Cultural Studies)の顕著な業績のよるものであり、そのときの所長はネオマルクス主義者の社会学者スチュアート・ホール(Stuart Hall)(1969-1979 所長)である。記号論は、文化研究やメディア研究では余り中心的でないが(少なくとも、初期のより構造主義の形態では)、記号論を理解することはその分野の人に取っては本質的である。勿論、学者にとって知るべきことは、記号論が関心のある研究テーマに光をあてるのに有効であるかどうか、またどうすれば良いか知ることである。ソシュールの用語である‘記号学’はソシュール学派で用いられ、‘記号論’はパース学派で用いられている。しかし、現在では‘記号論’が全分野をカバーする用語として用いられているようである(Noth 1990, 14)。
記号論は、学問上の一分野として余り広く認知されていない。それは、多彩な理論的立場と方法論を含む研究の一分野である。もっとも広い定義は、ウンベルト・エーコの、 ‘記号論は記号として捉えられる全ての事柄に関係する’である (Eco 1976, 7)。記号論は、毎日話すことのなかで ‘記号’と思われることに関するだけでなく、あるものの‘代わりをする’全てのものの研究でもある。記号論的意味では、記号は言葉、画像、音、身振りそして物体の形をとる。一方、言語学者のソシュールにとっては、‘記号学’は‘社会の一部分として記号が果たす役割を研究する科学’であり、哲学者チャールズ・パースにとっては‘記号論’は ‘記号の形式論’であり論理学と密接に関係している (Peirce 1931-58, 2.227)。彼にとっては‘記号は人にとって、ある点からまたは機能に関してあるものの代わりをするなにかである(Peirce 1931-58, 2.227)。彼は‘全ての思考は記号である’と宣言した(Pierce 1931-58,1.538:cf.5.250ff,5.238ff)。現在では、記号学者は、記号を孤立したものとしてではなく、(メディアや範疇のような)記号論的‘記号システム’の部分として研究する。彼らは、意味がどのように作られるかを研究する:コミュニケーションとともに実在 (reality) の確立と保持に関する研究である。記号論と、意味論として知られる言語学のその分野は、記号の意味に関連しているという点では共通している。しかし、John Sturrock は、意味論は言葉が何を意味するかに焦点をあてるのに対して、記号論はどのように記号が意味するかに関するものであると主張している (Sturrock 1986,22)。(次のような三重の分類をパースから導いた)C W モリスによれば、記号論は言語学の他の古典的な分野と同じく、意味論を包含している。
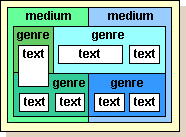 記号論は、しばしばテクストの分析に採用される(それは単なるテクスト分析の1手法以上のものであるが)。ここで、'テクスト’はどんな媒体にも存在し、言語、非言語または両者でありえることに注意する必要がある (この区分には言語中心主義のバイアスが掛かっているが)。テクストという言葉は、何らかの方法(たとえば書き物、オーディオ録音そしてビデオ録音)で記録されたメッセージを指すので、発信者や受信者からは物理的に独立している。テクストは(言葉、画像、音および/または身振りなどの)記号の集合体であり、範疇(genre)ごとの慣例に従ってコミュニケーションの特定の媒体上で生成(そして解釈)される。
記号論は、しばしばテクストの分析に採用される(それは単なるテクスト分析の1手法以上のものであるが)。ここで、'テクスト’はどんな媒体にも存在し、言語、非言語または両者でありえることに注意する必要がある (この区分には言語中心主義のバイアスが掛かっているが)。テクストという言葉は、何らかの方法(たとえば書き物、オーディオ録音そしてビデオ録音)で記録されたメッセージを指すので、発信者や受信者からは物理的に独立している。テクストは(言葉、画像、音および/または身振りなどの)記号の集合体であり、範疇(genre)ごとの慣例に従ってコミュニケーションの特定の媒体上で生成(そして解釈)される。
メディアという用語は、理論家ごとにいろいろな方法で使用され、そして次のような広い分類を含む。スピーチ、書物、印刷物、放送、または大衆メディア(ラジオ、テレビ、新聞、雑誌、本、写真、映画そしてレコード)としての特定の形態または個人間のコミュニケーションのためのメディア(電話、手紙、ファクス、eメール、ビデオ-会議、コンピュータを用いた対話システム)。メディアを‘経路 (channel)’(視覚、聴覚、触覚他)によって分類する理論家もいる(Noth 1995,175)。人間の経験はもともと多感覚的であり、経験の表現はそこに含まれるメディアにより制約され、アフォーダンスに従属している。全てのメディアは、それが用いる経路に制約される。例えば、あの柔軟な言語においてさえ、言葉では表現できない経験がある。そして、従来のメディアでは、匂いや手触りを表現する方法がない。異なるメディアとジャンルは、経験を表現するために異なる枠組みを持ち、ある表現形態を助長し、他を禁止する。このメディアの違いから、Emile Benveniste は複数の記号システムの‘第1原理’は、‘同意語的(synonymous)’でないことであると主張している: ‘実際上は、言語は他の全ての言語記号がそれに翻訳されるある言語記号である’としたイェルムスレェウ(Genosoko 1994,62 に述べられている)に対して、'異なる単位に基づく複数のシステムで "同じこと" を述べることができない'と主張している(Innis 1986, 235 において)。
メディアの使用法を知っている人によるメディアの日常的な利用は、問題の無いものそして また‘中立的’なものとして、間違いなく疑いの無いものになっていく:メディアは目的を達成する手段として進化し、通常、付随的なものになっていくので上記のことは驚くにあたらない。より頻繁にまたより円滑に、あるメディアが使われるようになると、利用者にとってそれはますます‘透明に’または‘見えないように’なっていく。殆どの日常的な目的にとって、メディアを意識させることは、目的を達成するための手段としての有効性を損なう。メディアが透明性を得たとき、その主要な機能を満たすポテンシャルは最大になるのが特徴的なことである。
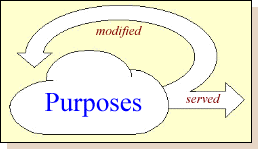
あるメディアを選ぶことは、その人が必ずしも気付ないうちにそれを利用する目的の一部分でない影響を、その使用者に与えるようになる。メディアに余り熟知するとそれが持つ調停作用に‘麻痺’させられてしまう:‘見失ったものは分からない'。そのプロセスに麻痺している限り、その利用において‘選択’を働かせているとは言えない。このようにして、手段が目的を変えていく。メディアの選択によって強調または軽視される現象の中には、あるメディアを使う目的がある。ある場合には、特定のメディアの使用により、‘目的’は微妙に(そして見えないように)再定義されてしまうかもしれない。これは、手段は目的に合うように選ばれまたすべて使用者の管理のもとにあるという実用主義や合理主義と反対の立場にある。
メディアのこの変換現象を知っているメディア理論家は、技術的手段やシステムはいつもそして必然的に‘それ自身が目的’になる(マーシャル・マクルーハンの有名な格言、‘メディアはメッセージである’と同じ考えである)と断定的に主張する。そしてメディアをそれ自身が(機能と反対に)‘目的’を持つまったく自立的な実体として表す。しかし、メディア化の過程に含まれる変換を認めるにしても、そのような極端な立場をとる必要はないであろう。どんな目的にメディアを使う場合でも、それを使うということが目的の一部となる。どこかかへ行くためには、移動することが不可欠である:そして、それが主な目的になるかも知れない。ある特定の交通手段を用いて移動することは、経験の一部分である。何かの目的のためにメディアを使うとき、その利用が目的の一部となる。話すことではなく書くこと、ペンではなくワードプロセッサを用いることもまたそうである。ある媒体を利用するとき、それがわれわれに役立つのと同様に、ある程度、我々もそれの目的のために役立っている。メディアに関るとき、メディアに働きかけまた働きかけられ、使い使われている。メディアは多様な機能を持っているので、これらの機能の一つを単独で作用するように選ぶことはできない。そのような媒体を用いた意味の作成には、ある程度の妥協が含まれるに違いない。ある特定の目的と媒体の機能が完全に一致することはめったになく、多くの場合、ある程度一致すれば適切なものとして受け入れられることになるだろう。
ここで、人類学者のクラード・レビィ=ストロースが(玉突きの)間接打ち (bricolage)と呼んだ次のような観察を思い出す。あるものを創作する過程は、計算された選択の賜物でもないし、また使用した素材が前もって明確に決めておいた目的に技術的に最も良く適合していたからでもなく、むしろそれが‘素材や実行手段との対話’を含んでいたからである (Levi-Strauss 1974,29)。そのような対話では、手元にある材料が(我々が言うように)行為の適応的な方向を‘示唆’し、最初の狙いが修正されるかもしれない。その結果、創造の行為は、純粋に機械的なものではなくなる:間接打ち (bricoleur) は‘物とだけでなく...物の媒体を介しても "話す"’(ibid. ,21):媒体の利用には意味がある。クラード・レビィ=ストロースの指摘の文脈は‘神話の思想’の討論であったが、(玉突きの)間接打ちはどの媒体の利用またどんな目的にも含まれていると、私は主張したい。たとえば書くという行為は、著者の意識的な目的だけでなく、そこに含まれる仲介の社会的かつ心理的プロセスとともに、 -言語の種類や記述の道具のような- 用いられている媒体の特徴によって形成される。素材によって提示される、いかなる著者の‘抵抗’も、書くというプロセスの本質的な部分になりうる。しかし、全ての著者が間接打ちのように行動し、感じるわけでない。個人で、媒体変換という考えに対する反応は著しく異なる。その範囲は、‘利用している’メディアを全体的に管理していると主張する人たちから、彼らを‘利用している’メディアによって形成されているという感覚を経験した人たちにまで及ぶ(Chandler 1995)。
Norman Fairclough は、各種のマス・メディアが依存している種々の経路や技術の間の差異の重要性について、次のようにコメントしている。
- 新聞は視覚的経路を利用し、その言語は書かれそして写真複製、グラフィック・デザインそして印刷の技術に依存しる。それに対してラジオは、聴覚の経路や話された言語を利用し、録音技術や放送技術に依存している。一方テレビは、録音と録画と放送技術の組み合わせである。
経路や技術におけるこれらの差異は、異なる媒体の意味のポテンシャルという点で重要でより広い含みを有している。たとえば、印刷はラジオやテレビより個人が重要な意味を持たない。ラジオでは個性や人柄が、声の個性を伝えることを通して前面に出てくる。テレビは人々が視覚的に、それも新聞の写真のように固定された様相でなく、動きと動作で知ることを可能とし、それにより個性や人柄をより前面に出す。(Fairclough 1995, 38-9)
一方、 技術決定論者は、次のように強調する。記号の生態は、異なる媒体における設計の基本的な特徴に影響される、つまり、異なるメディアが使われていく過程を形成する社会・文化的また歴史的な要因と、ある特定の文化的文脈での種々のメディアの(絶えず移っていく)地位を認識することが重要である。たとえば、多くの現代文化の研究者は、現代社会のコミュニケーション機能は、言語的なメディアより見るメディアがその重要性を増しておりまた、またそのようなメディアでのコミュニケーションに関連したシフトが起きていると言っている。異なった記号構造や言語の相互作用を‘生態的’用語で考察することにより、ロシアの文化記号学者のユーリー・ロットマンは‘検討対象としている文化の全体の記号空間を表すため'‘記号世界(semiosphere)’という言葉を作り出した(Lotman 1990, 124-125) 。この概念は生態学者の‘生物世界 (biosphere)’と関連し、Teilhard de Chardin の用語‘noosphere(人間の知的活動の総体)’ -心が験される領域- (1949年まで戻るが)を思い出させる。これは、文化学者が公的および私的世界と呼ぶものに関連付けられる。ロットマンは、文化において言語の機能を支配するものとして記号空間という言葉を用いたが、John Hartley は次のようにコメントしている。‘記号空間を同定できる複数のレベルがある -例えば、一つの国や一つの言語文化のレベル、"欧米" のようなもっと大きい単位のレベル、さらには "人類 (the species)" にまでおよぶ’;同様に特定の時代の記号世界も特徴付けられるかも知れない (Hartley 1996, 106)。この記号世界という概念は、批判者に対して記号学者は帝国主義者のようであると思わせるかもしれない。しかし、真空の中に存在するようなメディアを個々に研究するよりは、記号過程という統一的で動的な視野を提示できる。
勿論、テクスト分析には、記号論とは別の方法もある-とりわけ、レトリック分析、談話分析そして‘内容分析’である。メディアとコミュニケーションの分野では、テクスト分析の方法としては、内容分析が記号論の突出した競争相手である。記号論が文化研究に密接に関連しているのに対して、内容分析は社会科学研究の主流として伝統的に確立されている。内容分析はメディアテクストの目録的な‘内容’分析への定量的な接近方法であるのに対して、記号論は構造化された全体像としてテクストを分析しようとし、潜在的な共示的意味を調べる。記号論は定量的でなく、しばしばそのような接近法を退ける。ある項目がテクストの中にしばしば出現するからと言って、それを重要なものとはしない。構造主義記号学者は、要素間の関係を強調する。社会記号学者は、テクストの中の記号に読者が付与する意味の重要性を強調する。内容分析が明示された内容に焦点をあて、これが単一の固定された意味を表現すると示唆する傾向にあるのに対して、記号的研究はメディアテクストに含まれる‘談話’を支配する規則に着目し、意味を形づくるのに記号的文脈がはたす役割を強調する。しかし、何人かの研究者が記号分析と内容分析を組み合わせるようになっている(たとえば、 Glasgow University Media Group 1980; Leiss et al. 1990; McQuarrie & Mick 1992)。
何人かの解説者が、記号論に関する C・W・モリスの定義、‘記号の科学’を(ソシュールの精神で)用いているが、'科学’という言葉は誤解を招く(Morris 1938, 1-2)。いまだ、記号論は広く認められた理論的仮説、モデルや代表的な方法論を持っていない。記号論は多分に理論的であり、多くの理論家が領域と一般原理を確立しようと努めてきた。例えば、パースとソシュールの両者とも、記号の基本的定義に関心を持っていた。パースは、記号の型に関する精巧で論理的な分類法を開発した。その後の記号学者も、それにより記号が組織されているコードや慣習を明確にし、分類しようとしてきた。明らかに、多くの競合する理論的仮説がある特徴的な主題に対しては、確固とした理論的基盤作りを行う必要がある。方法論に関しては、ソシュールの理論がテクストと社会現象を分析するために用いられる種々の構造主義的方法論の開発の出発点を築いた。これらは、多くの文化現象の分析のために用いられている。しかし、そのような方法は広く認知されていない:社会主義指向の理論家は、ソシュールの方法が余りに構造にばかり注目していると非難しているが、それに代わって広く用いられている方法論はまだない。一方、経験指向の記号論研究もあり、記号原理を適用しテストしている。Bob Hodgeと David Tripp は子供とテレビに関する古典的な研究に、観察による方法を採用した (Hodge & Tripp 1986)。現時点で、これまでの研究の蓄積の上に構築された統合的試みとしての記号論への動きは、あまり感じられない。
記号論は独立した学術分野というより、芸術、文学、人類学やマス・メディアなど複数の領域にまたがる研究である。記号学者と言われる人には、言語学者、哲学者、心理学者、社会学者、人類学者、文学者、美学者やメディア研究家、心理分析家や教育学者が含まれる。もっとも基本的な定義から一歩出ると、記号論に何が含まれるかということについては、指導的な記号学者の間でも意見が分かれている。それは(意図的な)コミュニケーションだけでなく、我々がこの世のあらゆるものに意味を帰属させることに関する研究である。初期の記号論的方法の弱点を克服しようとして、記号論は時とともに変化し、記号論の基本的な用語にさえ、多様な定義ができてしまった。その結果、記号論的分析を行おうとする人はだれでも、どの定義を適用したかまた特定の記号学者の方法を使用する場合には、その出典を明記した方が良い。記号論には、ソシュールとパースから出た大きな二つの流れがある。ルイス・イエルムスレウ、ロラン・バルト、クラード・レビィ=ストロース、ジュリア・クリステヴァ、クリスチャン・メッツ、ジャン・ボードリアール (1929年生まれ) の研究はソシュールの‘記号学’の系統に属する。一方、チャールズ・W・モリス、イボール・A ・リチャード (1893-1979)、チャールズ・K・オグデン (1889-1957) やトマス・シービオク (1920年生まれ) は、パースの‘記号論’の系統に属する。これら二つの系統を結ぶ指導的な記号学者が、有名なイタリア人作家ウンベルト・エーコである。ベストセラーのバラの名前(小説は1980年、映画は1986年)の作家として、肖像権が価値をもっている唯一の記号学者である (Eco 1980)。
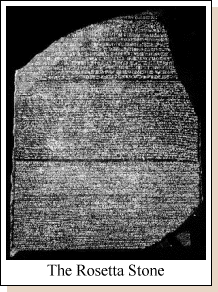 ソシュールは‘記号学上の問題を明らかにするには、言語の研究以上のものはない’と主張した (Saussure 1983, 16; Saussure 1974, 16)。記号論は言語的な概念に大きく頼ってきた。これは部分的にはソシュールの影響であり、言語学が他の記号システムよりも確立された分野であるためである。構造主義者は広範囲の社会現象を探求するためのモデルとして言語を用いてきた:クラード・レビィ=ストロースの神話、婚姻、トーテム;ラカンの無意識;バルトとグリマスの物語の‘文法’などである。ジュリア・クリステヴァは以下のように言っている。‘記号論が発見したのは、社会現象を支配する法則、またはそれに影響する主な制約はそれが表示することの中にある、ということである;つまりそれは言語のように分節されるということである’(Hawkes 1977, 125に述べられている) 。ソシュールは、言語(彼のモデルは話し言葉であるが) を記号に関する全てのシステムの中で‘最も重要なもの’とみなした(Saussure 1983, 15; Saussure 1974, 16)。言語は、これまでずっと、最もパワフルなコミュニケーション・システムであるとみなされてきた。例えば、Marvin Harrisは次のように述べている。‘人間の言語はコミュニケーション・システムの中で意味の普遍性を持っているという点でユニークである...。意味の普遍性を持っているコミュニケーション・システムは過去、現在、未来の全ての相、分野、属性、場所、出来事に関する情報、それが実際のものか可能性のあるものか、現実か虚構であるかいずれにせよ、を伝達することができる’(Wilden 1987, 138で言及されている) 。多分、言語は本当に基盤的である:Emile Benvenisteは‘言語は、言語的または非言語的な他の全てのシステムの解釈システムである’(Innis 1986, 239の中で)。一方、C・レヴィ=ストロースは次のように記している、'言語は優れて(par excellence)記号システムである;しかし、それは意味することはできない、そして意味作用を通してのみ存在する’((Levi-Strause 1972,48))。
ソシュールは‘記号学上の問題を明らかにするには、言語の研究以上のものはない’と主張した (Saussure 1983, 16; Saussure 1974, 16)。記号論は言語的な概念に大きく頼ってきた。これは部分的にはソシュールの影響であり、言語学が他の記号システムよりも確立された分野であるためである。構造主義者は広範囲の社会現象を探求するためのモデルとして言語を用いてきた:クラード・レビィ=ストロースの神話、婚姻、トーテム;ラカンの無意識;バルトとグリマスの物語の‘文法’などである。ジュリア・クリステヴァは以下のように言っている。‘記号論が発見したのは、社会現象を支配する法則、またはそれに影響する主な制約はそれが表示することの中にある、ということである;つまりそれは言語のように分節されるということである’(Hawkes 1977, 125に述べられている) 。ソシュールは、言語(彼のモデルは話し言葉であるが) を記号に関する全てのシステムの中で‘最も重要なもの’とみなした(Saussure 1983, 15; Saussure 1974, 16)。言語は、これまでずっと、最もパワフルなコミュニケーション・システムであるとみなされてきた。例えば、Marvin Harrisは次のように述べている。‘人間の言語はコミュニケーション・システムの中で意味の普遍性を持っているという点でユニークである...。意味の普遍性を持っているコミュニケーション・システムは過去、現在、未来の全ての相、分野、属性、場所、出来事に関する情報、それが実際のものか可能性のあるものか、現実か虚構であるかいずれにせよ、を伝達することができる’(Wilden 1987, 138で言及されている) 。多分、言語は本当に基盤的である:Emile Benvenisteは‘言語は、言語的または非言語的な他の全てのシステムの解釈システムである’(Innis 1986, 239の中で)。一方、C・レヴィ=ストロースは次のように記している、'言語は優れて(par excellence)記号システムである;しかし、それは意味することはできない、そして意味作用を通してのみ存在する’((Levi-Strause 1972,48))。
ソシュールは言語学を‘記号学’の一部門と見ていた。
-
言語学は、この一般科学[記号学]の一部門に過ぎない。記号学が発見する法則は言語学に適用できる法則である...。我々に関する限り....、言語学的問題は第一のかつ主要的な記号学的問題である...。言語システムの本質を発見しようとしたら、同じような性質を持つ全ての他のシステムと共通しているものは何か、第一に考えなければならない...。このようにして、光が言語学の上だけでなくあてられる。儀式や習慣を記号として考えることにより、それらに新しい視点を与えられると信じている。それらを記号的現象として捉え、記号学の規則に関する用語でそれを説明する必要があるように感じられる (Saussure 1983, 16-17; Saussure 1974, 16-17)。
ロラン・バルトは‘多分、ソシュールの定式化を逆転し、記号学は言語学の一分野であるということを主張しなければならないだろう’と言っていたが,他の人たちは記号論の中の言語学の占める位置を受け入れている(Barthes 1985, xi)。彼自身の他に,Jean-Marie Floch はイェルムスレウとグレマスを例に引いている(Floch 2000, 93) 。しかし、たとえ理論的に言語学を記号論の中に位置付けたとしても、言語モデルを使わないで他の記号システムを探求することは難しい。記号学者は共通して、テクストとして映画、テレビやラジオ番組、宣伝ポスターなどまた‘テレビを読むこと’に言及している(Fiske and Hartley 1978) 。記号学者によっては、テレビや映画のようなメディアはいくつかの点で‘言語’のようなものであると認めている。この主張は、映画は日常生活の‘現実’により近いかどうか、書物のような象徴システムと共通点をもっているかどうかといった辺りを循環している。言語よりもメディアの‘文法’に言及する研究者もいる。James Monaco は‘映画は文法を持っていない’と主張し、映画技術と自然 言語の文法との表面的な相似性に対する有益な批評を提示している (ibid., 129)。すべてのメディアを、言語的なフレームワークに押し込めようとするのは危険である。写真(映画やテレビも同じというかもしれないが)については、Victor Burgin が次のように主張している:'写真には‘言語’、つまり全ての写真がそれに依存できる(技術的用具と反対に)単一の意味システムはない(英文のテクストは全て、英語という言語に依存しているという感覚で);むしろ、写真が依拠するコードの異種複合体が存在する' (Burgin 1982b, 143)。
ここで、ソシュールの記号モデルを簡単に検証するが、その前に彼がそれをその中に位置付けた一般的な枠組みをある程度理解することが重要である。ソシュールは、かの有名なラング(langue)(言語)とパロール(parole)(話し言葉)という有名な区分を作った。ラングは、個々の使用者から独立し先在する規則システムである;パロールは、特定の例でのラングの使用である。この考えを単純に言語に適用するのではなく、もっと一般的な記号システムに適用すると、この違いはコードとメッセージ、構造と事象、またはシステムと(特定のテクストまたは文脈における)その慣習(usage)の違いになる。ソシュール流の区分によれば、映画のような記号システムにおいては、‘特定の映画は、映画言語という潜在システムの話し言葉である’ (Langholz Leymore 1975, 3)。ソシュールは、パロールよりラングを重視した。ソシュール派の記号学者にとってはもっとも重要なのは、伝統的に記号システムの単なる使用例としての特定の行為や実践よりも、記号システムの潜在的な構造や規則である。ソシュールの方法は、(映画のように)時間と共に進化する通時性よりも、むしろ(写真のように)あたかも時間が固定されたようなシステムの共時性を研究する。構造主義文化学者は、記号システムとしての社会および文化現象の機能に焦点をあてるソシュール流の優先順位を採用する。理論家たちは、システムが先行しその慣習を決定するのか(構造決定主義)、慣習が先行しシステムを決定する(社会決定主義)のかで意見が分かれている(しかし大部分の構造主義者は、システムが慣習を完全に決定するというよりは、制約すると主張していることに注意して欲しい)。
慣習とシステムの構造主義的二分法は結果から過程を、構造から主体を切り離すその硬直性を批判されてきた (Coward & Ellis 1977, 4, 14)。慣習より構造を重視するこの考え方では、構造の変化を説明できない。マルクス主義者はとくにこの点を批判してきた。1920年代後半、Valentin Volosinov (1884/5-1936) とミハエル・バフチン (1895-1975) は、ソシュールの共時的手法と言語システムの内部関係を強調する考え方を批判したVoloshinov 1973; (Morris 1994)。Volosinovは、ソシュール流のパロールに対するラングの優位性を逆転した:‘記号は、組織化された社会的意思交換の部分でありその外部では存在できず、ただの物理的人工物に戻ってしまう’(Voloshinov 1973, 21)。記号の意味は、言語システムの他の記号との関係の中にあるのでなく、それを使用する社会的文脈の中にある。ソシュールは歴史性を無視したことでも批判されている (ibid., 61) 。プラハ学派の言語学者のロマン・ヤコブソンと Yuri Tyanyanov は、1927年に‘純粋な共時性は幻想に過ぎない’と言明し、‘全ての共時システムは、お互いに分離できないシステムの構造的要素として過去と未来を有している’と付け加えている (Voloshinov 1973, 66) に記述)。1929年の著述で、 Volosinov は次のように観察している。‘現実には、言語の共時システムが構築されたことはない...。共時システムは、ある特定の言語グループに属する個々の話し手の、歴史のある瞬間における主観という観点からは存在するといえるかも知れない’(Voloshinov 1973, 66)。フランスの構造主義者クラード・レビィ=ストロースは共時的方法を人類学の分野に適用したが、多くの記号学者は歴史性と社会的文脈を再び重要視するようになってきている。言語は前の世代から受け継いだ静的、閉じたかつ安定したシステムでなく、常に変化しているシステムとして扱われるべきである。 記号は、Volshinov が述べているように、‘階級闘争の闘技場’である(ibid., 23)。真の‘社会記号論’を確立するために、Robert Hodge と Gunther Kress は‘記号システムの社会的な次元は性質と機能にとって本質的であり、システムだけを孤立して研究できない’と述べている(Hodge & Kress 1988, 1)
ソシュールは、記号論の創始者として認められているが、記号論はどんどんソシュール流でなくなっている。Teresa de Lauretisは1970年代に始まった構造主義的記号論から離れていく動きを次のように記述している。
-
10年前から、記号論は理論的ギアシフトを経験している:そのシフトは、記号システムの分類 -基本単位、構造的組織のレベル- から離れ、記号や意味が生成される形態や、システムとコードが社会的営みの中でいかに使われ、いかに変換されまたその枠を越えていく方法の探索へと向かっている。以前はメッセージを生成する機構と見なされていた(言語、文学、映画、建築、音楽他の)記号システムの研究が主体であったが、今はそれを介してなされる作用が主に検討されている。それはコードを構成しかつ/または変える行為または活動であるが、同時にコードを用いてその行為をなす個人を構成し、変化させていくことになる;このため、個人は記号過程の主体となる。
チャールズ・サンダース・パースから借りてきた‘記号過程’という用語は、エーコによって、ある文化が記号を作り、かつ/または記号に意味を付与する過程を指すために拡張された。エーコにとっては、意味の生成または記号過程は社会的活動であったが、記号過程という個人的活動に主観的要因が含まれることを認めている。その見解は、現在またはポスト構造主義的な記号理論の二つの流れに沿ったものである。一つは意味作用の主体的側面に焦点をあてたものであり、意味は主体-作用として解釈される(主体は記号表現の作用である)ラカン流の心理分析に強く影響されている。他の一つは意味作用、つまり個人間のコミュニケーションにおけるその実際的、倫理的、イデオロギー的利用の社会的側面に重点をおいた記号論である;そこでは、意味は文化的に共有されたコードを通して生産される意味論価値として解釈される。 (de Lauretis 1984, 167)
このテキストは、 記号論のキー概念 の概要を、主要な批判と共に示す。まず最初は、最も基礎的な記号の概念そのものから始める。それが、読者が進む方向を見つけることができる一助になればと期待している。しかし、この興味をそそられるが知ることを強要する主題の探求にとりかかる前に、なぜそんなに悩まなくてはならないか考えてみよう:なぜ記号論を学ばなくてはならないのだろう。記号学者の著述はたわごとに満ちているとの評判なので、これはなかなか切実な問題である:Justin Lewis は‘その主唱者は、読みにくくまた理解できないスタイルで書いている’と述べている (Lewis 1991, 25);他にもウイットに富んだ批判がある‘記号論は、我々が既に知っていることを決して理解できない言葉で語ってくれる’(Paddy Whannel, Seiter 1992,1 に記述))。記号論の上流階級は非常に排他的クラブであるが、David Sless が言っているように、‘記号論は非常に重要であり、記号学者に任せておけるような事業ではない'(Sless 1986, 1)。
記号論は、'実在 (reality)’とは人間の理解とは独立な、純粋に客観的な存在を有する何物として認められていると考えるべきではない、ことを教えてくれる点で重要である。実在とは記号のシステムであることを教えてくれる。記号論を学ぶことは、構文としての実在や、その作成において我々自身と他の人が演ずる役割を知ることを助けてくれる。また、情報や意味は、世界や本、コンピュータや視聴覚ビデオの中に‘含まれて’いないことを理解することを助けてくれる。意味は、我々に‘伝えられる’のではない -通常気付いていないコードや慣習の複雑な相互作用により、我々が積極的に作り出す。そのようなコードを知ることは本来、魅惑的で知的な力を与える。記号論から、我々は記号の世界に生きており、記号とそれを組織しているコードを通さなくては何事も理解できないことを知る。記号の研究を通して、記号とコードは通常は透明であり、それらを読もうとする我々の企てを欺こうとするにも気付く。増大する視覚的記号の世界に生きている今、もっとも‘真に迫った (realistic)’記号さえもそうであるように思われるものと違うことを習得する必要がある。記号が理解されるコードを明らかにすることにより、記号を‘変質’させるという、貴重な記号的機能を達成できるかもしれない。実在を規定する際には、記号はイデオロギー的機能を果たす。記号の実在性を解体し論争することは、誰の実在に特権が与えられ、誰の実在が抑圧されているかをはっきりさせることに役立つ。記号の研究は、実在の構築と保持の研究である。そのような研究を衰えさせることは、我々が住んでいる意味の世界の管理を他人に任せることになる。


