- ‘記号表現 (signifier)’(シニフィアン:sinifiant) - 記号がとる形
- ‘記号内容 (signified)’(シニフィエ:sinifie) ‐ それが表現する概念
- 記号表現:open という言葉;
- 意味内容としての概念:店は営業中である。
- 代表項 (The Representamen):記号の形(必ずしも物質的でない);
- 解釈項 (An Interpretant) :解釈者でなく、むしろ記号により作られる観念;
- 対象 (An Object):記号が指示するもの 。
- 記号負荷体 (Sign vehicle):記号の形体;
- 意義 (Sense) :記号により作られる意義;
- 指示物 (Regferent) :記号が表すもの;
- たまたま同じように綴られまた発音されるが、意味は異なる単語はトークンに含めるべきか?
- 大文字は、対応する小文字と同じタイプの具体例か?
- イタリック体で印刷された単語は、ローマ字体の同じ単語は同じタイプの具体例か?
- Xと言う人によって書かれた単語とYという人によって書かれた単語は同じか?
(Lyons 1977, 13-15) - ‘同じタイプの、単数または複数のトークン(複製)がある記号’(例えば、印刷された単語、または同じ色の全く同じモデルの自動車);
- ‘そのトークンがあるタイプから製造されたとしても、材質的には独自性を持った記号’(例えば、ある人が話したまたは手書きされた言葉);
- ‘そのトークンがそのタイプである、またはタイプとトークンが同一の記号’(例えば、唯一の原画である油絵またはダイアナ王女の結婚衣裳)。
(Eco 1976, 178ff) - 観念的超機能(ideational metafunction):‘ある記号システム外部の経験的世界の様子を -指示的または擬似の指示的意味で- 表現する’;
- 個人間超機能(interpersonal metafunction):‘記号の生産者...とその記号の受信者/再生産者の関係を反映する’; そして
- テクスト的超機能(textual metafunction):‘内部的にそしてそれが作られた文脈の中で凝集する、記号の複合体としてのテクストを形成する’。
(Kress & van Leeuwen 1996, 40-41)
Semiotics for Beginners
-初心者のための記号論-
Daniel Chandler (University of Wales)
 我々は、意味を作る欲望に動かされている種のように思われる:我々は、まさしくホモ・シニフィキャンズ (Homo sinificans)、意味の作成者である。特徴的なことは、我々は‘記号’の生成と理解を通して意味を作り出すことである。まさしく、パースの言う通り‘我々は、記号でのみ思考する’ (Peirce 1931-58, 2.302)。記号は言葉、画像(images)、音、匂い、味、動作やものの形をとるが、それらは本来意味を有しているものではなく、それらに意味をまとわせるとき記号となる。‘記号として理解されなければ、なにものも記号ではない’とパースは言っている(Peirce 1931-58, 2.172) 。なにものも誰かがそれが何かを意味している - つまり、それ以外の何かを指示するか、なにかの代わりをしている - と思えば記号になりうる。我々は、物事を慣習というおなじみのシステムに関連付けることにより、ほとんど無意識のうちに記号として理解している。記号論の関心の中心は、記号のこの意味に富む使用についてでである。
我々は、意味を作る欲望に動かされている種のように思われる:我々は、まさしくホモ・シニフィキャンズ (Homo sinificans)、意味の作成者である。特徴的なことは、我々は‘記号’の生成と理解を通して意味を作り出すことである。まさしく、パースの言う通り‘我々は、記号でのみ思考する’ (Peirce 1931-58, 2.302)。記号は言葉、画像(images)、音、匂い、味、動作やものの形をとるが、それらは本来意味を有しているものではなく、それらに意味をまとわせるとき記号となる。‘記号として理解されなければ、なにものも記号ではない’とパースは言っている(Peirce 1931-58, 2.172) 。なにものも誰かがそれが何かを意味している - つまり、それ以外の何かを指示するか、なにかの代わりをしている - と思えば記号になりうる。我々は、物事を慣習というおなじみのシステムに関連付けることにより、ほとんど無意識のうちに記号として理解している。記号論の関心の中心は、記号のこの意味に富む使用についてでである。
記号を構成するものに関しては、二つの主要なモデル、言語学者フェルデナン・ド・ソシュールと哲学者チャールズ・サンダース・パースのモデルがある。これらは、順次議論していく。
ソシュールは記号の‘二項’または2要素モデルを提案し、記号が次のように構成されていると定義した:
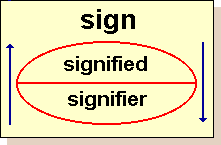 記号は、記号内容と記号表現の連合から生じる全体であるSaussure 1983, 67; Saussure 1974, 67)。記号表現と記号内容の間の関係は、‘意味作用’と呼ばれ、ソシュール流の図では、矢印で表される。二つの要素を区分する水平線は‘さく(bar)’と呼ばれる。
記号は、記号内容と記号表現の連合から生じる全体であるSaussure 1983, 67; Saussure 1974, 67)。記号表現と記号内容の間の関係は、‘意味作用’と呼ばれ、ソシュール流の図では、矢印で表される。二つの要素を区分する水平線は‘さく(bar)’と呼ばれる。
言語の例で、‘Open’という言葉は(店の戸口で、それに見た人によって意味が与えられたとき)、次のような構成の記号である:
記号は記号表現と記号内容の両者を有していなければならない。まったく意味の無い記号表現や、完全に形のない記号内容はありえない(Saussure 1983, 101; Saussure 1974, 102-103)。記号というのは、記号表現と特定の記号内容の認識可能な組み合わせである。同じ記号表現(‘open’という言葉)は、それがエレベータの押しボタンの上にあれば(ドアを開けるためには押すこと)異なる記号内容を表す(これは違う記号になる)。同様に、多くの記号表現が‘open’という概念を表すことができる(例えば、包装用ボール箱の上の‘この端を開けろ’ということを示すためのたれがついた箱状の小さな外形) - 再び言うが、それぞれの組み合わせは、別の記号を構成する。
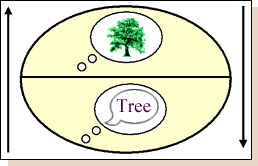 現在、基本的な‘ソシュール流の’モデルが共通的に採用されているが、ソシュール自身のものより物質的モデルになっている。記号表現は一般に記号の物質的(または物理的)形式 (form)として理解されている-それは見る、聞く、触れる、匂いをかぐ、味わうことができる何
かである。ソシュールにとっては、記号表現も記号内容も、ともに純粋に‘心理的’なものであった(Saussure 1983, 12, 14-15, 66; Saussure 1974, 12, 15, 65-66)。両者とも物体というより形式であった。
現在、基本的な‘ソシュール流の’モデルが共通的に採用されているが、ソシュール自身のものより物質的モデルになっている。記号表現は一般に記号の物質的(または物理的)形式 (form)として理解されている-それは見る、聞く、触れる、匂いをかぐ、味わうことができる何
かである。ソシュールにとっては、記号表現も記号内容も、ともに純粋に‘心理的’なものであった(Saussure 1983, 12, 14-15, 66; Saussure 1974, 12, 15, 65-66)。両者とも物体というより形式であった。
- 言語的な記号というのは物と名前の関係でなく、概念と音のパターンの関係である。音のパターンは実は音ではない:音というのは物理的な何かである。音のパターンというのは、聞き手にとっての音の心理的印象であり、感覚の形跡により聞き手に与えられる。音のパターンは感覚的印象の表現の場合のみ、‘物質的’要素と呼ばれる。言語的記号において、音のパターンはこのようにしてそれに連合する他の要素から区別される。この他の要素というのは、一般的にもっと抽象的な種類のものである:概念。(Saussure 1983, 66; Saussure 1974, 66Saussure 1983,66; Sassure 1974,66)
ソシュールは(言葉のような)言語的記号に焦点をあて、‘音声言語中心的に’話し言葉を特に重視した。特に聴覚映像(‘音声 - 映像’または‘音のパターン’)に触れ、書いたものは別の、二次的な、従属したしかし比較しうる記号システムと見ていた(Saussure 1983, 15, 24-25, 117; Saussure 1974, 15, 16, 23-24, 119)。書かれた記号という(‘別の’)システムでは、書かれた文字‘t’のような記号表現は、言語の一次的な記号システムでは音を意味していた(そして、書かれた言葉は概念よりもむしろ音声を意味する)。このようにソシュールにとっては、記号表現が記号内容に関連付けられるのと同じように、書き言葉は話し言葉に関連付けられた。ソシュールのモデルを採用した後継者たちは、話し言葉や書き言葉としての言語的記号の形式に言及することに甘んじている。あとで、ポストソシュール流の記号の‘再物質化’に戻る。
ソシュールのモデルを採用している解説者は、記号内容が間接的に世界の事物に言及しているかもしれないとしばしば言っているにもかかわらず、記号内容を精神的な構築物として扱っている。ソシュールの最初の記号モデルは‘指示物を括弧にいれていた’;つまり、この世界に存在する対象への指示を除外していた。彼の記号内容は指示物として直接に同定されず、心にある概念である-事物でなく事物の観念である。何故、ソシュールの記号モデルでは指示するのは概念であり、事物ではないのだろうと思っている人もいる。哲学者スザンヌ・ランガーの意見が(ソシュールの理論には言及していないが)参考になる。現在の研究者のように、ランガーは言語記号に対して、‘シンボル’という言葉を使っている(ソシュール自身はその言葉を避けた):それは対象の代理ではなく、対象に対する概念の乗り物である...。我々は事物について語るとき、事物そのものではなく事物に関する概念をもっている;シンボルが直接的に意味するのは、事物でなく概念である。概念への行動は、言葉が普通引き起こすことである;これが思考の典型的な過程である。‘もし私が“ナポレオン”と言っても、彼を紹介するようにヨーロッパの征服者に頭をさげる訳ではなく、単に彼のことを思い浮かべるだけである’と彼女は加えている(Langer 1951, 61)(Langer 1951,61)。
このようにソシュールにとって、言語的記号はまったく非物質的であった-それを‘抽象’として見ること嫌っていたが- (Saussure 1983, 15; Saussure 1974, 15)。ソシュール流の記号が非物質的であるということは、多くの一般的な解説書の中で無視される傾向にある特徴である。もし、非物質的という考えが奇妙に思えるなら、言葉はそれ自身の中に価値を持たないことを思い出してみよう-持たないことが言葉の価値である-。ソシュールは、それを貨幣の価値を決定するのは硬貨の材料でないのと同じだと言っている (Saussure 1983, 117; Saussure 1974, 118)。これに対して、いくつかの理由付けがなされている。例えば、言語的記号の物質性が重視されるようになると、それは伝達の透明性を妨げることになる((Langer 1951, 73))。さらに、非物質的であるので言語は特別に経済的な媒体であり、言葉は手近になる。それでも、節操のある論議が記号の物質性の再評価についてなされている。これについては、順を追って見て行く。
ソシュールは記号表現と記号内容という用語の選択が‘互いを分離する区分’を示すのを助けていると言っている (Saussure 1983, 67; Saussure 1974, 67Saussure 1983,67; Saussure 1974, 67)。このことや記号に関する彼の図における水平の柵にもかかわらず、ソシュールは音声と思考(または記号表現と記号内容)とは紙の両面のように切り離せないことを強調している((Saussure 1983, 111; Saussure 1974, 113))。それらは、‘連合の環によって’心の中で‘密接に結び付けられている’-‘各々が他のものを引き起こす’(
ルイス・イェルムスレウは,記号表現と記号内容を指して、‘表現’と‘内容’という用語を用いた (Hjelmslev 1961, 47ff)。記号表現と記号内容は時々、よく知られた二元論‘形式と内容’と等しいと見られる。そのような枠組みの中では、記号表現は記号の形式、記号内容は内容と見られる。しかし、形式を‘容器’と言う隠喩は問題が多い。内容を意味と等しいものとし、意味が理解という能動的な過程 を経ずに‘引き出され’、形式はそれ自体に意味を持たないということになるからである(Chandler 1995 104-6)。
ソシュールは、記号は秩序ある一般化された抽象的システムの一部分としてのみ意味を作ると主張した。彼の意味の概念は、指示的というより純粋に構造的、相対的である:最も優先されるのは、事物よりも関係である(記号の意味は、記号表現に内在する特徴や物質的事物への指示から導かれるというより、他の記号へのシステム的相対関係の中にあると見る)。ソシュールは、記号を‘実在の’または本質的な性質という用語で定義しなかった。ソシュールにとっては、記号は元来、互いを参照するものであった。言語システムでは‘全て関係に依存している’ (Saussure 1983, 121; Saussure 1974, 122)。記号は自分自身の上に意味を作らず、他との関係で意味を作る。記号表現も記号内容も純粋に相対的実体である(Saussure 1983, 118; Saussure 1974, 120)。この考えは、理解が難しいかもしれない。というのは、例えば‘木’のような個々の言葉は、我々にとって意味を持つように感じるからである。しかし、その意味はその言葉と共に使われるほかの言葉との関係において、使用される文脈に依存する。
 (左の図において)個々の記号内での、‘縦方向に’配置された記号表現と記号内容(これは二つの構造的レベルを示唆する)とともに、記号間の関係を強調していることが、事実上、二つの平面 -記号表現と記号表現- がどんなものあるかを決めている。ルイス・イェルムスレウは後にこれらの平面を‘表現’と‘内容’と呼んだ (Hjelmslev 1961, 60)(Hjelmslev 1961, 60)。ソシュール自身は、二つの異なるしかし互いに関連する平面を音声と思考と呼んだ。‘言語は漠然としたかつ無定形な思想の面(A)と同じように特徴の無い音声の面(B)に印された隣接する小部分の繋がりとして考えることができる’(Saussure 1983, 110-111; Saussure 1974, 112)。二つの連続体の記号への任意の分割は、点線により示されている。二つの‘不定形な’かたまりの(平行と言うより)波状の縁は、それらの間には‘自然な’接合など無いことを示唆している。二つの面の間にある割れ目とそれらの間に接合部のないことは、それらの相対的な自律性を強調している。ソシュールは慎重に、‘実在’に直接言及することはしなかったが、Fredric Jameson はソシュールシステムのこの特徴を次のように解釈している。‘現実世界の個々の対象や事象を“表したり”“反映したり”する個々の言葉や文章には重きを置かず、記号の全体システム、ラングの全体が実在そのものと平行にあるというのがソシュールシステムの特徴である;言い換えれば、それは実在世界に存在するどんな組織化された構造にも相似なシステム的言語の全体であり、また我々の理解は1対1基準で進むというより、一つの統一体またはゲシュタルトからその他へ進んでいくという特徴をもつ’( (Jameson 1972, 32-33))。
(左の図において)個々の記号内での、‘縦方向に’配置された記号表現と記号内容(これは二つの構造的レベルを示唆する)とともに、記号間の関係を強調していることが、事実上、二つの平面 -記号表現と記号表現- がどんなものあるかを決めている。ルイス・イェルムスレウは後にこれらの平面を‘表現’と‘内容’と呼んだ (Hjelmslev 1961, 60)(Hjelmslev 1961, 60)。ソシュール自身は、二つの異なるしかし互いに関連する平面を音声と思考と呼んだ。‘言語は漠然としたかつ無定形な思想の面(A)と同じように特徴の無い音声の面(B)に印された隣接する小部分の繋がりとして考えることができる’(Saussure 1983, 110-111; Saussure 1974, 112)。二つの連続体の記号への任意の分割は、点線により示されている。二つの‘不定形な’かたまりの(平行と言うより)波状の縁は、それらの間には‘自然な’接合など無いことを示唆している。二つの面の間にある割れ目とそれらの間に接合部のないことは、それらの相対的な自律性を強調している。ソシュールは慎重に、‘実在’に直接言及することはしなかったが、Fredric Jameson はソシュールシステムのこの特徴を次のように解釈している。‘現実世界の個々の対象や事象を“表したり”“反映したり”する個々の言葉や文章には重きを置かず、記号の全体システム、ラングの全体が実在そのものと平行にあるというのがソシュールシステムの特徴である;言い換えれば、それは実在世界に存在するどんな組織化された構造にも相似なシステム的言語の全体であり、また我々の理解は1対1基準で進むというより、一つの統一体またはゲシュタルトからその他へ進んでいくという特徴をもつ’( (Jameson 1972, 32-33))。
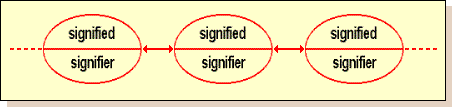
ソシュールは、記号の‘価値’というものはシステム内の他の記号との関係に依存し、記号はこの文脈から独立した‘絶対的な’価値は有していないとした (Saussure 1983, 80; Saussure 1974, 80)。ソシュールはチェスのゲームとの相似性を使い、駒の価値は盤上の位置によって決まると述べた (Saussure 1983, 88; Saussure 1974, 88)。記号は、部分の総和以上のものである。意味作用 -意味されること- は、記号の二つの部分の関係に依存するのに対して、記号の価値は、その記号とシステム全体内の他の記号との関係で決まる(Saussure 1983, 112-113; Saussure 1974, 114)。
- 価値に関する考えは...、記号をある音声と概念との組み合わせ以上の何者でもないと捉えることが大きな誤りであることを教えてくれる。記号をそれ以上のものでないと考えると、それを所属するシステムから孤立させてしまう。従来、個別の記号から出発して、システムはそれらを一緒にして組み立てていくと考えられてきた。それとは対照的に、全体としてのシステムから出発することにより、分析の過程を通して、その構成因子を同定していくことが可能となる(Saussure 1983, 112; Saussure 1974, 113)。
意味作用と価値の区別の例として、ソシュールは以下を挙げている。‘フランス語の mouton は英語の sheep と同じ意味を持っている:しかし、その価値は同じではない。これにはいろいろな理由があるが、とくに食肉としてのこの動物の肉に対する英語の単語は sheep でなく mutton であることが挙げられる。sheep と mouton の価値の相違は、英語では食肉に対して mutton という別の言葉があり、フランス語の mouton は両方カバーするという事実によって定まる’(Saussure 1983, 114; Saussure 1974, 115-116)。
ソシュールの意味の相対的概念は、特に差異的である:彼は記号間の差異を強調した。彼にとって、言語は作用に関する差異と対立のシステムである。‘言語においては、全ての他の記号学的システムと同様、記号を区別するものがそれを構成するものである’(Saussure 1983, 119; Saussure 1974, 121)。John Sturrock が指摘したように、‘一つの言葉の言語はあり得ない。というのは、その単一の言葉は全てのものに適用でき、なにものも区別できないからである:その言葉に定義を与えるためには、少なくとも、もう一つ他の言葉が必要である’ (Sturrock 1979, 10)。広告はこの考え方の良い例である。製品を‘位置付ける’ために重要なことは、広告の記号表現とその製品との関係ではなく、それと関係している他の記号との差別化である。記号が同一である(identity)ということは相対的にしか決まらないというソシュールの概念こそ、構造主義理論の中心部である。構造分析は、歴史の特定の時点における意味システムにおいて作用する構造関係に焦点をあてる。‘関係は、それらが説明できることのために重要である:意味に満ちた対比、そして許容されまたは禁じられた結合’ (Culler 1975, 14)。
ソシュールは、複数の記号の間に見られる負の対立する差異を特に強調した。構造主義分析の際の鍵となる関係は、(自然/文化、生/死のような)2項対立である。ソシュールは次のように主張している。‘概念...は、その内容に関する言葉を使って積極的に定義されるのではなく、同じシステムのほかの項目との比較により否定的に定義される。それぞれの言葉をもっとも正確に特徴付けるのは、ほかのなにものでもではないことである’(Saussure 1983, 115; Saussure 1974, 117 著者の強調したい参考文献)。この考えは、あなたがつむじ曲がりでもなければ奇異に思えるだろう。しかし、否定的な差異という考えは、同じ言語を使っていない人に‘赤’という言葉を教えることを考えればより明確になるだろう。‘赤’を示すために、赤いものをいろいろなものを見せて、それを教えようとしないだろう。それよりも、いろいろな色の同じような形や材質をもつ対象を用意し、それらのなかから赤のものを抜き出してこれが赤だと教えるだろう。ソシュールは、話し言葉を重視したが書き物についても述べている、‘文字の価値は純粋に否定的で差異的である’-我々ができるようになる必要があることは、それを他の文字から区別することである (Saussure 1983, 118; Saussure 1974, 119-120)。否定的な差異については、ソシュールは次のようにも注意している。記号内容と記号表現をそれぞれ個別に考えると純粋に差異的であり否定的であるが、それらが組み合わされた記号は肯定的な項となる。また次のようにも付け加えている。‘ある記号を肯定的組み合わせとして他の比較した瞬間、差異という項は消え去る..。二つの記号...は、互いに差異的ではなく単に区別されているだけである。それらは単純に、互いに対立しているのである。言語の全体的な機構...は、この種の対立と、それらに含まれる音声的および概念的差異の上に立っている’ (Saussure 1983, 119; Saussure 1974, 120-121)。
記号表現は記号内容を‘表す(standing for)’ものとして扱われるが、ソシュール流の記号学者は、記号表現と記号内容の間には必然的、本質的、直接的または不可避的な関係はないと強調する。ソシュールは、記号の恣意性 (Saussure 1983, 67, 78; Saussure 1974, 67, 78) -もっと明確に言えば、記号表現と記号内容の結びつきの恣意性- を強調した (Saussure 1983, 67; Saussure 1974, 67)。彼は、言語が最も重要な記号システムと見て、言語記号に焦点をあてていた;ソシュールにとって、記号の恣意性は言語の第一原理である (Saussure 1983, 67; Saussure 1974, 67) -恣意性は後に、Charles Hockettによって言語のキーとなる‘設計の特徴’として確認された (Hockett 1958; Hockett 1960; Hockett 1965)。恣意性という特徴は、言語の並外れた融通性を説明するのに役立つ (Lyons 1977, 71)。自然言語という文脈で、記号表現と記号内容の間には -それは音声または言葉の形とそれが指示する概念の間でもあるが- 本質的、根本的、‘透明’、自明または‘自然’な結びつきはないことをソシュールは強調している (Saussure 1983, 67, 68-69, 76, 111, 117; Saussure 1974, 67, 69, 76, 113, 119)。ソシュール自身は恣意性の原理を、言語と外部世界の関係に関連付けるのを避けたが、彼に続く研究者たちはそうしたし、純粋に概念的な‘記号内容’の裏に潜んでいる、現実世界の対象に関してソシュールがほのめかしていることを見つけることができる(Coward & Ellis 1977, 22)。少なくとも、言語では、記号表現の形式は意味するものによって決定されない:‘木’という言葉に関して‘木のような’ものはない。勿論、言語ごとに同じ対象を指示する方法は異なる。ある記号内容に対して、他の記号表現よりも‘本来的に’適している特定の記号表現はない;原則的に、どんな記号表現もあらゆる記号内容を表現できる。ソシュールは次のように考えていた。‘どんな考えであろうとも、任意の一連の音声への関連付けを阻むものはない’(Saussure 1983, 76; Saussure 1974, 76);‘ある特定の考えに対して、特定の連続した音声を選ぶ過程はまったく恣意的である’(Saussure 1983, 111; Saussure 1974, 113)。
言語記号の恣意性というこの原理は新しい概念というわけではない:アリストテレスは‘言語の音声と意味される事物の間には自然の繋がりはない’と述べている(Richards 1932, 32 の中の記述)。プラトンのクラチュロス(Cratylus)の中で、ハーモジェネスがソクラテスに‘事物につける名前は、なんであれ正しい;そしてもしその名前をあきらめ他の名前に変えたなら、後の名前は前のものよりやはり正しい、それはあたかも奴隷の名前を変えるようなものだ;というのは、本質的に特定の事物に所属する名前はないと考えている’ということを認めるように迫った (Harris 1987, 67の中の記述)。‘薔薇は、他の名前で呼んでも甘く匂う’とシェクスピアは言った。言語の恣意性という考えは新しくないが、ソシュールがそれを強調したこと、指示物を(疑わしいものとして)括弧でくくる文脈の中にソシュールの独創的な寄与がある。ソシュールは話し言葉を優先したが、‘書物の中で使われている記号も恣意的である、例えば文字tはそれが示す音声と繋がりはない’と強調した (Saussure 1983, 117; Saussure 1974, 119)。
恣意性の原理は記号自身だけでなく、記号システム全体にも適用できる。言語の原理的な恣意性は、それぞれの言語で、ある記号表現と他の記号表現の区分(例えば‘tree’と‘free’)とある記号内容と他の記号内容の区分(例えば‘tree’と‘bush’)が異なることを見れば明らかである。実在 (reality) は継ぎ目のない連続体であると認識するなら、記号内容は明らかに恣意的である(これが最初は分化されていない思考と音声両者の領域に対するソシュールの見方である):例えば、‘角(かど)' はどこで終わるか?常識は、世界での事物の存在は、それらに単純にラベル付けする(それはソシュールが否定した‘名称目録主義的’考えであり、これについては後で触れる)ことより先行することを示唆している。ソシュールは次のように述べている。‘もし、言葉があらかじめ固定されている概念を表現するという役割をもっているならば、ある言語ともう一つの言語の間でそれらの概念についての等価性を見出すだろうが、事実はそうでない’ (Saussure 1983, 114-115; Saussure 1974, 116)。実在は全ての言語により恣意的な種類に分けられ、各人が持っている概念世界はさまざまに分割される。実在を同じように分類する言語は二つとない。John Passmoreが言っているように‘言語は、違うように区別するので違っているのである’( Sturrock 1986, 17の中の記述)。言語的な分類は、単純にまえもって決められた世界の構造によるものではない。言語に単純に‘反映された’‘本質的な’概念または分類はない。言語は‘実在を構築する’ことに決定的な役割をはたす。
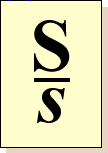 記号表現と記号内容の関係が恣意的であると認めたとしても、直感とは逆に、記号表現が記号内容により決まるのではなく、記号内容は記号表現により決定されるという人がいるかもしれない。まさしく、フランスの心理分析家のジャック・ラカンは、ソシュールの理論を変更し、精神における記号表現の優位性を強調した。彼は、ソシュールの記号モデルを準代数的記号の形に書き換えた。そこでは(記号表現を表す)大文字‘S’が、(記号内容を表す)小文字でイタリック体‘s’の上に来る。両者は水平の‘柵’で分離されている ((Lacan 1977, 149))。これは記号内容が必然的に記号表現の‘下にスリップし’、境界を決めようとする我々の企てに抵抗するというラカンの主張を表している。ラカンは詩的に、ソシュールの音声と思想の面に関する図に次のように言及している。‘創世記の写本からの縮図の上の水と下の水の、波状の線に似せたイメージ;二重の流れは雨の筋の痕跡である'。これは記号表現への記号内容の間断の無い滑り込みを説明していると見ることができる。一方、縦の点線は‘対応する部分’としてではなく、係留点として見なすべきだと主張している(points de caption -文字通り、覆いの布を家具に留めるボタン)。しかし、ラカンはこうも言っている。ソシュールのモデルは余りに直線的すぎる、というのは‘その単位のそれぞれの区切りに貼り付いているように、その点からあたかも‘垂直に’に吊り下げられている関連した文脈の全体の分節を持たない意味する環がないからである’((同上, 154))。ソシュールのモデルに関するラカン流の批判という点では、ラカンの後継者は記号表現と記号内容の仮の結びつきを強調している。また‘記号表現の連鎖’の‘固定化’は社会的に位置付けられていることも強調されている ((Coward & Ellis 1977, 6, 13, 17, 67))。記号表現を記号内容の上に位置付けるラカンの意図は明白であるが、彼の説明上の戦略は多少、奇妙に見えることにも注意しよう。というのは社会のモデル化において、オーソドックスなマルクス主義者は‘[技術 - 経済]に基づく’基本的な駆動力を(論理的に)‘[イデオロギー的な]超構造’の下位にあるとして説明するからである。
記号表現と記号内容の関係が恣意的であると認めたとしても、直感とは逆に、記号表現が記号内容により決まるのではなく、記号内容は記号表現により決定されるという人がいるかもしれない。まさしく、フランスの心理分析家のジャック・ラカンは、ソシュールの理論を変更し、精神における記号表現の優位性を強調した。彼は、ソシュールの記号モデルを準代数的記号の形に書き換えた。そこでは(記号表現を表す)大文字‘S’が、(記号内容を表す)小文字でイタリック体‘s’の上に来る。両者は水平の‘柵’で分離されている ((Lacan 1977, 149))。これは記号内容が必然的に記号表現の‘下にスリップし’、境界を決めようとする我々の企てに抵抗するというラカンの主張を表している。ラカンは詩的に、ソシュールの音声と思想の面に関する図に次のように言及している。‘創世記の写本からの縮図の上の水と下の水の、波状の線に似せたイメージ;二重の流れは雨の筋の痕跡である'。これは記号表現への記号内容の間断の無い滑り込みを説明していると見ることができる。一方、縦の点線は‘対応する部分’としてではなく、係留点として見なすべきだと主張している(points de caption -文字通り、覆いの布を家具に留めるボタン)。しかし、ラカンはこうも言っている。ソシュールのモデルは余りに直線的すぎる、というのは‘その単位のそれぞれの区切りに貼り付いているように、その点からあたかも‘垂直に’に吊り下げられている関連した文脈の全体の分節を持たない意味する環がないからである’((同上, 154))。ソシュールのモデルに関するラカン流の批判という点では、ラカンの後継者は記号表現と記号内容の仮の結びつきを強調している。また‘記号表現の連鎖’の‘固定化’は社会的に位置付けられていることも強調されている ((Coward & Ellis 1977, 6, 13, 17, 67))。記号表現を記号内容の上に位置付けるラカンの意図は明白であるが、彼の説明上の戦略は多少、奇妙に見えることにも注意しよう。というのは社会のモデル化において、オーソドックスなマルクス主義者は‘[技術 - 経済]に基づく’基本的な駆動力を(論理的に)‘[イデオロギー的な]超構造’の下位にあるとして説明するからである。
記号の恣意性は、実在に対して言語の自立性を提案した点で急進的な概念である。記号システムの内部構造に重点を置いたソシュールのモデルは、言語は実在を反映するものでなく、実在を構築するものであるという考えを支援していると見ることができる。我々は言語を次のように使用できる。‘言語は、世界に存在するものと同じように、存在しないものを言明できる。我々は、言語がなんであれその言語を通して、その只中に生れた世界を知るようになるので、実在が言語を決定するのではなく言語が実在を決定する、と主張するのは正当である’((Sturrock 1986, 79))。これに対して、オグデンとリチャーズは、彼らの本意味の意味で、ソシュールは‘記号が表現する事物をまったく無視している’と批判している ((Ogden & Richards 1923, 8))。また、その後の批判では、ソシュールのモデルは社会的文脈から遊離していると嘆いているものもある( (Gardiner 1992, 11))。Robert Sam は‘指示物を括弧に入れる’ことにより、ソシュール流のモデルは‘テクストを歴史から切り離している’と主張している (Stan 2000,122)。言語と‘実在’の関係に関しては、‘様相と表現’のところでまた議論する。
記号が恣意的であるという見方は、記号の解釈の広がり(と文脈の重要性)を説明するのに役立つ。記号表現と記号内容の間には、1対1の対応関係はない;記号は単一の意味でなく、むしろ多義的な意味を持つ。単一の言語でも、一つの記号表現は複数の記号内容を指示し(例えば、語呂合わせ)、一つの記号内容は多くの記号表現を指示される(例えば、同義語)。しかし研究者の中には、記号表現の記号内容への関係が、言語でさえ、常にまったく恣意的であるということに批判的な人もいる (例えば、Lewis 1991, 29)。擬声語についてはこの文脈で言及されることが多いが、記号学者は同じ音声に対しても、恣意性を無視すると、言語が異なれば言葉も異なるということを説明できないと反論している(特に身近な動物の鳴き声に関して)(Saussure 1983, 69; Saussure 1974, 69Saussure 1983,69; Saussure 1974,69) 。
‘言語システム全体が、記号は恣意的であるという不合理な原理の上に構築されている’とソシュールは言っている。この挑発的な宣言の後すぐに次のようなことも認めている。‘制約なしにこれを適用すれば、この原理はまったくのカオスへ導くことになるだろう’(Saussure 1983, 131; Saussure 1974, 133)。もし、言語的記号が全ての点でまったく恣意的であれば、言語はシステムでなくなり、そのコミュニケーション機能は破壊されるだろう。彼は譲歩して‘まったく有契的でない、言語は存在しない’とも言っている (同上)。ソシュールは、‘システムはある合理性を持っているため、言語は完全に恣意的とは言えない’と認めている(Saussure 1983, 73; Saussure 1974, 73)。恣意性の原理は、言葉の形は偶然やでたらめである、ということを勿論意味しない。記号は言語の外では(extralinguistically)決定されず、言語内の(intralinguistic)決定に従う。例えば、記号表現は、対象としている言語に存在するパターンに順応した良く組織された音声の組み合わせを形成しなければならない。その上、‘screwdriver’のような複合名詞はすべて恣意的というわけではなく、二つの記号の意味のある組み合わせとして認識できる。ソシュールは恣意性の程度(degree)を以下のように区別している。
- 言語記号の恣意性という基本的な原理は本質的に恣意的な言葉-つまり有契的でないもの-と相対的に恣意的なものの区別を阻んではいない。全ての記号が必ずしも絶対的に恣意的というわけではない。あるケースでは、恣意性のいろいろな度合いを認識させる要因がある。しかし、恣意性の考えをまったく棄却するものではない。記号は、ある程度まで有契的なものかもしれない (Saussure 1983, 130; Saussure 1974, 131;これは最初に出てくる個所であり、それに続く頁も参照のこと)。
ここで、ソシュールは彼の立場を少し変更し、記号は‘相対的に恣意的’と言っている。それに続いて、記号表現と記号内容の関係を(アルチュセールのマルクス主義的術語をまねて)‘相対的な自律’という言葉で説明する理論家もいる (Tagg 1988, 167; Lechte 1994, 150)。以下では、記号表現と記号内容の関係に関する相対的な慣習性という点に戻る。
記号表現と記号内容の関係は、存在論的には (ontorogically) 恣意的であるが(哲学的には、黒いものを白と呼んでもまたその逆でも、‘事物の条理’としてはこの存在の状態は変わらない)、意味システムが社会的、歴史的に恣意的であることを示唆しているのではないことに注意する必要がある。自然言語は、モールス信号のような歴史的発明と異なり、恣意的に確立したのではない。また、記号の恣意的性質は、記号を社会的に‘中立’にするのでなければ、物質的に‘透明’にするのでもない-例えば、西欧文化では‘白’は特権的な記号表現である ( (Dyer 1997))。交通信号の‘恣意的な’色でさえ、‘止まれ’に赤が最初に選択されたのも完全には恣意的でない。それまでに、明らかに赤は危険と関連付けられていた。C・レヴィ=ストロースが示したように、先験的(a priori)には恣意的であるが、後験的(a posteriori)には恣意的ではなくなっていく -記号が歴史的存在になると、それは恣意的に変更できなくなる (Levi-Strauss 1972,91)。コード(その用語はポスト・ソシュール主義の記号学者の間では基本的なものとなっている)に従って、社会的に記号を使用することにより、全ての記号は歴史と同時に、記号の使用者が属する文化の成員が熟知している記号の共示を獲得する。記号表現は‘自由に選択されるように見える’が、言語共同体という観点からはそれは‘自由に選択されるというより強制された’ものであるとソシュールは注意している。というのは、‘言語は常に過去からの継承であり’、使用者は‘選択の余地はなく受け入れざるを得ない’からである (Saussure 1983, 71-72; Saussure 1974, 71)。まさに、‘言語的記号がただ慣習にのみ従うのは記号が恣意的であるためであり、記号が恣意的でありえるのは、慣習の上に構築されているからである’ (Saussure 1983, 74; Saussure 1974, 74)。恣意性の原理は、勿論、個人が与えられた記号内容に対して記号表現を勝手に選択できるということを意味しない。記号内容と記号表現の関係は個人的選択の事柄ではない;もしそうなら、コミュニケーションが不可能になってしまう。‘記号がいったん、その言語共同体で確立してしまったら、個人にはどんな観点からもそれを変える力はない’ (Saussure 1983, 68; Saussure 1974, 69)。個々の言語使用者にとっては、言語は‘与えられている’ものである -我々は自分自身のシステムは創造しない。ソシュールは、言語システムは人がその中へ生れてくる、交渉の余地のない‘契約’であると言っている (Saussure 1983, 68; Saussure 1974, 69) - ただ、後でその用語を問題視してもいる (同上,71)。我々は、言語システムは‘自然’なものとして受容するように学習するので、その中に含まれる存在論的恣意性は見えないものとなる。
 ソシュールの記号の恣意性という遺産は、記号表現と記号内容の関係は慣習的であること -つまり社会的、文化的慣習に依存するということ- を、記号学者に強調させることになる。これは、ソシュールが検討対象とした言語記号の場合、明確である:言葉というものが我々に対して何を行うかを意味するのは、我々が共同してそれにそうさせることに同意しているが故である。ソシュールは、記号論の主な検討対象は‘記号の恣意性に基づいたシステムの全体グループ’であるべきだと感じていた。彼は次のように主張している。‘まったく恣意的である記号は、理想的な記号過程を他のものより良く備えている。これが、人間の言語に見られる、もっとも複雑でかつもっとも汎用的な表現システムが全ての特徴を示している理由である。この意味で、言語は記号学システムの一つのタイプの例に過ぎないが、それでも言語は記号学全体のモデルとなる’ (Saussure 1983, 68; Saussure 1974, 68)。彼が記号システムの例として提示したのは、話し言葉と著述物であり、以下は挙げただけである:聾唖者用の手話用アルファベット;社会的慣習;礼儀;宗教的また他の象徴的儀式;法的手続き;軍事用信号と手旗信号 (Saussure 1983, 15, 17, 68, 74; Saussure 1974, 16, 17, 68, 73)。ソシュールはつぎのようにも付け加えている。‘社会に容認されている表現のどの手段も、原則として、共同体としての習慣や慣習の上に置かれており、結局同じものになる’(Saussure 1983, 68; Saussure 1974, 68)。しかし、言葉のような純粋に慣習的な記号はその指示物から独立している一方、記号のあまり慣習的でない形式は指示物からあまり独立していない。それでもやはり、言語記号の恣意的性質は明らかなので、ソシュール流のモデルを用いる人は‘それを使う人にとって自然に見える記号が本質的な意味を持っており説明を要しない、と仮定するという犯しやすい誤り’を避ける傾向にある (Culler 1975, 5)。
ソシュールの記号の恣意性という遺産は、記号表現と記号内容の関係は慣習的であること -つまり社会的、文化的慣習に依存するということ- を、記号学者に強調させることになる。これは、ソシュールが検討対象とした言語記号の場合、明確である:言葉というものが我々に対して何を行うかを意味するのは、我々が共同してそれにそうさせることに同意しているが故である。ソシュールは、記号論の主な検討対象は‘記号の恣意性に基づいたシステムの全体グループ’であるべきだと感じていた。彼は次のように主張している。‘まったく恣意的である記号は、理想的な記号過程を他のものより良く備えている。これが、人間の言語に見られる、もっとも複雑でかつもっとも汎用的な表現システムが全ての特徴を示している理由である。この意味で、言語は記号学システムの一つのタイプの例に過ぎないが、それでも言語は記号学全体のモデルとなる’ (Saussure 1983, 68; Saussure 1974, 68)。彼が記号システムの例として提示したのは、話し言葉と著述物であり、以下は挙げただけである:聾唖者用の手話用アルファベット;社会的慣習;礼儀;宗教的また他の象徴的儀式;法的手続き;軍事用信号と手旗信号 (Saussure 1983, 15, 17, 68, 74; Saussure 1974, 16, 17, 68, 73)。ソシュールはつぎのようにも付け加えている。‘社会に容認されている表現のどの手段も、原則として、共同体としての習慣や慣習の上に置かれており、結局同じものになる’(Saussure 1983, 68; Saussure 1974, 68)。しかし、言葉のような純粋に慣習的な記号はその指示物から独立している一方、記号のあまり慣習的でない形式は指示物からあまり独立していない。それでもやはり、言語記号の恣意的性質は明らかなので、ソシュール流のモデルを用いる人は‘それを使う人にとって自然に見える記号が本質的な意味を持っており説明を要しない、と仮定するという犯しやすい誤り’を避ける傾向にある (Culler 1975, 5)。
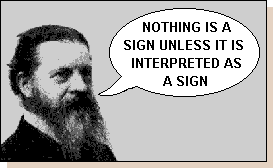 ソシュールが、彼の記号、‘記号学’および‘構造主義的方法論’のモデルを定式化したころ、大西洋の向こうで、実用主義哲学者であり論理学者であるチャールズ・サンダース・パース(Charles Sanders Peirce)が記号、‘記号論’および記号の分類に関する彼独自のモデルの定式化を進めていた。ソシュールの‘自己充足的な2項モデル’に対して、パースは3項モデルを提案した:
ソシュールが、彼の記号、‘記号学’および‘構造主義的方法論’のモデルを定式化したころ、大西洋の向こうで、実用主義哲学者であり論理学者であるチャールズ・サンダース・パース(Charles Sanders Peirce)が記号、‘記号論’および記号の分類に関する彼独自のモデルの定式化を進めていた。ソシュールの‘自己充足的な2項モデル’に対して、パースは3項モデルを提案した:
‘記号は...、[代表項の形で]ある観点またはある資格で誰かにとって何かを表すものである。それは誰かに語りかける、つまり人の心に同等の記号かまたはもっと展開された記号を生み出す。それが作り出す記号を、最初の記号の解釈項と私は呼ぶ。それはなにかを、つまりその対象を表す。それは対象を全ての局面ではなく、‘代表項のグラウンドと呼ぶ一種の観念に関連させて表現する’((Peirce 1931-58, 2.228))。代表項、対象と解釈項の間の相互作用は‘記号過程’と呼ばれている ((同上, 5.484))。パースの記号モデルでは、‘止まれ’の交通信号は次のように構成される:交差点の赤信号(代表項);止まっている自動車(対象)そして赤信号は自動車が止まらなければならないことを指示しているという観念(解釈項)。
パースの記号モデルは、対象または指示物を含んでいる ―それは勿論ソシュールのモデルには直接現れてこない。代表項はソシュールの記号表現に、また解釈項は、意味としては記号内容に似ている (A href="http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem13.html#Silverman_1983">(Silverman 1983, 15))。しかし、解釈項は記号内容とは異なる性質を持っている:それ自身、解釈者の心の中での記号である。パースは次のように記している。‘記号...は誰かに語りかける、つまりその人の心に同等または多分もっと展開された記号を生成する。それが生みだす記号を最初の記号の解釈項とよぶ’((Peirce 1931-58, 2.228))。ウンベルト・エーコは、これが(パースが良く知っていたように)解釈項の限りない(ad infinitum)連鎖に(潜在的には)結びつくことから、‘無限の記号過程’と名付けた (同上, 1.339, 2.303)。他のところで、パースは‘表象の意味は、表象しかあり得ない’と付け加えている (同上, 1.339)。最初の解釈は全て、再解釈されうる。記号内容自体が、記号表現の役割をはたすということは、辞書を使っていて、ある言葉の定義の中で使われている言葉を調べているうちに最初の言葉から離れてしまうという経験を持っている人にとっては分かり易いだろう。この概念は、記号の価値は他の記号との関連で決まるというソシュールの主張を超えるものと見ることができる。その後、ポスト構造主義者によって、それは急進的に展開された。パースのモデルに関連して、ソシュールのモデルからは明らかに排除され、一方、後の理論家により言及されたもう一つの概念は、双方向的思想という考えである。これは部分的にはパースが過程として‘記号過程’を強調したことから生じたものであり、ソシュールが共時的な構造を重視したのと対照をなしている (Peirce 1931-58, 5.484, 5.488)。‘全ての思考は問答体の形式である。ある事例に関する君の認識は、自己の同意を得るためもっと深い認識に訴える ’とパースは主張した (Peirce 1931-58, 6.338)。この考えはミハエル・バフチンの理論の中で、もっと発展した形で1920年代に再浮上する (Bakhtin 1981)。これの一つの重要な観点は、基本的には社会的なこととして、心理的な反射作用の特徴を記述した点である。
パースは三つ組みの構造に魅力を感じて、記号それ自身[または代表項]、その対象、解釈項をそれぞれ‘第一次性’、‘第二次性’、‘第三次性’の実体という現象学的な区別を行った。このような耳慣れない用語もパースの造語の中では比較的おとなしい例であり、彼の複雑な用語と文体は、パース独自の記号論の影響力を制限している。
パースの3項関係の変異体はよく‘記号論的三角形’として表現されている(あたかも、一つのバージョンしかないように)。ここに、よく出会うバージョンがあるが、これは馴染みのないパースの用語を単に書き換えただけのものである(Noth 1990, 89):
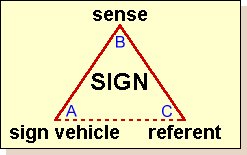
比較的良く知られた記号論的三角形はオグデンとリチャーズのもので、そこでは (a)‘象徴 (symbol)’、(b)‘思考または指示 (thought or reference)’、(c)‘指示物(referent)’という用語が使われている ((Ogden & Richards 1923, 14)。三角形の底辺が破線なのは記号負荷体と指示物の間に必ずしも観測可能なまたは直接的な関係がないことを示している。ソシュールの抽象的な記号内容(それは用語C よりもむしろ用語Bに機能が似ている)とは異なり、指示物は対象である。これは、必ずしも、記号の指示に物理的な事物とともに抽象的概念や虚構の実体をも含めることにならず、パースのモデルは客観的実在に対する位置を与えたのである。これは、ソシュールのモデルが直接的には触れなかった点である(パースは素朴な実在論者でなく、経験は記号によって伝達されるとも主張している)。しかし、パースが‘表現された事物の存在の様態が、それの表現の様態に依存するということは...実在の本質に反する’と強調していることに注意して下さい (Peirce 1931-58, 5.323)。パースのモデルに指示物を含めることは、自動的にそのモデルをソシュールのモデルより優れたものにすることではない。まさに、John Lyons はこう記している:
- 三つの要素 A,B,C をすべて考慮に入れなければならないことを認める人々の間でさえ、3項関係分析の詳細については大きな意見の相違がある。A は物理的実体としてまたは心理的実体として決定されるべきなのか? B の心理学的または存在論的資格はなにか? C は特定の出来事を指示するものなのか?または、それは記号を使用することにより指示される事物の全体なのか?または、第3の可能性として、このクラスの典型的または理想的な標本なのか? ((Lyons 1977, 99))
意味の作成が重要という考えは(これは、パースが彼の3項関係で触れていなかった解釈者を必要とする)、コミュニケーションやメディア研究家に特に訴えるところがある。というのは、彼らは理解の能動的な過程を強調しまた‘内容’と意味が同じという考えを否定するからである。これらの研究者の多くは、記号論的三角形に言及するとき、(‘意味’や‘解釈項’の代わりに)記号の解釈者(または‘使用者’)を明示する。これは、記号過程というプロセスに焦点をあてることになる(これはパースの概念そのものである)。記号の意味は、それ自身に含まれるのではなく解釈の中で生じてくる。2項モデルまたは3項モデルが用いられようが、解釈者の役割は -記号の形式モデルの中か記号過程の根本的な部分として- 考慮されなければならない。David Sless は‘使用者、記号または指示物に関する検討は、それぞれ他の項目と切り離して行うことはできない。ある一つの項に関してなにか言うことは、ほかの2項を意味的に包含する’と言明している (Sless 1986, 6)。Paul Thibault は、解釈者はソシュールの2項モデルの中にも暗に現れていると言っている(Thibault 1997, 184)。
記号学者が、記号と‘記号負荷体’(ソシュール流では‘記号表現’、パース流にいえば‘代表項’が対応する)を区別していることに,注意する必要がある。記号は記号負荷体以上のものである。‘記号’という用語はずさんに使われており、この区別がいつも守られているわけでない。ソシュールの枠組みでは‘記号’に関する言及は記号表現に関してのものとされるべきであり、同様にパース自身は厳密さが必要なときは代表項と言っていた。そのような混同は、記号がとる形式の‘向こう側’を見てしまう傾向があることによるものだと考えられる。しかし、もう一度繰り返しておきたい:記号表現や代表項は、(言葉の話された形式や書かれた形式のように)記号が顕現する形式であり、一方、記号は意味に富む総体である。
ソシュールは(言語的)記号の恣意性を強調したが、大部分の記号学者が、記号は恣意的/慣習的(またはそれとは対照的に‘透明性')の程度によって異なってくることを強調している。象徴は、記号表現と記号内容関係の一つの形式を反映しているにすぎない。ソシュールは記号の類型学は提案しなかったが、チャールズ・パースは脅迫観念的な分類学者であり、いくつかの論理学的な分類学を提案した (Peirce 1931-58, 1.291, 2.243)。彼の記号群の分割と細分割は、並外れて精緻である:まさに、記号の59,049種類へも及ぶ型への理論的写像を提案した。パース自身、この計算は‘クラスの個数を人の頭に簡単に入れるには、大きすぎるものとした'と皮肉っぽく述べている。そして、‘我々は、もっと細分化するのはそれが受け入れられようになるまで延期した方が良いだろう’と付け加えている (Peirce 1931-58, 1.291)。しかし、彼の最も穏健な提案さえ、気力をくじくものである:スザンヌ・ランガーは‘59,049種類の型は、本当はたった64に要約できるという彼の保証は慰めにもならない’と論評している (Langer 1951, 56) 。不幸にも、そのような類型学の複雑さは、それらを実用的なモデルとしては余り役立たないものにしている(Sturrock 1986, 17)。しかし(1867年に概要が示された)パースの基本的な分類の一つは、後の記号論の研究で広く参照されている (Peirce 1931-58, 1.564)。彼は、それを記号の‘最も基礎的な’区分と認めている(同上, 2.275)。それは‘記号の型’の分類よりも、むしろ‘記号媒体と指示物の関係の態様’を分類するのに役立つ (Hawkes 1977, 129)。パースは‘記号’(sic) と対象との関係も検討の中に入れていたが、著者は、今後の説明の中では、これまで通りソシュールの用語である記号表現と記号内容を用いる。というのは、パース流の区分は広い意味でのソシュール流の枠組みの中で共通的に採用されているためである。そのような統合は、ソシュールモデルの記号内容における指示能力を強調する(しかし間接的に)ことになる。以下に、三つの態様の、著者自身による簡単な定義と説明例を示す。

![]()

ここでの三つの形式は、慣習の度合いが減少するような順序で並べてある。言語のような象徴記号は(少なくとも)高度に慣習的である;類像記号は常に、ある程度、慣習を含んでいる;指標記号は‘強制的に’注意を対象に向ける (Peirce 1931-58, 2.306)。指標記号と類像記号の記号表現は、指示された記号内容により制約されていると見ることができ、もっと慣習的な象徴記号では、記号内容はかなりの範囲まで記号表現により決定されてしまうと見ることができる。それぞれの形式のうちでも、慣習の度合いは変わってくる。他の判定基準も、三つの形式を別の方法でランク付けするのに適用できるかもしれない。例えば、Hodge と Kress は、指標性は判断や推論作用に基づいており、類像性は類像記号という最も高度な‘様相’を作る‘直接的な認識’に近いことを示唆している。‘有契性’(ソシュールから)と‘制約’という用語は、記号内容が記号表現を決定する範囲を記述するために使われることに注意しよう。記号表現が記号内容に制約されるほど、記号はより‘有契的’になる:類像記号は高度に有契的である;象徴記号は有契的でない。記号の有契性が低いほど、共用されている慣習の学習が必要とされる。それでも大部分の記号学者は、記号に関連した慣習の役割を強調する。後で見るように、写真や映画でさえ‘読む’ことを習得しなければならない慣習を前提として作られている。そのような慣習が、重要な社会的な記号の次元である。
パースとソシュールは、‘象徴’という用語をそれぞれ異なって用いている。今日、大部分の研究者は、言語を象徴的な記号システムと捉えているが、ソシュールは言語記号を‘象徴記号’と言うのを避けていた。象徴記号という言葉を普通に使った場合、それは(裁判を意味する)天秤のような例が挙げられる。それに対して、ソシュールはそのような記号は‘全面的に恣意的というわけではないし、空の形式でもない’と主張した。それらは、彼が後に‘合理的’と呼んだ結びつき、つまり記号表現と記号内容の間に‘少なくとも、自然な接続の名残を示している’(Saussure 1983, 68, 73; Saussure 1974, 68, 73))。ソシュールは言語記号の恣意性に焦点をあてたが、恣意的な象徴記号のもっとはっきりした例は数学である。数学は、外部世界に言及する必要はまったくない:その記号内容は明白に概念であり、数学は関係のシステムである(Langer 1951, 28)。
パースは、象徴記号を次のように捉えていた。‘法則、通常は観念の連合によって表す対象を示す記号であり、法則は、象徴記号がその対象を指示するものとして理解させるように動作する’ (Peirce 1931-58, 2.249)。我々は、象徴記号を‘規則’または‘習慣的な連想’によって理解する( (同上, 2.292, 2.297, 1.369))。‘象徴記号は、その象徴記号を使用する動物の観念によりその対象と接続され、それなしではそのような接続は存在しない’((同上, 2.299))。‘記号が構成されるのは、単にまたは主にそれがそのように使用されまた理解されるという事実による’((同上, 2.307))。象徴記号は‘解釈項がなければそれを記号として成立させる特性を失うであろう’(((同上,2.304)。象徴記号は‘慣習的な記号かまたは(獲得または生まれつきの)習慣に依存する記号である’(同上,2.297)。‘すべての言葉、文、本および他の慣習的な言葉は象徴記号である’(同上,2.292)。パースは、言語記号をソシュールと同じように慣習性という用語で特徴付けた。彼は、(‘トークン’と呼んだ)個々の象徴記号の恣意性についてはめったに触れなかったが、それらは、‘殆ど慣習的であるか恣意的である’と述べている(同上3.360)。象徴記号は次のような特徴を持っている。‘それが表現するものを表す特定の意味作用または妥当性はなにものの中にもなく、それがそのように理解される習慣、性癖、または他の実効的な規則があるという事実そのものの中にある。例えば、“man”という言葉を取り上げよう。この3文字は人間に似ていない;また人間が連想される音声でもない’(同上,4.447)。彼は、他でも次のように加えている。‘象徴記号は‥‥、その対象との相似性や共通性がなくてもまた実際の関連がなくてもその機能を満たす’、その機能を満たすのはもっぱら記号として理解されることにある (同上,5.73;初期の強調)。
次は類像記号(icon)に移る。パースは、類像的記号は対象を‘主に相似性’によって表現すると宣言している(Peirce 1931-58, 2.276)。記号は、‘そのものに似ており、その記号として使用される限りにおいて類像記号である’(同上, 2.247)。まさに、彼が始めて‘類似’という様態に名前を付けた(例えば,(同上,1.558)。彼は‘全ての絵画(習慣的な分類法であるが)’は類像記号であると付け加えた(同上, 2.279)。類像記号は、それが表現する対象が持つ性質と似た性質を持ち、‘心の中に同じような感覚を生起する’((同上,2.299,3.362も参照のこと)。指標記号と異なり、‘類像記号はそれが代表する対象と動的接続を持たない’(同上)。単に、記号表現が、それが描くものに似ているからといって、それは必ずしも純粋に類像的なものにならない。哲学者スザンヌ・ランガーは‘絵画はそれが表現するものの複製でなく、象徴記号である’と主張している(Langer 1951, 67)。絵画はそれが表現するものに、ある観点でのみ似ているのである。我々が画像の中で見出しがちなのは、部分の全体に対する関係と似た関係である(同上, 67-70)(,67-70)。パースにとっては、‘あらゆる図表は、それと対象が似ていなくとも、それぞれ部分の間の関係に相似性があれば、全ての図表’は類像記号に含まれる(Peirce 1931-58, 2.279)。‘多くの図表は見かけ上、まったく似ていない;それらが似ているのは部分の間の関係に関してだけである’(同上, 2.282)。最も‘現実的な’画像さえ、描かれたものの複製でもなくまして写しでもない。しかし、我々は、それが何を表しているのか、その表現を誤って解釈することはない。
記号学者は一般に、‘純粋な’類像記号はなく、文化的慣習の要素が含まれているという立場を採る。パースは、‘(絵画のような)物質的な画像’は、それが表現しているものに似ている外観をしていると認識されるかもしれないが、‘表現の様態という点では大いに慣習的である’と述べている (Peirce 1931-58, 2.276)。‘会ったことのない人でも、その肖像画は説得力があると言う。その中で見たことに基づいて、その中で表現されている人についての観念を形づくる。その限りでは、それは類像記号である。しかし、実際にはそれは純粋な類像記号ではない。というのは、それは画家を通した、元の外見から生じた作用(effect)だと知ることによって、大きく影響されるからである...。一方、肖像画は、ある慣習的な観点以外ではまた慣習的な価値判断の後では、元の人にわずかしか似ていないことを知る’ (同上, 2.92) 。
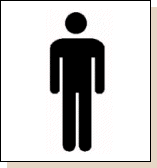 Guy Cookは、男性用公衆トイレのドアの類像記号は、本当に女性より男性に似ているのだろうかと疑問を呈している。‘記号が真に類像的であるためには、前にそれを見たことのない人にとっても明瞭なものでなければならない - そしてこれは考えられているほどありそうにないように思われる。類似点を見るのは、既に意味を知っている場合である’(Cook 1992, 70)。このように、‘写実的な’イメージでさえ、類像的であり象徴的である。
Guy Cookは、男性用公衆トイレのドアの類像記号は、本当に女性より男性に似ているのだろうかと疑問を呈している。‘記号が真に類像的であるためには、前にそれを見たことのない人にとっても明瞭なものでなければならない - そしてこれは考えられているほどありそうにないように思われる。類似点を見るのは、既に意味を知っている場合である’(Cook 1992, 70)。このように、‘写実的な’イメージでさえ、類像的であり象徴的である。
類像的および指標的記号は、記号表現と記号内容を接続させることが習慣になると、象徴記号よりも‘自然’なものとして読まれる傾向にある。類像記号の記号表現は、何かを思い起こさせるのに非常に効果的である。Kent Graysonは次のように見ている:‘我々は類像記号の内に対象を見ることができるので、指標記号や象徴記号をみているより、真実にちかいところ連れて行ってくれるという感覚を残しやすい’(Grayson 1998, 36)。彼は次のようにも付け加えている。‘我々の注意を表象に常に存在する裂け目に引き付ける代わりに、類像的経験は無意識的にこの裂け目を埋めさせ、表象には裂け目などないと信じさせようとする...。これは表象のパラドックスである:それが最も良く作用していると考えるとき、人を欺く’(同上, 41)。言語学者のJohn Lyonsは、類像性は‘常に、そこで形式が決定される媒体の性質に依存する’と記している (Lyons 1977, 105)。彼は、英語の擬声語カッコウ(cuckoo)を例として挙げ、それは音声媒体(話し言葉)でのみ類像的であり、図形的媒体(書き言葉)ではそうでないと言っている。音響媒体は特徴的な音を表現でき(しかし、比較的慣習化された方法で)、図形的媒体は特徴的な形状を表現できる(エジプトの象形文字のように) (Lyons 1977, 103)。記号の物質性の重要性については、もう少し後で検討する。
指標性は多分、最も親しみにくい概念である。パースは、なにが指標記号を構成するかについての種々の規準を提案している。指標記号は、何かを‘指す’:例えば、‘日時計または時計は一日の時刻を指す(indicate)’(Peirce 1931-58, 2.285)。彼は‘記号’と、‘理解する心’に純粋には依存しない対象との間の‘純正な関係’について言及している(同上, 2.92, 298)。対象は‘必ず存在する’(同上, 2.310)。指標記号は、その対象と‘当たり前のこととして’接続されている(同上,4.447)。‘真の接続’がある(同上, 5.75)。‘直接的で物理な繋がり’があるかも知れない(ibid., 1.372, 2.281, 2.299)。指標的記号は‘対象から切り離された断片’のようなものである(同上, 2.231)。(対象が虚構であっても良い)類像記号とは異なり、指標記号は‘紛れもなくあれこれの存在物’を表す(ibid., 4.531)。‘指標記号は、必ず実在物との共通の性質を持っている’、一方記号表現は、記号内容により‘真に影響される’;‘実際の修飾’が含まれている(同上, 2.248)。指標記号と対象の関係は、‘ただの相似性’に基づいていない(同上):‘指標記号は...は、その対象への表象の相似性を持っていない’(同上, 2.306)(,2.306)。‘類似や相似性’は指標記号を決めるものではない(同上, 2.305)。‘注意を引くものは全て指標記号である。我々をはっとさせるものは、なんものでも指標記号である’(同上, 2.285; 3.434も参照のこと)。指標的記号は、‘注意を対象へ強制的に向ける’(同上, 2.306; 2.191,2.428も参照のこと)。‘心理学的には、指標記号の作用は近接による連合に依存しており、相似性による連想または知的操作には依存していない’(同上)。
写真は、それが描写するものに似ていると認識されているが、パースは、写真は類像的かつ指標的であると記している:‘写真、とくにインスタント写真はまさに啓発的である。というのは、ある観点からは、それらは表現しているものに正確に似ていることを知っているからである。しかし、この相似性は、写真が物理的に逐一、強制的に自然と対応させられているという環境のもとで作成されていることによるためである。その観点からは、写真は物理的な接続を有している記号クラス[指標的クラス]に属している’(Peirce 1931-58, 2.281; 5.554も参照のこと)。この意味では、写真の像は感光乳剤の上の光の作用の指標であり、全ての未編集の写真や映画の像は指標的である(実際は、構図、ピント合せ、現像など各種の操作から成るが)。当然そのような像は、それが描写するものに‘似ており’、写真や映画の画像の‘真の力’は‘類像的意味作用にある’ことを示唆している(Deacon et al. 1999, 188)。しかし、デジタル画像技術が写真画像の指標性を次第に侵食しているが,解釈者にそれらが‘現実’の‘客観的な’記録と思わせるのは、媒体が持っている指標性であると言うことができる。パースは、‘写真は、対象と光学的に接続されているということが、その外観が現実に対応している証拠である’と認めている(Peirce 1931-58, 4.447)。多くの文脈、特に法律的な文脈では、写真は少なからず‘証拠’として認められている。動画では、ビデオ・カメラは広く‘証拠として’使われている。ドキュメンタリー映画やテレビ・ニュース番組の野外撮影は記号の指標性に依存している。そのような分野では、指標性は証拠としてのその物の状態を保証する。写真や映画の画像は、また象徴的かもしれない:テレビ・ニュースの観察研究で、DavisとWaltonはニュースの主題である人々、場所および出来事の類像的また直接的表現が占める場面は、全場面の中で比較的少ないということを見出した。はるかに多くの部分を占める場面は、内容と間接的にしか関係しないものだった:それらは指標的または象徴的に話題となっていること‘を表現している’(Davis & Walton 1983b, 45)。
記号を、‘記号の型’としてのパースの三つの様式に当てはめがちであるが、それらは互いに排他的でない:記号は、類像記号でも象徴記号でも指標記号またはその組み合わせでもあり得る。パースは、充分それに気付いていた:例えば、彼は次のように主張していた。‘まったく純粋な指標記号を実現することも、指示的性質を全く欠いた記号を見出すことは不可能ではないとしても難しい’ (Peirce 1931-58, 2.306)。地図は、事物の位置を示すという点では指標的であり、目印間の距離と方向を示すという点では類像的であり、その意味を学習しなければならない慣習的なシンボルを用いている点では象徴的である。映画研究者であるPeter Wollenは、次のように論じている。‘記号に関するパースの分析の大きな利点は、記号の異なる局面を互いに排他的と見ていない点である。ソシュールと違って、彼はあることやその他のことをえこひいきする偏見を示さなかった。彼は、記号の三つの局面に基づく論理学と修辞学を望んだのである’(Wollen 1969, 141)。映画とテレビはこの三つの様式をすべて利用している:類像記号(音と映像)、象徴記号(話と文章)、そして指標記号(撮影されたものの作用);最初は類像的記号が支配的なように思える、しかし、例えば、回想場面がそれに続くことを意味する‘溶暗(画面をぼかして次の場面を重ねる)’のように、映画の記号はかなり恣意的である。
Hawksは、ヤコブソンに続いて次のように言っている。記号の三つの様態は、‘必然的にそれらの一つが、他のものに対して優位を保つという階層的形式で共存する’。そして、その優位性は文脈によって決定される(Hawkes 1977, 129)。記号が象徴的であるか、類像的であるか、指標的であるのか、は主に記号が使用される方法に依存する。そのため、教科書で記号の各種の様態を説明するため選ばれた例は、誤った方向に読者を導きやすい。同じ記号表現がある文脈では類像的に使われ、もう一つの文脈では象徴的に使われるかもしれない:ある婦人の写真は、‘女の人’という広い分野を代表するかも知れないし、撮影された特定の女性を表現したものかもしれない。記号は、ある特定の文脈での使用者の目的を考えないと、三つの様態の言葉で分類できない。その結果、記号はある人にとっては象徴的、もう一人の人にとっては類像的、第三の人物にとっては指標的に扱われるかも知れない。Kent Graysonが説明したように、‘我々は類像記号、指標記号または象徴記号について語るとき、記号それ自体の客観的な性質は考えないで、視聴者の記号に関する経験に留意する’(Grayson 1998, 35)。記号は時間とともに、その様態を変化していく。Jonathan Cullerが述べているように‘ある意味ではロールス-ロイスはそれを購入するためにはその人が金持ちでなければならないという意味で、富の指標記号であった、しかし、それが使われるにつれ、富の慣習的記号に変わってしまった’ (Culler 1975, 17)。
ソシュールは、‘通時的’(その進化)よりも‘共時的な’‘言語状態’を研究することに重点を置いた(言語がある時点で固定されたようにみなす)にも拘らず、彼は、言語における記号表現と記号内容の関係は時間とともに変わることに気付いていた(Saussure 1983, 74ff; Saussure 1974, 74ff)。しかし、それは彼の関心の中心ではなかった。構造主義的手法への批判は、記号表現と記号内容の関係は、動的に変化するということである:Rosalind CowardとJohn Ellisは‘記号表現の連鎖’が‘固定される’のは一時的なことであり、また社会的に決定されるものであると主張している((Coward & Ellis 1977, 6, 8, 13))。
パースの三つの様態では、一つの様態から他の様態への歴史的転移が生じる傾向にある。パースは、ソシュールよりはるかに非言語的記号を許容していたが、ソシュールと同じく、象徴的記号を重要視していた:‘それらが唯一の一般的記号である;そして一般性が論証にとって本質的である’ (Peirce 1931-58,3.363;又4.448&4.531も参照のこと)。ソシュールが恣意性の原理の重要性を強調するのは、象徴的記号を優先することの反映であり、一方パースは、ホモ・サピエンス(人類)を‘象徴記号を使用する動物’と呼んでいる(Peirce 1931-58, 2.299)。記号システムが象徴記号の様態へ進化していくという考えは、そのような視点と一致する。パースは、‘記号に生命があるとしたら -必要な媒体は存在するとするが- それは一連の発展過程を通っていくだろう’と推測している。面白いことに彼は、これが象徴的形式という‘理想形’への必然的な歩みとは表明していない。というのは、‘形式変化の同じ循環が繰り返し記述される’という理論的な可能性を許容しているからである (同上, 2.111)。そのような可能性を認めている一方、‘通常の進歩は...、類像記号、指標記号、象徴記号の順で起こることは注意すべきかもしれない’と述べている(同上, 2.299)。パースは、類像性を意味作用が元々欠如している様態として位置付けており、類像記号を‘原初的な記号’と宣言している(同上, 2.299)。そして、これを‘分類のうちで最も素朴、単純そして本来の記号’であると定義している(同上, 2.90)。‘純正の記号...または象徴記号’と比較すると、指標記号は‘すこし退化したもの’であり、類像記号は‘大きく退化したもの’であるとしている。パースは、記号は‘もともと部分的に類像的であり、部分的に指標的’であると述べている(同上, 2.92))。彼は、‘エジプトの象形文字のような初期の書き物ではすべて、非論理的種類の類像記号である表意文字があった’と加えている。そして、彼は‘話し言葉の初期の形式には、ものまねの要素が多かったのではないだろうか’と推測している(同上,2.280)。しかし、時が経つとともに、言語記号はより象徴的かつ慣習的な特性を育成していった(同上, 2.92,2.280)。‘象徴記号は、他の記号特に類像記号から発展した形で生れてきた’(同上, 2.302)(同上,)。
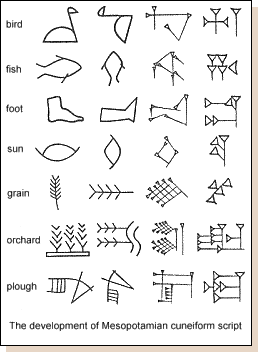 歴史的な証拠も、言語記号は指標的そして類像的形体から象徴的形式へ進化する傾向にあることを示している。アルファベットは、最初は音声を慣習的象徴記号で置き換えたものではなかった。Marcel Denesiは次のように述べている。‘考古学的研究は、以下のことを示唆している...アルファベットの書き物の始まりは、飾り像や小銭製造者が今日使っている鋳型のような、イメージを形成している対象の基本形状から生成された象徴記号にある。その後、それらはもっと抽象的な性質を持つようになった’ (Danesi 1999, 35; see Schmandt-Besserat 1978を参照のこと)。ギリシャ語やラテン語のアルファベットの何文字かは、エジプトの象形文字の類像記号から来ている。地中海文明の初期の字体は、絵文字や表意文字や象形文字を使っていた。これらの多くは直接的または比喩的に、参照している事物や動作に似せている類像的記号である。時間が経つと、絵としての書き物はより象徴的になり、類像的な要素が少なくなっていった(Gelb 1963)。類像的なものから象徴的なものへの移行によって、‘のみや葦のはけの利用による口述筆記が、効率的に出来るようになったと言えるかもしれない’(Cherry 1966, 33);一般に、象徴記号は記号論的にはより柔軟で効率的である。人類学者のC・レヴィ=ストロースは、特定の文化の概念体系で、明確な有契性から恣意性への移行が見られることを認めている(Levi-Strauss 1974, 156)(Levi-Strauss 1974,156)。
歴史的な証拠も、言語記号は指標的そして類像的形体から象徴的形式へ進化する傾向にあることを示している。アルファベットは、最初は音声を慣習的象徴記号で置き換えたものではなかった。Marcel Denesiは次のように述べている。‘考古学的研究は、以下のことを示唆している...アルファベットの書き物の始まりは、飾り像や小銭製造者が今日使っている鋳型のような、イメージを形成している対象の基本形状から生成された象徴記号にある。その後、それらはもっと抽象的な性質を持つようになった’ (Danesi 1999, 35; see Schmandt-Besserat 1978を参照のこと)。ギリシャ語やラテン語のアルファベットの何文字かは、エジプトの象形文字の類像記号から来ている。地中海文明の初期の字体は、絵文字や表意文字や象形文字を使っていた。これらの多くは直接的または比喩的に、参照している事物や動作に似せている類像的記号である。時間が経つと、絵としての書き物はより象徴的になり、類像的な要素が少なくなっていった(Gelb 1963)。類像的なものから象徴的なものへの移行によって、‘のみや葦のはけの利用による口述筆記が、効率的に出来るようになったと言えるかもしれない’(Cherry 1966, 33);一般に、象徴記号は記号論的にはより柔軟で効率的である。人類学者のC・レヴィ=ストロースは、特定の文化の概念体系で、明確な有契性から恣意性への移行が見られることを認めている(Levi-Strauss 1974, 156)(Levi-Strauss 1974,156)。
歴史的な視点は、何人かの学者が‘記号は決して恣意的でない’と主張する根拠となっている(Kress & van Leeuwen 1996, 7)。例えば、Gunther Kressは、記号よりむしろ記号の使用者の意図を強調している(Hodge & Kress 1988,21-2も参照のこと)。Rosalind CowardとJon Ellisは、‘記号表現と記号内容が同一であることは全て生産性とその生産性を制限する作用の結果である’と主張している(Coward & Ellis 1977, 7)。
デジタル記号とアナログ記号の区分も時々、検討される。Anthony Wildenは‘人間の生活や思想において、連続と非連続が最も原則的な2つの範疇であり2種類の経験である’と言っている(Wilden 1987, 222)。我々は、時間は連続体として経験するが、それをアナログまたはデジタル形式で表現できる。(時間、分、秒の針を持った)アナログ表示の時計は、時間をお菓子のように切り分けることができるという利点をもつ(たとえば、それにより授業中、あとどのくらいの時間が残されているか‘見る’ことができる)。(現在時刻を数字で表示する)デジタル表示の時計は、正確さという長所をもつ。それにより、‘いま’何時かを正確に知ることができる。ある時計(日本では殆どの時計)では、アナログ表示でさえデジタル時計の上で模擬されている。
我々は、アナログ様式に深く馴染んでいるので、デジタル表現を‘実物ではない’また‘本物ではない’と見る傾向がある -少なくとも、最初の段階では(例えば、オーディオのレコードLPとCDの場合のように)。 アナログ/デジタルの区分は、しばしば‘自然のもの’対‘人工的なもの’に例えられる。多分、部分的であるが、これは無意識 -我々の中のもっと深い部分と考えている- が相似的に作用しているのではないかという考えと結び付く(Wilden 1987, 224)。アナログ的なものが優先されるというのは、ロ-マン主義主義思想における無意識が占める位置と合理性の挑戦(それは未だに、我々自身は‘個人’であるという概念を支配している)ということに関連付けられるかもしれない。 デジタル・コードではコミュニケーションするという計画的な意図が主体であり、アナログ・コードでは‘コミュニケーションしないなんて、およそ不可能である’(ibid., 225)。 意識的な意図の他に、我々は、身振り、表情、声の抑揚等々で、コミュニケーションする。アナログ・コードは、止むを得ず、そのようなものを我々の気分、姿勢、意志や誠実性(または他のもの)を表す‘方法を付与する’ 。しかし、1971年にデジタル時計が現れ、それに引き続いてのオーディオやビデオ録画での‘デジタル革命’がエレクトロニクス技術のデジタル・モードに我々を巻き込んだかもしれないが、デジタル・コードは言語の初期の形態から存在していた -書くことは、‘デジタル・技術’である。表現するシステムは、我々がしばしば動的で切れ目のない流れととして経験することに、デジタル的な順序を強制する。あるものを記号として定義すること自体が、連続体を離散体に変えることを含んでいる。 後で見るように、2項分割あれまたはこれは、意味構造を生成する基礎的な過程である。デジタル記号は、言葉や‘整数’ のような離散的単位を包含し、意味されるものの分類分けに依存する。
(映像、身振り、手触り、味や匂い等のような)アナログ記号は、連続体上の等級付けされた関係を含む。それらは‘言葉では表せない’、限りなく微妙なものを意味する。感情や感覚は、アナログ的意味内容である。象徴的な記号表現とは違い、有契的ないくつかの記号表現は互いに混合する(記号内容も同様である)。微笑や笑いのような動的なアナログ記号の包括的な分類表はあり得ない。勿論、(音楽や静止画や動画のデジタル記録に示されるように)アナログ記号はデジタル的に再生できるが、言語記号のようには直接、標準的な‘辞書’や‘文法’と関係付けられない。Bill Nicholsは次のように述べている。‘アナログ・コードの等級付けされた性質は、それらの意味を豊かにするかもしれないが、構文上の複雑さと意味の正確さを痩せさせる。それに対して、デジタル・コードの離散的単位は意味を希薄なものとするが、複雑さや意味作用をより大きくできる’(Nichols 1981, 47; Wilden 1987, 138, 224も参照のこと)。美術史の研究者Ernst Gombrichは、‘文章は映像に変換できない’そして‘絵画は言明できない’と主張している -この主張はパースにおいても見出される(Gombrich 1982, 138, 175; Peirce 1931-58, 2.291)。それでもやはり、そのような伝達目的に役立つ映像は‘理解するために開放されている’かもしれないのに対して、現在の視覚的な宣伝は、広告会社が言葉で明らかにしようとしない暗黙の主張を生成するために映像がどのように使われるかを示す強力な例である。
イタリアの記号学者ウンベルト・エーコは、何人かの研究者が‘恣意的’、‘慣習的’と‘デジタル的’を明確に等しく置いていること、を非難している。彼は、次のような広く行き渡った組み合わせ表が、縦に並んだ用語はここでは同義語であると誤って示唆する、やり方に注目している(Eco 1976, 190)。例えば彼は、写真は‘有契的であり’、‘デジタル的’であると見ている。(社会的また文化的な慣習に依存する)‘慣習性’は(記号表現と記号内容の本質的な結びつきを欠いた)‘恣意性’と等価ではない。そのような用語を等しく取り扱うのはたやすいが、この教科書はこれとは異なる立場をとる。後で触れるが、我々がたびたび(多分、不可避的に)知らないうちにだまされている相似性(analogy)という見方の方を好む。
| デジタル的 | 対 | アナログ的 |
| 恣意的 | 対 | 有契的 |
| 慣習的 | 対 | 自然の |
記号負荷体のもう一つの区分は、パースによって導かれたトークンとタイプという言語的な概念と関連している (Peirce 1931-58, 4.537)。話や書かれたテクストの中の単語を例とすると、トークンの個数は(タイプに関係なく)単語の全数であり、タイプの個数は異なる単語の、繰り返しは無視した個数である。意味論の言葉では、トークンはそのタイプを例示する(タイプの具体例である)。‘Word’と‘word’は、同じタイプの具体例である。言語はトークンとタイプの間の区分、つまり特定の例と一般的な分類に依存する。これは分類の基礎である。John Lyonsは、あるものがあるタイプのトークンとして数えられるかどうかは、その人の目的によると述べている。例えば:
記号論的視点からは、次のようなことによってのみ、そのような疑問に回答できる。特定の何かを意味する行為という文脈で、異なる形式が、関係する記号使用者にとって重要ななにかを意味しているかどうかを考慮する。
エーコは、3種類の記号負荷体を列挙している。その区分は、部分的に材料の種類に関係することは注目される:
タイプ-トークンの区分は、テクストを理解する方法にも影響している。文学者であり哲学者であるWalter Benjamin(1892-1940)は、影響力のある随筆‘機械的再生産の時代における芸術の働き(The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction)’に、技術社会はもとの作品から再生産された物 -もとのタイプのトークン- に支配されてしまうと述べている(Benjamin 1992, 211-244)。例えば、有名な油絵の‘原画’を見るときでも、恐らく最初は、それをまずいろいろな複製(本、絵はがき、ポスター -時には、同じテーマの模造画や変形したテーマ)で見たであろう。そして、それまでに出会った複製や変形によって形成された判断の光で、本物を‘観察する’ことができる(テクスト間相互関連性Intertextualityを見よ)。ポストモダンの時代には、大部分のテクストが‘原本を持たない複製’である。
記号のタイプ-トークンの区分は、社会記号論の用語としては記号負荷体の絶対的属性としてではなく、その記号を使うことに巻き込まれた人々にとって、与えられた状況で(特定の目的のために)重大なものである場合にかぎり重要となる。おなじ包みのトランプカードの、裏のパターンに生じた少しの違いもギャンブラーにとって生死の問題となる。しかし、コレクターにとっては、(スペードのエースのような)各タイプのデザインのスタイル上の差が、トランプカードが異なる組のものであるかどうかを見分けるものとしてとして問題となる。
既に示したように、ソシュールは記号表現と記号内容の両者を、非物質的な‘心理学的’形式と見ていた;言語それ自身は‘形式であり、物質でない’(Saussure 1983, 111, 120; Saussure 1974, 113, 122)。彼は、要点を強調するためいくつかの例を挙げている。例えば、いくつかあるチェスとの相似のうちの一つで、‘もし象牙の駒の代わりに木製の駒を用いたとしても、その変化はシステムに違いをもたらさない’ (Saussure 1983, 23; Saussure 1974, 22)。この機能的な方法を追いながら、彼は他のところで、ジュネーブ午後8時25分発のパリ行きは機関車、列車、乗客が変わっても‘同じ列車’と言われると記している。同様に、完全に作り直された街路が何故‘同じ通り’なのかという問いも出している。彼は、それが‘純粋に物質的な構造物ではないかからである’と示唆している(Saussure 1983, 107; Saussure 1974, 108)。ソシュールは、そのような実体(entity)は‘抽象的’であると言っているのではない、というのは物質的な現実性なしで街路や列車を思い浮かべることはできない、と主張している -この物理的な存在は、それらが何であるか理解するのに必須である(Saussure 1983, 107; Saussure 1974, 109; また同上,15を参照のこと)。これは、タイプ-トークンの区分と関係付けることができる。ソシュールは、言語を物質的な実体ではなく形式的な機能と見ていたので、システムにおいて同じ機能を果たす何物も同じタイプのもう一つのトークンとして認識していた。言語に関しては、ソシュールは‘物質的な要素である音声は...単に補助的であり、言語が使用する物質である’と見ていた(Saussure 1983, 116; Saussure 1974, 118)。言語的な記号表現は‘どのみち物理的でない。それらは、一つの音声パターンを他のものから識別する差異によってのみ構成されている’ (Saussure 1983, 117; Saussure 1974, 118-119)。彼は、不承不承、一点だけ認めている。‘言語記号は、話す場合には実体的である:書くことは慣習的な形でそれを固定する’ (Saussure 1983, 15; Saussure 1974, 15)。しかし、書かれた記号については、次のように注釈を付けている。‘碑文の実際の様態は、それがシステムに影響を及ぼさないことから、重要でない...。黒または白、彫りこみ文字または浮き彫りで書こうが、ペンまたは鏨を用いようが、どれも意味にとって重要ではない’ (Saussure 1983, 118; Saussure 1974, 120)。言語学者がいかに言語の形式と機能を重視し、言語の物質的な形を周辺の問題と見ているか理解できるだろう。‘言語学者は...トークンではなくタイプに興味を引かれている’((Lyons 1977, 28))。
これは言語学者のソシュールだけでなく、哲学者パースの姿勢でもある:‘"man"という言葉は...インクの三つのにじみから成っているのではない。もし、"man"と言う言葉が、数万部印刷される本の中に数百回使われたとしても、数百万にもなる三つ組のインクのかけらはたった一つの同じ言葉の化身なのである...おのおの化身は象徴記号の複製となる。これは、言葉はものではないことを示している’((Peirce 1931-58, 4.447))。パースは、記号の物質性にも触れている:‘記号は表象されるものと同一でなくある観点からはそのものとは異なるので、それは自分自身の中に物質に属するある特性を明瞭に持たねばならない...。これを記号の物質的性質と呼ぶ。’彼は、物質性は記号の属性であり、‘認知理論においては非常に重要である’ことを認めていた。物質性は、‘その表象機能を果たさない’また彼の類別の体系には現れてこない。しかし、物質性の表象能力に簡単に言及している:‘ある性質をもつ物を全て取り上げ、それらを他の系列の物と互いに物理的に接続すれば、記号とよべるものになるだろう’。例えば、ある人にとって赤い花の色が関心事であれば、赤みが記号となる(同上, 5.287))。
ソシュールが言語記号の物質性を無視することを選んだのに対して、彼のモデルを採用した後継者たちは、記号の(厳密には記号表現の)物質性を再び取り上げることを選んだ。記号学者は、記号使用者が意味をそれに帰する要因を捕らえなければならず、そして記号の物質的な形体は差異を作り出す。現在の記号学者は、記号の物質的形式はそれ自身の共示義(connotations) を生成するかもしれないと考えている。1929年ごろ、Valentin Voloshinovはマルクス主義と言語哲学(Marxism and the Philosophy of language)を出版し、その中で記号に関するソシュールの心理的かつ暗に含まれている唯心論的モデルに対して、唯物論からの批判を行った。Voloshinovは、ソシュールのモデルを‘抽象的な客観主義’の‘最も衝撃的な表現’と記述している(Voloshinov 1973, 58)。彼は、‘記号は外部世界の現象である’そして‘記号は...特定の物質的なものである’と主張した。すべての記号は、‘音、物理的な質量、色、身体の動き、それらと同様なもののような物質的な体現である’(同上, 10-11; 10-11;28を参照のこと)。Voloshinovにとっては、言語を含めて全ての記号が‘確固とした物質的な実在’((同上, 65))であり、記号の実質という物理的な性質を有している。
心理分析理論もまた、記号表現の再評価に寄与している -フロイドの夢の理論においては記号表現である音声の方が、従来の‘記号解読’が示唆するものよりも、起こりうる記号内容への良い指針と認められている(Freud 1938, 319)。例えばフロイドは、婚約中の婦人のスズランとスミレの花の夢について報告している。一般的な象徴主義ではスズランは純潔の象徴であり、彼女がスズランの花から純粋を連想していることに示唆している。しかし、フロイドは、彼女が音声的に‘スミレ(violet)’から英語の単語‘暴力(vioalate)’を連想し、これは‘花を手折る’暴力を恐れていることを示唆していることを発見し、驚いている。もしこれが聞いたことがあるように思えるなら、この特殊な夢の主題は映画Final Analysis(1992)で取り上げられている。心理分析者ジャック・ラカン(最初は1957年に)が強調しているように、凝縮(condensation)と転移(displacement)というフロイドの概念が、夢の中での記号表現による記号内容の決定ということを説明してくれる(Lacan 1977, 159ff)。凝縮ではいくつかの考えが一つの象徴記号に凝集され、転移では無意識の願望が(夢の検閲を避けるため)些細な象徴記号に置き換えられる。
ポスト構造主義者は、記号表現の価値を回復しようとしている。ソシュールの言語記号における物質性の軽視と結びついた音声中心主義は、1967年に挑戦を受けることになる。その年、フランスのポスト構造主義者ジャック・デリダが、彼の著作グラマトロジーについて(Of Grammatology)の中で、ソシュールの中に見られる書き物に対する話の優位性を攻撃した(これは彼の前後の言語学者にも見られる)(Derrida 1976)。プラトンからC・レヴィ=ストロースまで、西欧的な世界観では話し言葉が優位性を保ってきた。そして、我々の自我に深く組み込まれ、真実と真正という記号を構成している。話し言葉は全体として自然なものとなっているため、‘記号表現と記号内容が一体となっているように思われるだけでなく、このような混乱の中で記号表現は自分自身を消去するか透明になっているように思える’(Derrida 1981, 22)。書き言葉は、伝統的に第2の位置に落とされていた。脱構築グループは、‘抑圧されたものの復権’を謳っている(Derrida 1978, 197)。‘グラマトロジー’の確立またはテクスト性の研究を模索して、デリダは物質的言葉の最優位性を擁護してきた。言葉の特質はそれ自身、物質的次元であると彼は記している。‘言葉の物質性は翻訳できないし、他の言語に持ち越すことはできない。物質性は、まさにどの翻訳も放棄したものである’ -この翻訳もたぶんそのような損失の例となっているだろう(同上, 210)(同上,210)。ロラン・バルトも、書く行為における記号表現の役割を再評価しようとした。‘古典的な’文学では、作者は‘常に記号内容から記号表現へ、内容から形式へ、考えからテクストへ、また心で思うことから表現へ進むと思われていた’(Barthes 1974, 174)。しかし、これはバルトが書く行為というものを特色づけようとした方向とは反対である。彼にとっては、書くことは記号表現とともに作業することでありり、記号内容を自分自身で始末させることである -この逆説的な現象はほかの著者からも報告されている(Chandler 1995, 60ff)。これに続く理論家たちも、言語的記号の‘再物質化’を模索し、言葉は事物でありテクストは物質世界の一部であると強調している(例えば, Coward& Ellis 1977; Silverman & Torode 1980)。
Jay David Bolterは次のように論じている。‘記号は常に媒体に係留されている。記号は多かれ少なかれ、ある媒体の特性に依存する -それらの記号は多かれ少なかれ、うまく他の媒体に乗り換えられるかもしれない- しかし、媒体なしでは記号のようなものは存在しない’ (Bolter 1991, 195-6)。これは少し誤解を招く。というのは、Justin Lewisが記しているように‘記号は、物質的な存在ではない、というのは意味は言葉や対象へ運ばれて来るものであり、それらの中に刻まれているものではないからである。記号表現 -意味に先行する単位- だけが物質的実在物として存在する’(Wren-Lewis 1983, 181)。それにも拘らず、Bolterの指摘は記号の負荷体へ適用できる。そしてHodgeとTrippが述べているように‘全ての記号論的分析の基礎となるのは、どの記号のシステム(記号論的コード)も、それ自身の構造原理を持った物質的媒体によって運ばれることである’ (Hodge & Tripp 1986, 17)。そのうえ、ある媒体は相互作用のある、複数の記号システムを帯同している:例えば、テレビと映画は言葉、映像、音楽そして運動する記号を活用する。媒体は‘中立的’ではない;それぞれの媒体は制約があるし、ウンベルト・エーコが述べているように、すでに‘文化的意味作用で充満している’(Eco 1976, 267)。例えば写真や聴視覚媒体は、他の表現形体より‘真実に近い’と常に認められている。Gunther KressとTho van Leewenは‘テクストの物質的表現は、常に意味のあるものである:それは一定しない記号論的特徴である’(Kress & van Leeuwen 1996, 231)。形式または媒体のレベルで記号表現を変えることは、記号内容に影響を与える -それは、見かけ上同じ‘内容’を持つものから読者が作る意味である― 。ファックスで絶交宣言することには、会って絶交を言うのとはちょっと違った意味が認められる。
以前に、形式と内容の間の不確実な区分に触れた。言語学者ルイス・イェルムスレウは‘表現を伴わない内容または無表情な内容はありえない;また内容を伴わない表現または内容なし表現はありえない’と認めている (Hjelmslev 1961, 49)。しかし、彼は分析的な区分を容易にする枠組みも提案している(同上, 47ff)(, 47ff)。これを表現と内容の‘平面’(ソシュールの記号表現と記号内容)とし、このモデルを充実させた(同上, 60)。彼の貢献は、表現、内容はともに実質と形式を有していることを示唆したことである。このように、四つの範疇が存在する:表現の実質、表現の形式、内容の実質、内容の形式。Christian Metzのようなさまざまな研究者がこの理論的区分に依拠し、この四つの範疇になにか異なることを割り当てている(Tudor 1974, 110; Baggaley & Duck 1976, 149; Metz 1981を見よ)。
| 実 質 | 形 式 | |
| 記号表現: 表現の平面 | 表現の実質: 媒体の物理的素材(例;写真、録音された声 、紙に印刷された言葉) | 表現の形式: 言語、形式的な統語構造、技術および文体 |
| 記号内容: 内容の平面 | 内容の実質: ‘人間的内容’(Metz)、文字の世界、主題、分野 |
内容の形式: ‘意味的構造’(Baggaley & Duck)、‘語幹構造’(話も含む)(Metz) |
ソシュールは、言語は‘形式であって実質ではない’と主張したが、イェルムスレウの枠組みは、テクストをいろいろな次元から解析することとそれぞれに意味作用の可能性を認めることを可能とする。そのような基盤は、テクストの系統的な分析のための有効な枠組みを提供し、何が記号を構成しているかに関する考えを広げそして記号の物質性はそれ自身で意味することを気付かせる。
明らかに、社会的記号の観点から、Gunther KressとTeo van LeeuwenはMichael hallidayの言語モデルを採用し、記号システムは三つの本質的な超機能を有していると主張した:
特定の記号システムはコードと呼ばれる。


