- 3次元 − 平面
- 詳細 − 抜粋
- 多色 − 単色
- 編集されている − 編集されていない
- 動的 − 静的
- 音が聞こえる − 静粛
- 可能 − 不可能
- 本当らしい − 本当らしくない
- お馴染みの − 馴染みのない
- 時間的には現在 − 時間的に離れている
- 空間的には部分 − 空間内で離れている
- this [pipe] is not a pipe; これ[パイプ]はパイプではない。
- this [image of a pipe] is not a pipe; これ[パイプの図]はパイプではない;
- this [painting] is not a pipe; これ[絵]はパイプではない;
- this [sentence] is not a pipe; これ[文]はパイプではない;
- [this] this is not a pipe; [これ]これはパイプではない;
- [this] is not a pipe; [これ]はパイプではない。
- 科学的にみれば、牛は究極的には原子、電子などから構成される。それは現状の科学的推測による...。
- 我々が認識する牛は言葉ではなく経験の対象であり、それは神経系統が抽象化した(選択した)物である...。
- (乳牛)‘ベッシ−’という言葉はlevel2の認識対象に与えられた名称である。その名前は対象ではない;それは単に対象を表しているに過ぎず、対象の多くの特性への指示を除いている。
- ‘乳牛’という言葉は牛、牛、牛...牛に共通する物として抽象化した特性をあらわしている。
- ベッシ−が‘家畜’として指示される場合のみ、豚や鶏、山羊等と共通して持っている性質が留意される。
- ベッシ−が‘農場の資産’に含まれる場合は、指示は、農場における他の全ての売却可能な項目と共通なことに対してなされる。
- ベッシ−が一つの‘資産’(asset)として指示される場合は、もっと多くの彼女の特徴が省かれる。
- ‘財産’(wealth)という言葉は最高に高いレベルの抽象化であり、ベッシ−の特徴に関する指示は殆ど除かれてしまう。
(McKim 1972, 128; この例の原典はKorzybskiの中にある、via Hayakawa 1941, 121ffを介して) - 指示的な相 − 記号表現と指示物は直接結ばれていると見なされる;
- 類像的な相 − 記号表現は指示物の一部ではなく、それを明瞭に描くものと見なされる;
- 象徴的な相 − 記号表現は恣意的であり、ただ他の記号を指示すると見なされる。
- それは基本的な実在の反映である。
- それは基本的な実在を隠し、変質させる。
- それは基本的な実在の不在を隠す。
- それはどんな実在とも関係を持たない:それはそれ自身の純粋なシミュラークルである。(Baudrillard 1988, 170)。
Semiotics for Beginners
-初心者のための記号論-
Daniel Chandler (University of Wales)
記号論には、テクスト分析という形で出会うことが多いが、それはまた、実在(reality)の構築における記号の役割に関する哲学的な理論付けを含んでいる。記号論は表現と、表現という実践活動に含まれる過程に関する研究を包含する。そして、記号学者にとって、‘実在’は常に表現を含む。
記号学者にとって、記号を決定する特徴は、それらが使用者にとって他の物の‘意味する’また表現する物として扱われることである。ジョナサン・スイフトの、ラガーゴの虚構の学者に関する皮肉っぽい物語は、記号が我々の世界にある物理的な物の代わりに直接なるという常識的な考えの不適切さを浮かび上がらせている。
-
全ての言葉を廃止する案は、簡略さと健康のために良いと主張されている。我々が話す言葉は、腐食作用によって肺を減少させているのであり、その結果、命を縮めているのである。言葉は単に物の名前なので、全ての人が話したいと思う用件に必要な物を運べばもっと便利なのではないかいう案が出されている。もし女性たちが、粗野な人や無学な人たちと一緒になって、祖先のように舌で話す自由をゆるさなければ叛乱を起こすと脅さなければ、この発明は実現するところであった;科学にとって常に和解できない敵は民衆である。教養のある人や賢い人は、物自体のよって表現する方法に固執しているが、一つの問題点はある人の用件が大きくまた種類が多いと、召使がいないと背中に大きな荷物を背負っていかなければならないことである。私は、我々のまわりの行商人のように荷物の重みで沈みかかっている賢人を二人見た;通りで会うと、荷物を降ろし、包みを開け一時間ほど話をする;それから、道具を包み、荷物を背負うのを互いに助け合い、去っていく。
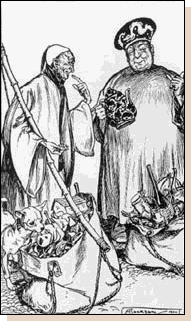
-
しかし、短い会話のためなら、ポケットや小脇に抱えて道具を運ぶことができるし、家の中では困らない:このため、この方法を実行する人たちが集まる部屋は、この種の人工的な会話を行うために用意された物で一杯になってしまう。この発明のもう一つの利点は、全ての文明国で理解される世界語として使えれることである。その文明国では、所有品や家庭用品はおなじ種類か似た物になるので、その使い方をすぐ理解できる。そして、大使は、話し方が分からない外国の王女や首相と折衝するのが容易になるだろう。
(ジョナサン・スイフト[1726/1735]:ガリバー旅行記,第3巻,‘ラピュタ、バルニバービ、ラグナグ、グラブダブドリップおよび日本への航海’、第5章‘)
ラガーゴの学者からの言葉の代わりに物を用いるという提案は、記号は物の直接的な代用品であるという簡単な考え方の問題点を際立たせる。その学者は、言葉は外部世界の対象を単純に反映していると仮定する素朴な実在主義という哲学的な立場を採用している。彼らは、‘言葉は単に物の名称である’と信じており、‘物’は言葉によって‘分類される’前に、言語と独立に必然的に存在するという考えをとる。この立場(それは言葉についてまだ広く行き渡っている一般的な誤解と一致する)によれば、言葉と指示物の間には一対一対応(時に言語学の言葉で同形(isomorphism)と呼ばれる)があり、言語は単に命名法(nomenclature)である −世界における物の品目ごとの命名である。ソシュールが述べたように、これが‘一般大衆の表面的な見方’である(Saussure 1983, 16, 65; Saussure 1974, 16, 65)。
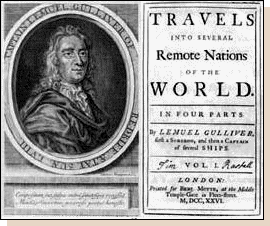 言語という語彙目録の中では、言葉の大部分は‘物’を指す‘辞書的言葉’(名詞)であるというのは真実であるが、これらの物の大部分は、この世界における物理的な対象というより抽象的な概念である。‘固有名詞’のみが、日常世界で特定の指示物をもつ。そして、これらのうちのある物だけが唯一の実体を指示する(例えば、Llanfairpwllgwyngyll−gogerychwyrndrobwllllantysiliogogoch−ウエールズの村)。Rick Altmanが記しているように、‘競馬の予想紙で用いられているような、固有名詞だけで編成されている言語は表現上、重要な利点をもたらす;すべての名前は特定の馬に対応し、同定する’(Altman 1999, 87)(Altman 1999,87)。しかし、充分機能化された言語を使って伝達するには、個々の実例の特殊性を超越した指示の広がりを必要とする。木の葉や雲や笑いは個々には他のものとは異なるが、効果的な伝達のためには一般的な分類や‘一般概念’が必要となる。言語を共有していない人とコミュニケーションしようとした人はだれでも、物しか指し示すことができないとことの限界を知っている。‘心’や‘文化’や‘歴史’は指し示すことができない;これらは物ではない。ある言語における辞書的言葉の大部分は、高度な抽象化レベルにあり、(‘建物’のような)物のクラスや(‘建設’のような)概念を示している。言語は分類に依存しているが、実例をクラスに分類する(トークンからタイプへ)やいなや、(もし‘物’で特定の対象を意味しているなら)言葉と物との一対一の対応は無くなってしまう。その上、言語から辞書的言葉を除いた語彙目録の残りの要素は、世界に存在する対象を全く意味しない‘機能的言葉’(または‘ただ一つ’や‘...の下に’といった文法上の言葉)である。言語という語彙目録は、単純に名詞だけで構成されているのではなく、多くの種類の記号から構成されている。言語が物の名前に還元できないのは明確である。
言語という語彙目録の中では、言葉の大部分は‘物’を指す‘辞書的言葉’(名詞)であるというのは真実であるが、これらの物の大部分は、この世界における物理的な対象というより抽象的な概念である。‘固有名詞’のみが、日常世界で特定の指示物をもつ。そして、これらのうちのある物だけが唯一の実体を指示する(例えば、Llanfairpwllgwyngyll−gogerychwyrndrobwllllantysiliogogoch−ウエールズの村)。Rick Altmanが記しているように、‘競馬の予想紙で用いられているような、固有名詞だけで編成されている言語は表現上、重要な利点をもたらす;すべての名前は特定の馬に対応し、同定する’(Altman 1999, 87)(Altman 1999,87)。しかし、充分機能化された言語を使って伝達するには、個々の実例の特殊性を超越した指示の広がりを必要とする。木の葉や雲や笑いは個々には他のものとは異なるが、効果的な伝達のためには一般的な分類や‘一般概念’が必要となる。言語を共有していない人とコミュニケーションしようとした人はだれでも、物しか指し示すことができないとことの限界を知っている。‘心’や‘文化’や‘歴史’は指し示すことができない;これらは物ではない。ある言語における辞書的言葉の大部分は、高度な抽象化レベルにあり、(‘建物’のような)物のクラスや(‘建設’のような)概念を示している。言語は分類に依存しているが、実例をクラスに分類する(トークンからタイプへ)やいなや、(もし‘物’で特定の対象を意味しているなら)言葉と物との一対一の対応は無くなってしまう。その上、言語から辞書的言葉を除いた語彙目録の残りの要素は、世界に存在する対象を全く意味しない‘機能的言葉’(または‘ただ一つ’や‘...の下に’といった文法上の言葉)である。言語という語彙目録は、単純に名詞だけで構成されているのではなく、多くの種類の記号から構成されている。言語が物の名前に還元できないのは明確である。
もう少し素朴ではない実在主義者はこの点で、言葉は必ずしも客観的な物質世界の中に存在する物理的な物に名前を付けるのではなく、想像上の物や概念にも名称をつけると言うかも知れない。例えば、パースの指示物は物理世界に存在する物に限定されず、存在しない対象や観念も含む。しかし、ソシュールが述べているように、言葉が概念の名称であるとする考えは‘観念(ideas)は言葉と独立に存在すると仮定している’(Saussure 1983, 65; Saussure 1974, 65)。そして彼にとっては、‘観念は、言語的構造に先行して確立されることはない’(Saussure 1983, 110; cf. 114-115, 118を参照のこと; Saussure 1974, 112; cf. 116, 120を参照のこと)。言葉を対象および先在する観念の‘名札’と見るのが、言語に関する理性論者と‘命名論者’の立場である。言語を物に名前を付けるという純粋に指示的な機能に還元するのが、還元主義者である。我々が言語を使うとき、種々の記号が互いに複雑に関連し合うが、これは言語を命名法に還元するということを無意味なものとする。指示機能は言語の一つの機能かもしれないが、複数の機能の一つにすぎない。しかも、Vivien Burrが言っているように、‘“実在”世界の本質がなんであれ、我々の言語の言葉がそれを指示または記述していると仮定することはできない’(Burr 1995, 60)。記号表現は指示物をもつのが記号の必要条件であるという哲学的にはひびが入った仮定は、ロラン・バルトに‘指示の幻想’(referential illusion)(Barthes 957)またMichael Riffaterraに‘指示の誤信’(referential fallacy)と名付けられている(Genosko 1994, 38, 51; Allen 2000, 115)(Genosko 1994,38,51;Allen 2000,115)。
実在主義者に対する過激な反応は、物は我々が使っている記号システムとは独立に存在しないということである;‘実在’はそれをありのままに表現できるように思われる媒体によって生成される。言語は、先在する分類にありのままに名称を与えるのではない;分類は‘世界’に存在しない(雲の境界はどこか;笑いの始まりはいつ?)。John Lyonsの、実体は常に継ぎ目なく認識されると強調するのは行き過ぎであるとの思慮深い注意を認めるべきかもしれない。Lyonsは、‘現象世界の大部分は、我々がそれを認識するとき、区分されない連続体ではない’と推測している;そして我々が参照する分類は、本質的に目立つように見えるある特徴と関係を持っているように思われる(Lyons 1977, 247; 著者強調; 同上, 260参照のこと)。この考えの裏付けとして、ゲシュタルト心理学では人間には一般に、次のような傾向があると報告している。見る人は顕著な存在(図)を、背景(地)に追いやった物から分離する傾向がある(美術における‘輪郭’についてはGombrichを見よ: Gombrich 1982, 283)。しかし、そのような観察も、言語の語彙構造が外部の実在を反映していることを、明確に示しているものではない。ソシュールが言っているように、もし言葉が先在する物に対する命名法ならば、ある言語からもう一つの言語への翻訳は容易であろう(Saussure 1983, 114-115; Saussure 1974, 116)。しかし実際は、言語によって世界を分類する方法が異なる −ある言語の記号内容は他の記号のそれにきちんと対応しない。言語の中では、多くの言葉が‘同じ物’を指示するが評価は異なる(ある人とっての‘家畜小屋’(hovel)は他の人にとっては‘家’(home)である)。しかも、言葉にとって意味される物は、歴史的に変化する。その意味では、‘実在’または‘世界’は我々が使う言語によって生成される;この論証は、記号表現の卓越性を主張している。‘実在世界’は我々の記号システムの産物であるという急進的な立場を採用しないとしても、経験世界には対応する言葉がない物が多くあり、また殆どの言葉が既知の世界の対象にまったく対応していないことを認めなければならない。このように、全ての言葉は‘抽象’であり、言葉と世界の‘物’の間には直接的な対応はない。
記号のソシュールモデルは、記号の外の実在への直接的な指示を含んでいない。これは言語外の実在の‘否定’でなく、言語学者としての彼自身の役割に関する理解の反映である。大部分の科学分野では‘研究の対象’は‘予め与えられ’、観察者の視点と独立に存在するということことを、ソシュールは受け入れていた。しかし、対照的に言語学では‘対象を生み出すのは、採用された視点である’ことも強調している(Saussure 1983, 8; Saussure 1974, 8)。そのような記述は、(数学のような)自己−充足的であると認められる分野では注釈なしに済ませられるが、人間の言語という文脈では理想化されたモデルであるとどのように非難されるか理解できる。ソシュールのモデルでは、記号内容は心理的概念である;概念は心理的構築物であり、‘外部の’対象ではない。しかし、Rodowickが述べているように、‘対象とその記述の形式または実質の間の差異または不一致という関係を強調することは、表現の欠如を意味しない’(Rodowick 1994, 162)。勿論、概念は経験的実在の何かを指示するが、記号内容がある種の不変の‘実在’で定義される客観世界における明白で自律的な実体であるとする‘実在主義者’(essentialist)の主張の否定が、ソシュール流の立場である(Culler 1985, 24)。ソシュール流の記号学者は、対象の非実在的性質を主張する。記号表現と同様、記号内容は記号システムの部分である;記号内容は社会的に作られる。ウォーフ流の立場によれば、記号内容は我々の文化の‘見方’の恣意的生産物である。ソシュール流の展望は、‘世界が言語の秩序を決めているのではなく、言語が世界の秩序を決定していると提案することにより、命名論者が言語外の世界に与えている優先権を逆転させる傾向にある’ (Sturrock 1986, 17)。
ソシュール流のモデルに対して、パースの記号モデルは指示物(referent)を、明確な特徴としている −指示物は記号負荷体が言及している記号の向こうにある何物かである(必ずしも物質的な物とは限らない)。しかし、それはまた記号の‘無限連鎖’へと導く解釈項も特徴としており、そのため同時にパースのモデルは、記号が指示物から相対的に独立であることを示唆しているように思われる(Silverman 1983, 15)。パースにとっては、実在は記号を介してのみ知ることができる。もし、表現のみが実在に接近する手段であるならば、表現の正確さを判定することはきわどい問題になるだろう。パースは、論理学から、記号の真理値に言及するため‘様相(modality)’の考えを取り入れ、三種類を認めた:現実性、(論理的)必然性そして(仮説的)可能性 (Hodge & Kress 1988, 26)。しかも、記号負荷体の指示物への関係に関する様式(mode)による記号の分類は、様相を反映している −それは、‘実在’に関する記号の外見上の透明度である(例えば、象徴様式は様相が低い)。パースは、論理的には意味作用は部分的な真値しか提供できないと主張している。というのはもし完全な真値を提供すると対象と同一になるので、それ自身を破壊することになる(Grayson 1998, 40で記述されている)。
哲学的な唯心論(idealism)という極端な立場を志向する理論家(彼らにとって実在は純粋に主観的であり、我々により記号を使って構築される)は、ソシュール流のモデルには問題はないとみるかもしれない。まさに、ソシュール流モデルはそれ自身、‘唯心的’として記述される(Culler 1985, 117)。哲学的実在論へ向かう人は(彼らにとって、唯一の客観的実在は我々の‘外部’に存在するのは議論の余地がないほど自明である)、唯心論の立場に挑戦する。実在論の立場にたてば、実在はそれを理解するために使う媒体により‘歪められる’が、その媒体は世界の‘構築’に寄与しない。 −言語や他の媒体が‘実在の社会的構築’に主要な役割をはたすという− 中間的な解釈主義の(constructionist)(または構成主義の(constructivist))立場をとる人たちでさえ、ソシュールのモデルにある社会的実在へのあからさまな無関心に反対する傾向にある。特に、政治的に左派の人たちは存在の物質的条件の重要性を脇に押しやることに反対している。ウンベルト・エーコは挑発的に、‘記号論は原理的に、うそをつくために使われるあらゆる物を研究する分野である’と主張している (Eco 1976, 7)。
社会記号論の観点からは、元々のソシュール流モデルは理解できるように問題が多い。我々の哲学的立場がどうであれ、日常行動では実在に関する表現はほかの物より信頼できる、という根拠にたって活動している。そして、(言語学者に続いて)記号学者が‘様相の印(modality markaer)’と呼ぶテクストの中の手がかりをよって、部分的に行動する。そのような手がかりは、特定の範疇(genre) に属する、ある認識可能な実在の表現としてのテクストのもっともらしさ、信頼性、信用度、真実性、正確性または事実性として種々記述されることに関係している。Gunther Kress とTheo van Leeuwenは次のことを認めている。
- 真実についての社会記号論は、表現の絶対的な真実または偽りを確立すると言いつのることはできない。特定の(視覚的、言葉や他の形での)‘主張’は、真またはそうでないかとして表現されていることを、それは示すことができるに過ぎない。社会記号学の視点からは、真実と言うのは記号過程の構造物であり、特定の社会団体の真実はそのような団体の真実や信念から生じてくる(Kress and van Leeuwen 1996, 159)。
そのような観点からは、実在には創造者がいる;客観主義者により断定されているような単一の実在ではなく、むしろ多くの実在がある。この立場は、言語と実在の間の関係に関するウォ−フ流の枠組みと関係している。解釈主義者は、極端な主観主義者が言っているように実在は際限がなく個人ごとに独特のものである、ということはないと主張している;むしろ、それらは社会的定義の産物であり、地位がばらばらである。実在については論争されており、テクスト表現は‘闘争の場’である。
様相(modality)は、記号やテクストまた範疇に適合または要求される実在の状態を指している。より公式的には、Robert HodgeとGunter Kressは‘様相はメッセージの状態、権威また信頼性、存在論的状態または真偽または事実としての価値を指示している’と宣言している (Hodge & Kress 1988, 124)。テクストを理解するにあたって、解釈者は世界や媒体に関する知識に頼って、それに関する‘様相判定(modality judgments)’を行う。例えば、そのテクストに事実または虚構、現実性または演技、生(なま)(live)または記録されたものであるかを割り当て、そのテクストの中で描かれているできごとやその中でなされている主張の可能性やもっともらしさを評価する。
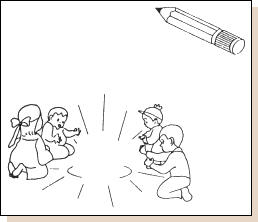 テクストが‘真実’と認識される範囲は、用いられている媒体に部分的に依存する。例えば書物は、映画やテレビより低い様相しか持たない。しかし、媒体の様相の明確な順位付けはできない。John Kennedyは子供たちに、輪になってすわりその真中に空白がある簡単な線画を見せた(Kennedy 1974)。彼は、子供たちにこの空白に彼ら自身の絵を加えるように頼んだ。すると彼らが絵の中央部に意識を集中したとき、多くの子供たちが絵の上の右隅に描かれた鉛筆を取ろうとした。その作業に夢中になることが、実在は媒体の中に構築されているという状況を受け入れさせてしまったのである。これは、子供に限った現象ではないようである。というのは、(多くの媒体で)物語に引き込まれたとき、実在から表現を区別する我々の能力を弱体化することなしに、‘疑惑の停止状態(suspension of disbelief)’に陥る。チャールズ・パースは、‘絵画をじっと眺めていると、それは物ではないという意識がなくなり、実在とそのコピーの区別が消えること時がある’と回想している(Peirce 1931-58, 3.362)。
テクストが‘真実’と認識される範囲は、用いられている媒体に部分的に依存する。例えば書物は、映画やテレビより低い様相しか持たない。しかし、媒体の様相の明確な順位付けはできない。John Kennedyは子供たちに、輪になってすわりその真中に空白がある簡単な線画を見せた(Kennedy 1974)。彼は、子供たちにこの空白に彼ら自身の絵を加えるように頼んだ。すると彼らが絵の中央部に意識を集中したとき、多くの子供たちが絵の上の右隅に描かれた鉛筆を取ろうとした。その作業に夢中になることが、実在は媒体の中に構築されているという状況を受け入れさせてしまったのである。これは、子供に限った現象ではないようである。というのは、(多くの媒体で)物語に引き込まれたとき、実在から表現を区別する我々の能力を弱体化することなしに、‘疑惑の停止状態(suspension of disbelief)’に陥る。チャールズ・パースは、‘絵画をじっと眺めていると、それは物ではないという意識がなくなり、実在とそのコピーの区別が消えること時がある’と回想している(Peirce 1931-58, 3.362)。
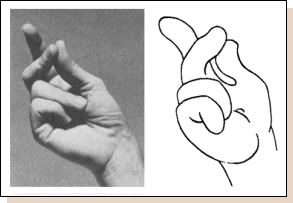 同じ物を撮った写真と漫画を意識的に比較した場合は、写真の方がより‘現実的’と判定されるが、視覚的認識に含まれる心的輪郭は、写真よりも漫画という紋切り型の簡略的な絵に近いかもしれない。人々は手の写真を見せられよりも、漫画の方がすばやく手としてのイメージをつかむことができる(Ryan & Schwartz 1956)。これは、実在を構築する上での認識的コード の重要さを裏書している。ウンベルト・エーコは、習熟により類像的記号表現はその記号内容に対する優越性を確保できる、と主張している。そのような記号は‘受信者がそれに慣れるにつれ、一歩一歩、慣習的になっていく。ある時点で、類像的表現は、どんなに様式化されていても実際の経験よりも真実に近いように思われ、人々は物を類像的慣習という眼鏡で見るようになる(Eco 1976, 204-5)’。
同じ物を撮った写真と漫画を意識的に比較した場合は、写真の方がより‘現実的’と判定されるが、視覚的認識に含まれる心的輪郭は、写真よりも漫画という紋切り型の簡略的な絵に近いかもしれない。人々は手の写真を見せられよりも、漫画の方がすばやく手としてのイメージをつかむことができる(Ryan & Schwartz 1956)。これは、実在を構築する上での認識的コード の重要さを裏書している。ウンベルト・エーコは、習熟により類像的記号表現はその記号内容に対する優越性を確保できる、と主張している。そのような記号は‘受信者がそれに慣れるにつれ、一歩一歩、慣習的になっていく。ある時点で、類像的表現は、どんなに様式化されていても実際の経験よりも真実に近いように思われ、人々は物を類像的慣習という眼鏡で見るようになる(Eco 1976, 204-5)’。
テクストの中での様相の手がかりは以下のように、媒体の様式的な特徴と内容の特徴を含む(高い様相の典型的な手がかりがそれぞれの対の最初に示してある)。しかし、もっとも重要なのは、それらの相互作用と解釈である。

| 様式の特徴
内容の特徴
|
| Cornelius Gijsbrechts (1670): A Cabinet of Curiosities with an Ivory Tankard (showing reverse of cupboard door) Oil on Canvas, Statens Museum for Kunst |
典型的にもっとも‘実在的’と判断される媒体は写真のように精密な描写 −特に映画とテレビ− である。James Monacoは以下のように示唆している。‘映画では、記号表現と記号内容が殆ど一致している...。言語システムの力は、記号表現と記号内容の間に大きな差があることである;映画の力は、それがないことである’(Monaco 1981, 127-8)。これはChristian Metzが映画の記号表現を‘心象の記号表現’として記述しているときに、指摘していることの重要な部分である。象徴記号を使った書物ほどは信頼できないが、映画やテレビや写真は記号表現と記号内容の間の明白なギャップが少ないことほのめかしており、それらは‘実在を反映している’と思わせる(その反映が心象的であっても)。しかし、写真はその対象を再生していない:‘それは実際を抜粋し、伝達する’(Burgin 1982a, 61)。ある物をほかの物と間違えることはしないが、写真や映画はできごとを単純に記録した物でなく、無数の可能な表現のうちの一つであるということは銘記しておく必要がある。すべての媒体のテクスト、しかし‘実在的な’、は実在の単純な記録や再生というより表現である。映画研究家のD N Rodowickは、以下のように言っている。‘実在主義というイデオロギーが一般の人の信頼を得ているように、映画という仕掛けは、“世界”を自発的また自動的に再生するというより、常に選択的に、原材料の映像を限定し、ろ過し、変換する作用を持つ’ (Rodowick 1994, 77)。
映画研究者のAndre Bazinは‘再現の虚偽’を次のように言っている。物を本物らしく見せることのできる唯一の表現は、全ての面でそれが表現している物と正確に似ている(またはそう見える)表現だけである。ディジタル資源の再生産を除いて、テクストはそれが表現するのと異なる材料で構築され、表現は複製ではあり得ない。Bazinにとって、美的な写実主義は、より広範な‘実在への真実性’に依存している(Bazin 1974, 64; Lovell 1983, 81)。
様相の判定には、テクスト的表現と日常世界から導かれるモデルとの比較および様式を基礎としたモデルとの比較を含まれる;そのため、それらは世界と媒体が関係しあった経験に依存する。Robert HodgeとDavid Trippの子供とテレビに関する記号論研究は、子供における様相判定の発達 に焦点をあてている(Hodge & Tripp 1986)。
Ien Ang (1985)は、次のように主張している。テレビのメロドラマを見ることには、指示的レベルというより共示的レベルで、視聴者にとって一種の心理的または感情的現実感が含まれている。視聴者は、感情的または心理的に‘生活に即した’表現を見出す(たとえ、指示的レベルでそれが‘非現実的’に見えたとしても)。特に、(ファンにとってはその期間より‘現実的’に見えるかもしれない)長期間の連続ドラマでは、包括的な現実感(generic realism)と呼ぶものもが、もう一つの要因であると著者は言いたい。特定のメロドラマの人物や習慣に通じている視聴者は、ある外部の‘実在’を考えるよりもドラマ自体の包括的要因でその番組を判定する傾向にある。例えばある人物の今の行動は、その人物についてこれまで学習してきたことと一致するであろうか?そのドラマはある程度、それ自体この世界のこととして当然受け入られるかもしれないが、そこでは少し違う物さしが適用されるかもしれない。もちろん、これが、ドラマがそれに依存している‘疑うことの自発的な停止’とColeridgeが呼んだものの基礎となることである。
Robert HodgeとGunter Kressは以下のように論じている:
- 媒体(例えば、漫画本、(時事)漫画、映画、TV、絵画)または内容(例えば、西部劇、サイエンス・フィクション、ロマンス、ニュース)のどちらにより分類されるにせよ、種々の様式は一群の様相の標識と、様式に対する基本線として作用する全体価値を確立する。この基本線は、種々の分野の視聴者/読者、また種々のテクストやテクストの要素によって異なってくる。
表現の‘実在的’スタイルとして認識されるものは、美的コードを反映している。時とともに、ある媒体や範疇におけるある制作方法は、自然なものとなってくる。内容は‘実在の反映’として受容されるようになる。たとえば、大衆的なテレビや映画では、‘隠された編集’(invisible editing)の使用は、大部分の観客にとって‘自然’と思えるようになるほど普及した慣例の代表的なものである。‘実在的’なテクストでは、もっとも目立つのは作品の‘様式’または文体よりも、内容である。‘科学的’談話に関する支配的な方式では、媒体とコードは中性的であり透明であるとしてその役割が割り引かれ、テクストの標識は見えないものに後退する。その結果、‘実在’はその表現に先在し、そして実在は‘それ自身を語る’と思われている:述べられることは、このように‘真理’のオーラ(霊気)を有するようになる。John Taggは以下のように主張している。
- 記号表現はあたかも、先在する記号内容と一体化しているように扱われる、そして...、読者の役割は純粋に消費者になる...。記号内容と記号内容が一体化しているように見えるだけでなく、記号表現は透明になり、概念はそれ自身を呈示するように見える。そして恣意的な記号が、表示と指示物またテクストと世界の見せ掛けの一体化により元から存在する自然なものと見なされるようになる(Tagg 1988, 99)。
しかし、Taggはそのような立場は‘コードの閉鎖的な世界’を仮定すること (同上, 101)、または表現過程の外部に表現されている物が存在することを否定することを必ずしも含まない(同上, 167)xと付け加えている。彼は‘実践と力という問題と意味のきびしい関係’を強調し、‘実在は与えられたテクストが除去、分離したまた意味しない、支配的なかつ支配された談話の複合体である’と主張している(同上, 101)。
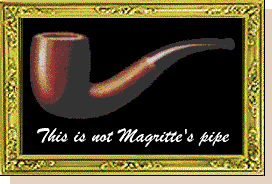 ベルギーのシュールリアリズム(超現実主義)の画家ルネ・マグリット(Rene Magritte)(1898-1967)は1936年にイメージの裏切り(La Trahison des Images)という絵を画いた。それは喫煙用パイプの側面図と‘これはパイプではない(This is not a pipe)’という文を描いている。ここで示されている像は似ているが、文は異なっている−これはマグリットの絵の複製ではない(!)。マグリットの絵とこの絵の両方の例は、我々を戸惑わせる。それは、我々が容易に認識できる対象を‘写実的に’描いている。言語の授業や子供の‘読書’(そのスタイルは、私に昔の子供のためのLadybird社の本(Ladybird book)本を思い出させる)なら、‘これはパイプだ(This is a pipe)’という言葉を期待するだろう。パイプを最初に書き、それから‘これはパイプではない(This is not a pipe)’という主張している標識を付けることは、最初誤っているように思われる。これは単に不合理なのか、またはこの明白な逆説からなにか学べるものがあるのだろうか?なにを意味しているのだろう?我々の心は安定で意味のある解釈を見つけようとしており、この疑問に対する唯一の‘正しい’解答がないということに愉快ではないかもしれない −しかし、曖昧であることに比較的我慢できる人は、それが実在のレベル(または様態)に関して考えるための多くの糧を提供しているのだということを受け入れるかもしれないが − 。指示語の‘これ(this)’が、この絵を理解する鍵と見ることができる:‘これ(this)’という言葉は何を指しているのだろう? AnthonyWildenは、いくつかの解釈を示唆している:
ベルギーのシュールリアリズム(超現実主義)の画家ルネ・マグリット(Rene Magritte)(1898-1967)は1936年にイメージの裏切り(La Trahison des Images)という絵を画いた。それは喫煙用パイプの側面図と‘これはパイプではない(This is not a pipe)’という文を描いている。ここで示されている像は似ているが、文は異なっている−これはマグリットの絵の複製ではない(!)。マグリットの絵とこの絵の両方の例は、我々を戸惑わせる。それは、我々が容易に認識できる対象を‘写実的に’描いている。言語の授業や子供の‘読書’(そのスタイルは、私に昔の子供のためのLadybird社の本(Ladybird book)本を思い出させる)なら、‘これはパイプだ(This is a pipe)’という言葉を期待するだろう。パイプを最初に書き、それから‘これはパイプではない(This is not a pipe)’という主張している標識を付けることは、最初誤っているように思われる。これは単に不合理なのか、またはこの明白な逆説からなにか学べるものがあるのだろうか?なにを意味しているのだろう?我々の心は安定で意味のある解釈を見つけようとしており、この疑問に対する唯一の‘正しい’解答がないということに愉快ではないかもしれない −しかし、曖昧であることに比較的我慢できる人は、それが実在のレベル(または様態)に関して考えるための多くの糧を提供しているのだということを受け入れるかもしれないが − 。指示語の‘これ(this)’が、この絵を理解する鍵と見ることができる:‘これ(this)’という言葉は何を指しているのだろう? AnthonyWildenは、いくつかの解釈を示唆している:
我々は習慣的に、テクストの‘意味’を述べられたまたは推定された作者の目的に関係付けるが、マグリット自身の目的は我々の現在の関心にとって必須のものではない。我々の目的は、この表現は(またはどの表現でも)それが表す物ではないという意味としてその絵はとらえられると示唆することである。このパイプの像は、‘像に過ぎないし’そしてそれでタバコを吸えないことは明らかに思える −正気の人はだれもそれを取り上げて本物のパイプとして使おうとしないだろう(ただ、多くの読者はだまされた男が不幸にも、‘妻を帽子と間違えた’話を聞いたことがあるだろう)。しかし、我々はそのようにリアルに画いた物を見ると、画かれている物以上の何者でもないと考えるだろう。表現は、それが表現する物の単なる再製以上の物である:それは、また実在の構築に寄与する。‘写真写実主義’でさえ、媒介されない実在は描かない。もっとも写実的な表現は、象徴的また比喩的に他の何物かを全面的に‘表象する’かも知れない。さらに、パイプの絵は、それが正確に画いている特定のパイプがこの世界に存在するということを保証しない。まさに、それはかなり一般的なパイプのように見え、特定のパイプというより(あたかも言語の授業、子供用百科事典等でしばしば用いられる)パイプという概念の説明図として見ることもできる。標識は我々の解釈を 係留(anchor) しようとしている −係留は後で触れる概念である− しかし同時に、標識は枠に付けられた題目よりもむしろ絵それ自身の部分でさえある。マグリットの絵は、惰性から抜け出るための一つの試みと見られるかも知れない:我々は、物を見てそれに標識付けするのに慣れているので、その物を深く見ないしまたその特性を把握しようとしない。美術(特に超現実主義美術;シュールリアリズム)の一つの役割は(ロシア・フォルマリズムの人たちが言ったように)‘ありふれた不思議を作る’ことである。
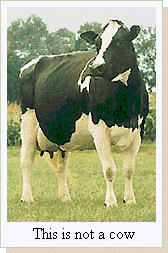
‘一般意味論’として知られる活動の創設者であるAlfred Korzybski(1879-1950)は、‘地図は領土ではない’そして‘言葉は物ではない’と言っている(Korzybski 1933; Chase 1938 and Hayakawa 1941を参照のこと)。勿論、記号と物が一致しないことはソシュール派の基本原則である。しかし、ソシュールのモデルが非実在論である一方、一般意味論者は、言語は我々と客観的世界の‘間’に生じるという立場を採用し、‘実在’の言語的なひずみを打ち消すために、我々の言語行動を矯正しようとする。一般意味論者は、記号表現と指示される記号内容との混乱の一つの原因は、我々がそうであると考えているよりも‘抽象のはしご’に我々を縛り付けることを言語に許すことにあると感じている。ここに、‘ベッシ−(Bessie)’と呼ばれる乳牛に関連した言葉の抽象化レベルの素朴な例がある;
梯子(はしご)という比喩は、抽象化のレベルを示す方法として適している −思索家のことを‘雲の中にある頭’、‘現実家’のことを‘地に足が着いている’と言う。梯子を上るにつれ、特殊から一般に、堅固な現実から抽象的な一般性に移っていく。勿論、一般意味論者は頭の固い実在主義者であり、人々が地にしっかり足を置いておくことを望んでいる。言語の使用者に抽象化のレベルに注意を向けさせる際には、一般意味論者は高位の論理型と低位の論理型を取り違えないように努めている。‘地図’は‘領土’より高位な(より一般的な)論理型であり、そして特に言語表現はこの抽象化のプロセスとして役に立つ。明らかに、ある場所のことを知るのには地図を見るよりは訪れた方がより多くのことを学べるし、また人のことを知るには写真を見るよりは会ったほうが良い。低位レベルから高位レベルに移ることにより、その特性を失うことは避けられない −段々目が細かくなる篩にかけられた土のようにまたは繰り返し複写されたコピーのように。その結果生じる損失に着目すると、不在や排斥は‘一般意味論者’だけでなく記号学者にとっても重要となる。論理学者はそのようなレベルを分離できるかもしれないが、大部分の伝達行為では‘ずれ’が常に生じるが、我々は通常は扱っているメッセージの種類に抽象化のレベルを割り当てることにより同定している。記号学者は、人間のコミュニケーションではある種の‘移行’は避けられないと見る。C・レヴィ=ストロースは、‘理解は、実在のある型から他の型への還元にある’と言っている(Levi-Strauss 1961,61)。A.J.グレマスは‘意味作用は...あるレベルの言語から他のレベルの言語、ある言語から異なる言語への転移に他ならず、意味はそのようなコードの変換(transcoding)の可能性に他ならない’と見ている(Jameson 1972, 215-216に記述されている)。
抽象ということ、をレベルと論理的な型付けという点から考えるのは有用なことだが、一般意味論者の‘抽象化の梯子(はしご)’のなかに暗に含まれた濾過機の比喩はあまりに一次元的過ぎる。認識された‘対象’は単一の‘客観的な’体系ではなく、いろいろな方法で類別される。適用される範疇(categories)は経験、 役割や目的などの要因に依存するが、これが理解に関する論争を引き起こす。例えば、婦人の顔を使った宣伝を見たとき、その像は一般的な婦人を代表しているとある人は思い、他の人は彼女が特定のタイプ、役割やグループを表現していると考え、さらに彼女を特定の個人として認識するかもしれない。そのような像を理解することに関して、適切な抽象化レベルを知ることができるかどうかは関連する文化的 コードに精通しているかどうかによる。
一般意味論者は、言語と実在の関係をもっと‘透明’にするために言語を‘純正にする’という対症療法的ゴールを彼ら自身に課し、それを基にして‘基本的英語(Basic English)’の開発というようなプロジェクトを発足させた (Ogden 1930)。そのようなゴールについてどんな保留条件を付けるにせよ、Korzybskiが恣意性の原則を普及させたことは、我々の心の習慣にとって有用な矯正になると見なされている。警告としては、Korzybskiの警句は不必要に思われる:みんな‘犬’という言葉は吠えないし、かまないことは知っている、しかしある状況下では我々は、記号表現はそれが表す物と不可分であるがごとく振舞う。‘常識’は日常的に記号と物、表現とそれが表現する物を同一視するように誘導する。Terence Hawkesは次のように記している。‘母国語の話し手は必要な“妥当性”、記号表現と記号内容の間の確かな“同一性”、“木”という言葉により作られる“音の映像”と実際の木という概念の間の確かな“同一性”、を仮定する傾向にあると、ソシュールは指摘している。この仮定は、言語の麻酔作用のもとになっている’(Hawkes 1977, 70)。
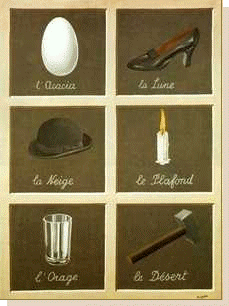
ジークムント・フロイトは、彼の巨大な影響力をもつ本夢判断(The Interpretation of Dreams)の中で次のように主張している。‘夢の内容は、あたかもそれであるように絵文字で表現され、何を象徴しているか翻訳しなければならない...。勿論、これらの象徴を絵としてその価値と関連させて読むのは間違っており、それらの意味はそれらが何を象徴しているかを読むべきである’(Freud 1938, 319)。彼はまた‘言葉は夢の中で物として扱われる’と見ていた(Freud 1938, 319)。マグリットは、記号表現と記号内容を同一視する我々の習慣を、対象と‘それに属していない’言葉の標識をもった一連の線画と絵によりからかった。夢判断という題目がついた油絵で、6個の良く知った対象の言葉の標識が付いた像と出会う。そのような配置は、黒板のような背景によって示唆される言語習得という文脈でお馴染みの物である。しかし、すぐに言葉は絵と対応していないことが分かる。心の中でそれを再配置しようとすると、標識はどの像とも対応していないことが分かるだろう。対象の像とそれに付けられた言葉の標識は恣意的なものとして提示される。
表現と表現された物を混同するのは、精神分裂症や精神異常の特徴である(Wilden 1987, 201)。‘象徴記号を操作するためには、まず記号とそれが表現する物とを区別できるようになることが必要である’(Leach 1970, 43)。しかし、‘実在のレベル’に関する混乱は子供の認識の発達の初期段階における正常な特徴でもある。James Brunerは次のように観察している。就学前児童にとって、考えることと考えている対象は同じような物であるが、学校へ行っているうちに言葉と物を分離するようになる (Bruner 1966)。(最初は身振りや物真似の音声により)指示物の代わりに記号を代用することは、子供が言語を習得する際の難しい局面となる。子供はすぐにそこにない物を指す言葉の魔力を発見する ―この置き換えという性質は、言語にとっての鍵となる‘設計の特色’(design feature)である(Piaget 1971, 64; Hockett 1958; Hockett 1960; Hockett 1965)(Piaget 1971,64;Hockett 1958;Hockett 1960;Hockett 1965)。18ヶ月の時に盲目でかつ耳が聞こえなくなったヘレン・ケラーは、次第に看護婦によって話すことを教えられていく(Keller 1945)。9才のとき水遊びをしていて、手で看護婦の喉と口が‘water’という言葉で震えるのを感じた。意外な事実を発見したと言う衝撃で、彼女は‘全ての物は名前をもっている’という意味の言葉を叫んだ。子供時代の半ばまで、時々、言葉とそれが表す物を分離するのが難しいのは驚くにはあたらない。ピアジェは9歳半の子供との面談で幼い子供の‘申し分のない実在主義’を説明している:
- ‘太陽を‘月’と呼びそして月を‘太陽’と呼べますか?’−‘いいえ’ ‘なぜ駄目ですか?’−‘太陽は月よりも輝いているから...’ ‘しかし、もし皆が太陽を‘月’と呼び、月を‘太陽’と呼んだとしても、それが間違っていると分かりますか?’ ‘はい、太陽はいつも月より大きいので、いつもそれらしくあり、月も同じです’ ‘そうですね。しかし太陽は変わらないでその名前だけですよ。それでも月と呼べませんか?’ ‘呼べません...月は夕方昇るし、太陽は朝です’
(Piaget 1929: 81-2)
このように、子供にとって言葉はとても恣意的には思えない。同様に、Sylvia ScribnerとMichael Coleは、リベリアの教育を受けないVaiの人々が太陽と月の名前は変えられないと感じていることを見出した。彼らの一人は、これらの名前は神から与えられたという見方を表明している(Scribner & Cole 1981, 141)。
人類学者のClaude Levy-Bruhlは次のように主張している。‘原始的な’文明にいる人々は名前とそれが指す物を区別するのが難しく、そのような記号表現を記号内容の本質的部分として扱う(Olson 1994, 28に記述されている)。ユダヤ教とキリスト教の伝統にある‘偶像’に対する恐れやブードー教の呪術的な行いや信仰は、明確にそのような現象と関連している。David Olsonは書物の認識論的な重要性を強調して、次のように主張している。‘文法に沿った書き物’の(約4000年前の)発明(それは印の使用に取って代わった)は、指示語を容易に指示物から区分することを可能とし、言語を純粋に指示的なもの以上とし、言葉はそれ自身の権利として(言語の)実体として考えられるようになった。そのような書き物により‘言葉の魔法’に終止符が打たれ、言葉はそれが指示している物の一部分または本来備わっている性質というより表現と見られるようになったと、彼は示唆している。しかし、中世には言葉と像はまだ(創世記にアダムより与えられた‘本当の名前’をもつ)物との自然な繋がりを持っていると見られていた。言葉は表現というより物の名前と見られていた。ミシェル・フーコー(1926-84)が示しているように、近世の始めに、学者は言葉や記号表現を複写としてよりも慣習に縛られた表現と見なすようになった(Foucault 1970)。17世紀までに表現(記号表現)、観念(記号内容)と物(指示物)との間に明確な区別がなされるようになった。そのとき学者は、記号表現は物を直接指示するというより観念を指すと見なすようになった。表現は、それが表現する物やその作者の両者から比較的独立した慣習化された構築物であった;知識は、そのような記号の操作を伴うようになった。Olsenは、いったんそのような区分が成されるようになるや、表現の資格に関する様相 −それらの認識される真偽や的確さ− の判定を行うことへの道が開かれたと述べている(Olson 1994, 68-78, 165-168, 279-280)。記号へと向かう17世紀の方向変換は‘中立性’、‘客観性’や‘真理’の探索の一部であったが、現代では、当然、‘意思や解釈を伴わない表現はない’という認識に至っている(Olsen 1994,197)。
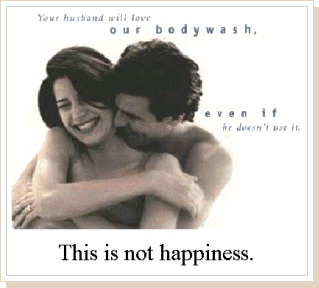 ある人が天文学者に、まだ知られていない星の名前をどうやって見つけたのか聞いたそうである。気のきいた学者なら、名前が物に‘所属している’という考えをからかうことができただろう。Aldous Huxleyの小説の一つで、年取った農夫が豚を指し示した:‘あれを見てください’、ころげまわる豚へ手を動かしながら言った、‘豚と呼ばれるのは当然だ’(Chrome yellow(黄鉛),第5章)。教養ある人は、この種の正真正銘の実在主義に捕らわれることはないかもしれない。しかし、ある記号表現によっては、とても恣意的とは見なされず、ほとんど魔術的な力を得る場合がある −‘写実的な’断言(swearing)や先入観を持った論争のように。これは、記号表現が社会的には恣意的でないということを際立たせる。子供たちは、まさにこれを気付いている:‘棒や石は骨を折るかもしれないが、名前は私を傷つけない’という大人の意見に納得させられているなどいうことは断じてない。University of VermontのThomas Streeterは広告に彼自身が作った標識をつけ加えることにより、言葉のささえを上手に使うことにより指示物を再定義できることを警告した。‘言葉は物ではない’と肝に銘じておくことは、最初思われていたよりも有用かもしれない。
ある人が天文学者に、まだ知られていない星の名前をどうやって見つけたのか聞いたそうである。気のきいた学者なら、名前が物に‘所属している’という考えをからかうことができただろう。Aldous Huxleyの小説の一つで、年取った農夫が豚を指し示した:‘あれを見てください’、ころげまわる豚へ手を動かしながら言った、‘豚と呼ばれるのは当然だ’(Chrome yellow(黄鉛),第5章)。教養ある人は、この種の正真正銘の実在主義に捕らわれることはないかもしれない。しかし、ある記号表現によっては、とても恣意的とは見なされず、ほとんど魔術的な力を得る場合がある −‘写実的な’断言(swearing)や先入観を持った論争のように。これは、記号表現が社会的には恣意的でないということを際立たせる。子供たちは、まさにこれを気付いている:‘棒や石は骨を折るかもしれないが、名前は私を傷つけない’という大人の意見に納得させられているなどいうことは断じてない。University of VermontのThomas Streeterは広告に彼自身が作った標識をつけ加えることにより、言葉のささえを上手に使うことにより指示物を再定義できることを警告した。‘言葉は物ではない’と肝に銘じておくことは、最初思われていたよりも有用かもしれない。
文学研究者のCatherine Belseyは次のように主張している。
-
言語は、我々が世界を“理解する”前に存在するので、命名法として経験される。言葉は物の象徴であると見られる。というのは、言語を構成する差異のシステムの外側では、物を考えられないからである。同様に、これらの物そのものは心の中、つまり思考の自律的な領域で、表現されると考えられている。というのは、思考は本質的に象徴的であり、象徴的な秩序によって引き起こされる差異に依存するからである。そして、そのように言語は経験および/または心の中での意味の探索のため、‘監視され’、隠される。物の世界と主観が真理の二人の保証人となる(Belsey 1980, 46)。
ハムレットは言っている:演劇の目的は昔も今も、‘自然に向かって鏡をかかげ’、善は善なるままに、悪は悪なるままにその真の姿を抉り出し、時代の真相を浮かび上がらせる(シェイクスピア、ハムレット,III, ii)、そして‘真実であること’が多分、今でも文学的価値を判定する主要な基準なのである。しかし、Belseyは次のようにコメントしている:
- 文学という形式が世界を反映しているという主張は、単に同義反復(トートロジー)に過ぎない。もし‘世界’という概念で、我々が経験する世界つまり言語により区分された世界を理解するなら、実在主義は世界を反映すると言う主張は、実在主義は言語で構成された世界を反映しているということを意味する。これは同義反復である。もし言説が、記号と世界の実体との関係によるというよりも記号同士の関係によって意味する記号システムを通して概念を分節するなら、またもし文学が意味行為なら、それが反映できるものは、全て特定の言説に刻まれた秩序であり世界の本質ではない(同上)。
言語という媒体は、‘透明’という幻想を獲得するようになる:媒体のこの特徴は、経験的な世界を構築するにあたって、それが果たす役割から使用者の目をそらせる傾向にある。‘現実感のある’テクストは、表現の中に見せかけの目的を反映する −余りにそっくりに真似しようとするので、経験したことを仮想的に全く同じように(そして自然に)描くことになる。純粋に言葉での記号表現が、現実世界の指示物と間違われないのは明らかである。言葉を慣習的な象徴記号と認めるのは容易であるが、記号内容に似ているイメージの慣習性を認めるのはなかなか難しい。まさにイメージでさえ、それが表現する物ではない −イメージの存在は指示物の不在を印象付ける。記号表現と記号内容の差異は根本的なものである。それでも、記号表現が高度に‘現実感のあるものごと’として経験されると −写真や映画のように− 、記号表現と記号内容が同一であると認めることへたやすく滑り込んでいく。現実感のある絵画や線画と対照的に、写真は作られた(authored)という感じが少ない。‘言葉は物でない’また‘地図は領土でない’と同様、写真やテレビニュースはそれが描く現象ではない。ただ依然としてまた日常生活における‘常識的’な態度として、高度な様相をもつ記号表現をそれが表現するものと同じものとして扱っている。まさに、多くの現実味のある映画の物語や記録映画は、表現と実在の混同を招き入れるように思える (Nichols 1981, 21)。このようにして、テレビはしばしば、‘世界の窓’とされ、‘カメラは騙さない’と仮定される。もちろん、‘映画の中の犬は吠えないし、噛み付かない’ことは知っている(Hall 1980, 131) (しかし、映画に引き込まれると、それが演じられているドラマであると知っているという文脈で、‘疑うことを停止’するかもしれない)。しかし、出来事がジャーナリストのカメラにより介在されている時でさえ、我々は‘自分自身の目という証拠’を受け入れる傾向にある。どんな媒体でも、高度に‘現実的な’表現も常に視点を含んでいる。‘現実的である’と主張する表現は、地図と領土との避けられない差異を否定する。ルイス・キャロルは、この差異の重要性を無視することから生じる論理的な帰結をこう皮肉っている。
- ‘あなたの国から学んだ別のことは’とマイン・ヘルが言った、‘それは地図を作ることです。しかし我々は、あなたがたよりずっと詳細にそれを行いました。本当に役に立つもっとも大きい地図はなんだと考えますか?’
‘1マイルに対して6インチ’
‘たったの6インチ!’とメイン・ヘルは叫んだ。‘我々はすぐに1マイル6ヤードにしました。それから、1マイルに100ヤードを試しました。そして、もっとも申し分のない考えに達しました。実際、1マイルに1マイルの縮尺で国の地図を作成したのです’。
それを大いに利用しましたか?’と私は問いただした。
‘それはまだ広げられたことはありません’マイン・ヘルは言った:‘農夫が反対したのです:彼らは、それは国全部を覆ってしまい、日の光を遮ってしまう!と言いました。それなので、いまは国その物を地図のように利用しています。それは同じように役立っていると保証します。’
(ルイス・キャロル,シルヴィーとブルーノ 完結編,11章)
表現された物とその表現に間には、常に避けられない差異があるという意味では、‘カメラはいつも嘘をついている’。意味作用システムによる‘実在の歪み’に関して、我々は必ずしもいわゆる一般意味論者の‘科学的’実在論を採る必要はないが、そのかわり実在が記号に独立には存在しないことを認め、誰の実在が特定の表現において優先されるかという議論へ批判的に注意を向けても良いかもしれない −それは主観論に後退することを避け、社会的世界における権力の不均一な分布へ注意を向けるという視点である。
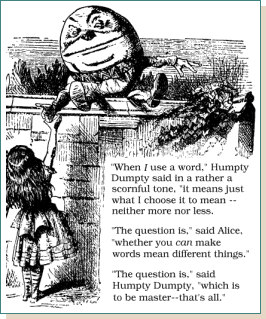 (言語をモデルとする)ソシュール派の記号学者は記号内容への記号表現の恣意的な関係を強調したが、後継者の何人かは‘記号表現の優位性’を強調している −ジャック・ラカンはルイス・キャロルのハンプティ・ダンプティが、‘おれがある言葉を使うと、おれが持たせたいと思う意味をぴったり表すのだ’と宣言したことから、‘記号表現の親方’と賞賛した。多くのポスト・モダン主義者は、記号表現と記号内容の完全な断絶を自明なこととした。‘空な’または‘浮遊している記号表現’は曖昧な、変わり易く、特定し難いまた不在の記号内容をもつ記号表現として種々定義されている。そのような記号表現は、いろいろな人々にとっていろいろなものを意味する:それらは、多くのまたはあらゆる記号内容さえ表すかもしれない;それらは、その解釈者がそれらに意味させたいと望むものをなんでもを意味する。記号表現と記号内容のそのような過激な断絶という状態では、‘記号は、それが意味するということだけを意味する’ (Goldman & Papson 1994, 50)。そのような断絶は文学や審美的なテクストでもっともはっきりし、表現の作用や形式を前面に出し、記号表現と指示物の間の‘中立的’または‘透明’な繋がりのあらゆる意味を侵食す。しかし、Jonathan Cullerは次のように示唆している。‘空の記号内容’を指示することは、暗黙のうちに記号表現としてのその状態を受け入れることであり、その記号内容が知られないとしても‘その記号表現と内容を相関させている’;‘記号表現のもっとも過激な役割も、また記号内容を据えることを必要とし、それを介して動作する’ (Culler 1985, 115)(Culler 1985,115)。よく知られているようにシェイクスピアは、‘大ばか者が怒りに駆られて大声で話したことなど、何も意味しない’と言っている(Macbeth V, iii)。‘浮遊する記号表現’という考えは、1950年ごろC・レヴィ=ストロースの中に見出される(Lechte 1994, 26-7, 64, 73を見よ)。特にロラン・バルトは、非言語的記号は解釈に任されており、‘記号内容の浮遊する連鎖’を構成すると言っている(Barthes 1977, 39)。‘空(くう)の記号表現’に関して最初に言及したのは、著者が知っている限りロラン・バルトのエッセイ‘現代の神話’の中である(Barthes 1957; Culler 1975, 19)を参照のこと)。バルトは空の記号表現を、記号内容を持たないものと定義した。‘空の部類’という言語の概念と類似点が多い(Lechte 1994, 64)。そしてイェルムスレウの形成素(figurae)や意味を持たない記号要素とも類似点がある(同上, 137; see 分節の章を見よ)
(言語をモデルとする)ソシュール派の記号学者は記号内容への記号表現の恣意的な関係を強調したが、後継者の何人かは‘記号表現の優位性’を強調している −ジャック・ラカンはルイス・キャロルのハンプティ・ダンプティが、‘おれがある言葉を使うと、おれが持たせたいと思う意味をぴったり表すのだ’と宣言したことから、‘記号表現の親方’と賞賛した。多くのポスト・モダン主義者は、記号表現と記号内容の完全な断絶を自明なこととした。‘空な’または‘浮遊している記号表現’は曖昧な、変わり易く、特定し難いまた不在の記号内容をもつ記号表現として種々定義されている。そのような記号表現は、いろいろな人々にとっていろいろなものを意味する:それらは、多くのまたはあらゆる記号内容さえ表すかもしれない;それらは、その解釈者がそれらに意味させたいと望むものをなんでもを意味する。記号表現と記号内容のそのような過激な断絶という状態では、‘記号は、それが意味するということだけを意味する’ (Goldman & Papson 1994, 50)。そのような断絶は文学や審美的なテクストでもっともはっきりし、表現の作用や形式を前面に出し、記号表現と指示物の間の‘中立的’または‘透明’な繋がりのあらゆる意味を侵食す。しかし、Jonathan Cullerは次のように示唆している。‘空の記号内容’を指示することは、暗黙のうちに記号表現としてのその状態を受け入れることであり、その記号内容が知られないとしても‘その記号表現と内容を相関させている’;‘記号表現のもっとも過激な役割も、また記号内容を据えることを必要とし、それを介して動作する’ (Culler 1985, 115)(Culler 1985,115)。よく知られているようにシェイクスピアは、‘大ばか者が怒りに駆られて大声で話したことなど、何も意味しない’と言っている(Macbeth V, iii)。‘浮遊する記号表現’という考えは、1950年ごろC・レヴィ=ストロースの中に見出される(Lechte 1994, 26-7, 64, 73を見よ)。特にロラン・バルトは、非言語的記号は解釈に任されており、‘記号内容の浮遊する連鎖’を構成すると言っている(Barthes 1977, 39)。‘空(くう)の記号表現’に関して最初に言及したのは、著者が知っている限りロラン・バルトのエッセイ‘現代の神話’の中である(Barthes 1957; Culler 1975, 19)を参照のこと)。バルトは空の記号表現を、記号内容を持たないものと定義した。‘空の部類’という言語の概念と類似点が多い(Lechte 1994, 64)。そしてイェルムスレウの形成素(figurae)や意味を持たない記号要素とも類似点がある(同上, 137; see 分節の章を見よ)
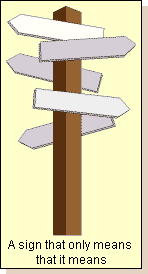 ソシュールは、記号表現と記号内容を用紙の両面のように分離できないと見ていたが(しかし、その関係は恣意的である)、ポスト構造主義者は、ソシュールのモデルに組み込まれている安定しまた予測可能な関係を拒否している。フランスの心理分析者ジャック・ラカンは、‘記号内容の記号表現の下への絶え間ない滑り込み’について書いている(Lacan 1977, 154) −特定の記号表現を、特定の記号内容に繋ぎ止めるものはないと彼は主張した− これは心理分析という文脈ではあまり異論がない。ジャック・デリダは、記号表現の‘戯れ’について言及している:記号表現は記号内容に固定されず、それ自身を越えて‘記号表現の記号内容への不確かな参照’において他の記号表現を指し示す (Derrida 1978, 25)。究極的には決定可能な意味があるということを彼は否定して、西欧の記号システムの‘脱構築’のチャンピオンとなった。ソシュールにとって記号の意味は記号同士が互いにどのように異なるかから引き出されるものであったが、デリダは意味が無限に引き延ばされることに言及するため、差延という用語を作り出した。‘卓越した記号内容’はない(Derrida 1978, 278-280; Derrida 1976, 20)。これらの考えは、パースの‘無限の記号過程’の中で論じられている、しかしパースは、実際にはこの潜在的に無限のプロセスは日常生活の実際上の制約によって打ち切られる、と強調している(Gallie 1952, 126)。パースと異なり、ポスト・モダン主義者は記号作用の外部のどんな実在への接近もないことを認めている。デリダにとっては‘テクストの外部には何もない’のである −この言明は必ずしも‘文字通り’にとる必要はないが(Derrida 1976, 158, 163)。唯物主義のマルクス主義者や実在主義者にとっては、ポスト・モダン主義者の観念論は許容できるものではない:‘一つの記号がもう一つの記号を指し示し、その環は記号が指示するものの進入によって破られることがない、意味作用という終りのない連鎖の中に指示物を飲み込むことは記号には許されていない。’ (Lovell 1983, 16)。何人かの研究者は、記号作用の不可避性を強調することは、外部の実在を否定することを必要としていない、と記している。David Slessは次のようにコメントしている。‘宇宙の物はただ記号またはテクストであるとか、記号なしではなにも存在しないとは言わない。しかし、記号がなくてはなにごとも認識できない、と主張する’(Sless 1986, 156)。ついでに、‘空(または浮遊する)記号表現’という句は、学術的な‘見出し(sound-bite)’となっており、その用語自体が皮肉なことに空の記号表現になる危険性がある。
ソシュールは、記号表現と記号内容を用紙の両面のように分離できないと見ていたが(しかし、その関係は恣意的である)、ポスト構造主義者は、ソシュールのモデルに組み込まれている安定しまた予測可能な関係を拒否している。フランスの心理分析者ジャック・ラカンは、‘記号内容の記号表現の下への絶え間ない滑り込み’について書いている(Lacan 1977, 154) −特定の記号表現を、特定の記号内容に繋ぎ止めるものはないと彼は主張した− これは心理分析という文脈ではあまり異論がない。ジャック・デリダは、記号表現の‘戯れ’について言及している:記号表現は記号内容に固定されず、それ自身を越えて‘記号表現の記号内容への不確かな参照’において他の記号表現を指し示す (Derrida 1978, 25)。究極的には決定可能な意味があるということを彼は否定して、西欧の記号システムの‘脱構築’のチャンピオンとなった。ソシュールにとって記号の意味は記号同士が互いにどのように異なるかから引き出されるものであったが、デリダは意味が無限に引き延ばされることに言及するため、差延という用語を作り出した。‘卓越した記号内容’はない(Derrida 1978, 278-280; Derrida 1976, 20)。これらの考えは、パースの‘無限の記号過程’の中で論じられている、しかしパースは、実際にはこの潜在的に無限のプロセスは日常生活の実際上の制約によって打ち切られる、と強調している(Gallie 1952, 126)。パースと異なり、ポスト・モダン主義者は記号作用の外部のどんな実在への接近もないことを認めている。デリダにとっては‘テクストの外部には何もない’のである −この言明は必ずしも‘文字通り’にとる必要はないが(Derrida 1976, 158, 163)。唯物主義のマルクス主義者や実在主義者にとっては、ポスト・モダン主義者の観念論は許容できるものではない:‘一つの記号がもう一つの記号を指し示し、その環は記号が指示するものの進入によって破られることがない、意味作用という終りのない連鎖の中に指示物を飲み込むことは記号には許されていない。’ (Lovell 1983, 16)。何人かの研究者は、記号作用の不可避性を強調することは、外部の実在を否定することを必要としていない、と記している。David Slessは次のようにコメントしている。‘宇宙の物はただ記号またはテクストであるとか、記号なしではなにも存在しないとは言わない。しかし、記号がなくてはなにごとも認識できない、と主張する’(Sless 1986, 156)。ついでに、‘空(または浮遊する)記号表現’という句は、学術的な‘見出し(sound-bite)’となっており、その用語自体が皮肉なことに空の記号表現になる危険性がある。
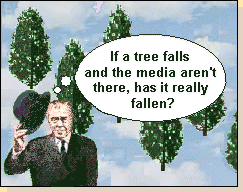
実在は堕落するという考えは、(言語を習得する前の子供やアダムとイブの堕落以前の人間を示す)無垢な状態に関するローマン主義の神話の中に見出される(Chandler 1995, 31-2)。Daniel Boorstinは彼のThe Imageという本で‘擬似的な出来事’と呼ぶもの −マス・メディアが報告するように目論まれたもの− の増加を図示している(Boorstin 1961)。しかし、すべての‘出来事’は社会的な構築物であり、取り上げられた‘出来事’は客観的な存在を持たず、全てのニュースは‘物語’である(Galtung & Ruge 1981)。
表現上の範例における三つの主要な歴史的な変化を、記号の指示の状態の区分に関するパースの枠組みと関連して位置付けられるかもしれない:
そのような図式は、ポスト・モダン主義者ジーン・ボードリアールのそれと類似点がある。ボードリアールは、多く表現は実在の不在を隠す手段であると解釈している;彼はそのような表現を‘シミュラークル’(または原作のない複製)と呼んでいる(Baudrillard 1984)(Baudriallard 1984)。記号が次第に意味のないものとなる表現の様式を、彼は堕落的な進化と見ている:
-
これらは、形象の連続する相である:
ボードリアールは、次のように主張している。談話と書物が生成されるとき、記号は物質的または社会的実在を指すため考案されるが、記号内容と記号表現の間の結合力は腐食される。広告、宣伝、商品化が定着するにつれ、記号は‘基本的な実在’を隠すようになる。コミュニケーションの媒体においては、幻想だけが本物らしく見える。つまり‘過度の現実(hyper-reality)’のポストモダン時代には、記号は実在の不在を隠しなにか意味しているように欺く。ボードリアールにとって、シミュラークル(simulacra) −最近の資本主義を特徴付ける記号− は三つの形式でやってくる:見せかけ(模造) −記号表現と記号内容にまだ直接的な関係があるとき;生産(幻想) −記号表現と記号内容にまだ間接的な関係があるとき;そしてシミュレーション(作り事) −記号表現は他の記号表現との関係で成立し、固定された外部の実在と関係をもたないとき。Douglas Kellnerがボードリアールを、記号生産における物質性を無視する‘記号論的観念主義者’と呼んだのは驚くにあたらない(Stam 2000, 306に述べられている)。ボードリアールの、湾岸戦争は起らなかったという主張は確かに挑発的である(Baudrillard 1995)。
もちろんそのような観点は、次のような根本的な疑問、‘“実在”とはなにか’には答えていない。‘実在’を問題視し、介在や慣習を強調する記号論的立場は時によっては、実在主義に向いた人々によって極端な‘文化的相対主義’として批判されている −それらの批判は、‘正確さ’のような指示に関する問題をあからさまに脇に寄せてしまうことに反対している(例えばGombrich 1982, 188, 279, 286))。しかし哲学的な実在主義者でさえ、世界に関する知識の多くは間接的であることを受け入れている;多くのものが、主として(または全く)メディアやコミュニケーション技術の範囲内で我々に表現されていることを、我々は経験している。表現は、それが表すものの全くの複製ではあり得ないので、それらは中性また透明でなく、その代わり実在を構成する。Judith Butlerが言っているように、我々は‘本来透明なもの、をなにが不明瞭にしているのだろう?’と聞かなければならないだろう(Butler 1999, xix)(Butler 1999)。記号論は、表現は‘実在の反映’として認知されたものであると考えるのではなく、実在と表現を分離し、それらは誰の実在を表現しているのだろうと考えられるようにする。


