Semiotics for Beginners
Daniel Chandler (University of Wales)
分節(articulation)
記号論的コードにおける構造や‘分節’の複雑さは一様でない。分節(articulation)という用語は、A.マルチネス派の構造主義的言語学から導かれ、記号論者は‘コードの構造’を指すものとして、使っている。その用語の日常的な使い方は、どのくらい‘はっきりものをいうことができる(articulate)’かということを指すので、ともすれば、誤解されやすい。このように混乱する可能性があるので、言語学の理論家は、構造的な意味での分節という用語を使うことを放棄し、‘パターンニングの二重性’という用語を好むが、記号論者は分節という用語を使い続けている。その記号論的使用法は、むしろ、貨物自動車(トラック)は‘分解(articulate)’できるという感覚に近いものである -つまり、それは結ばれているが、分解もできる部分からなっている。ピエール・ギローは、記号論的分節に関して、次のようにコメントしている:
言語モデルに従えば、分節されるコードは、基本単位の‘語彙’と、より大きな意味をもつ組合せを生成するために使われる統語的規則を持つ(Innis 1986, 88-9, 99-102)。(言語のように)‘二重分節’をもつ記号論的コードは、二つの抽象的構造レベルに分解される:高レベルは‘第1分節レベル’、低レベルは‘第2分節レベル’と呼ばれる (Noth1990; Eco 1976, 231ff)。交通標識は2重分節はしないが、分節しないわけではない。そのような場合、通常、第1分節のみ有すると言われる。
第1分節のレベルでは、そのシステムは、使うことが出来る最小単位で構成されている(例えば、言語での形態素や単語がこれにあたる)。言語では、このレベルの分節は、文法レベルと呼ばれる。このレベルの意味を持つ単位は完全な記号であり、それぞれ記号表現と記号内容より成る。コードが、繰り返し出てくる意味のある単位(例えば、オリンピックのスポーツ絵文字や布地の取り扱い注意シンボル)を有する場合、それは第1分節を有する。2重分節を有するシステムでは、これらの記号は、分節のより低い(第2の)レベルからの要素で作りあげられる。
第2分節のレベルでは、記号論的コードは、それ自身では意味を持たない最小の機能単位(例えば、話し言葉における音素、書き物における書記素)に分割される。これらの純粋に区分できる構造単位(イウエルムスレフはこれを形成素(figurae)と呼んだ)は、コードの繰り返し出てくる特徴である。それらは、それ自身、記号ではない(コードが、これらの低位の単位を組み合わせて、意味のある記号になるためには、第1分節を持たねばならない)。両者を有するコード(‘二重分節’システム)では、低レベルの単位の機能は、純粋に最小の意味のある単位を区別することにある。言語では、音素/b/、/p/、/t/は第2分節の要素であり、その機能は/pin/、/bin/、/tin/のような、第1分節の要素である単語を区別することである。このように、言語では、第2分節は音韻論的(phonological)レベルである。
記号論的コードは、単分節、二重分節または分節なしのいずれかである。二重分節は、記号論的コードが、少数の低レベルの単位を用いて、意味を持つ組合せを際限なく形成することを可能とする(それは経済性と能力を提示する)。有限の要素を無限に使うことは、一般に媒体に関連して、‘記号論的経済性’と呼ばれている特徴である。伝統的定義では、二重分節は人間の言語のみとしており、そのため、これは主要な‘設計要因’であると認められている(Hockett 1958; Hockett 1960; Hockett 1965)。ルイス・イエルムスレウは、それを言語の原理的かつ決定的特徴だと認めている (Hjelmslev 1961)。言語の創造的経済性は、二重分節によるところが大きいと見られている。言語は、高度に経済的な記号システムである -少数の記号のみ用いているだけである。言語の他の長所と較べても、言語の経済性は、学習と再現を容易にしている。創造性に関しては、言語は無限に生産的である。例えば、40または50の第2分節の要素(音素)しか有していないが、それで数十万の単語を生み出すことができる。同様に、限られた語彙から、無数の文を生成できる(語の組合せを構造的に有効なものにする文法の制約を受けるが)。結論的には、ノーム・チョムスキーが言っているように、言語の創造的経済性は、我々が出会ったこともないような文章を、際限なく生成する力を与える。経験の詳細を全て表現しようと企てることが出来るのは、多様な方法で単語を組合せられることによる。全ての詳細を表現するのに、個々の言葉を用いるとなると、膨大な量の言葉が必要となり、学習したり、思い出したり、操作したりする我々の能力を越えてしまう。John Lyonsは、次のようにコメントしている。‘二重性は、言語において、それが作用する時、それはまた恣意性とも結び付く。もし、ある形式での音韻的要素がそれぞれ、慣例的であれまたは自然的なものであれ、その意味のある側面と、類像的関連があるならば、音韻的要素をもう一つの音韻的要素と組合わせるのが非常に難しくなるのは、明らかである’(Lyons 1977, 74)。ローマン・ヤコブソンは、次のように見ていた
ヤコブソンが言っているように、文章のレベルを越えてでさえ、単語をつかう方法は、我々に開かれている可能性を制限する言語の慣習に従う。その規範から、あまり離れると、コミュニケーションに失敗するだろう。
2重分節は、人間以外の動物の間での自然のコミュニケーションでは生じないように思われる。人間の2重分節を有する記号システムは、他に、図書館や問屋のカタログで使われているシステム的コードや‘データ処理における多くのコード’に見られる、とNothが言っている。彼は、次のようにも加えている。‘建築、写真、映画、記号言語や物語のようないろいろなコードの構造について、多くの議論がなされてきたが、これらのコードの分節については、納得できる結論には達していない’ (e-mail 12/8/97)。スザンヌ・ランガーは、次のように主張している。写真や絵画といった視覚的媒体は、‘抽象的で組合わせることができ’かつ‘言葉のように、分節つまり複雑な組合せ’が可能な線、色、陰影、形状、大きさ等々を有するが、それらは、独立した意味を持つ単位の語彙を有していない(Langer 1951, 86-7)。
しかし、ランガーは‘非推論的’媒体を、その限界の故に、遠ざけるのではなく、次のように主張している。それらは、話しことばより、複雑で巧妙であり、‘観念の表現に適した独特なものであり、言語的な“観念の具体化”に挑戦するものである’、と主張している。彼女は、次のようにも主張している。他の媒体の分節を支配する法則は‘言語を支配する構文法則とまったく異なる’ので、言語モデルを他の媒体に押し付けるべきでない。それらを言語的用語で扱うことは、それらを‘誤解する(misconceive)’ことになる:それらは‘翻訳’に抵抗する(ibid., 86-9)。
2重分節を持たない記号論的コードには、第2分節のみ有するものもある。これらは、特定の意味を持つ記号から構成されているが、その意味はそれらの要素からは導出されない。それらは、(最小の機能単位である)形成素にのみ分割される。Nothは、‘第2分節のみ有するもっとも強力なコードは情報理論の2進コードである’と示唆している(e-mail, 12/8/97):これは0と1の二つの機能単位しか持っていないが、その単位を組合わせると、数字、文字や他の単位を生成することができる。第2分節のみ有するコードのうち、もう少し強力さに欠けるのが、本の索引コードであり、単純に一連番号である。
話し言葉には2つ以上の分節がある、と言っている研究者もいるが、ギローは、次のように主張している:
ウンベルト・エーコは劇映画は3重分節を有していると主張している:類像的表象(iconic figures);セメ(semes)(類像的表象の組合せ);そしてキネモルフ(kinemorphs)(セメの組合せ)(Stam 2000, 114)。
要するに、分節という考えは、記号システムを基本レベルに分割する方法である:話し言葉の場合、レベルは音と意味のレベルと言うことができる。これは、明らかに、記号を‘音声-イメージ’(記号表現)と概念(記号内容)に分けるソシュール流の分析と関連付けられる。2重分節のある記号システムでは、記号表現と記号内容のレベルは、相対的に独立している。
表示義、共示義そして神話 は、記号論的には、レベル(イエルムスレウとバルトの‘意味作用の順位’)という用語で記述できる。もっと一般的に言えば、ソシュールは、記号はそれ自身、記号を含むことができると述べている。例えば、twenty-nineという複合記号は、‘単純記号’であるtwentyとnineから構成されている(Saussure 1983, 130; Saussure 1974, 131)。規模を広げて考えれば、テクスト全体が、複数の他の記号から構成されている記号である(Saussure 1983, 127; Saussure 1974, 128)。
モデリングシステムの概念は、記号システムの分節のレベルという考えに関連付けられる。というのは、‘第2次モデリングシステム’は、‘第1次モデリングシステム’の上に構築された上部構造物として記述されるからである。 ユーリ・ロットマンに続く何人かの研究者は、これらの用語で言語を解釈している。この枠組では、書くことは第2次モデリングシステムであり、書かれたテクストは、話し言葉で構成される第1次モデリングシステムの上に構築されている。第2次モデリングシステムは、あたかもそれらが記号の記号、または表現の表現を構成しているように提示される (Culler 1985, 122)。ソシュールはこの立場を採り、‘言語とその書かれた形式は、二つの別々の記号システムを構成しているが、後者の存在する唯一の理由は、前者を表現することにある’と言っている(Saussure 1983, 24; Saussure 1974, 23)。この立場は、話し言葉の優位性を認めるものなので、(特にジャック・デリダによって)音声中心主義(phonocentric)であると、批判されている(Derrida 1976)。もし、認識さえエンコーディングを含むものだ、と認めるなら、話すことさえ、他の記号-システムと同様、‘2次的’である。マーシャル・マクルーハンは、彼自身は音声中心主義者であるが、書かれた言葉の力を強調し、その基礎が、両者の構造的レベルでの恣意性にあることに言及している:‘意味を持たない音声に結び付けられた、[書かれた文字]という意味を持たない記号が、西欧人の形状と意味を作ってきた’(McLuhan 1962, 50)。他の研究者は、モデリングの概念を、他の媒体の‘テクスト’に拡張し、それらを第1次の‘言語’によって構築された第2次のモデリングシステムであると見ている。文学のテクストは、第1次の言語システムの上にまたは書かれた言葉というモデリングシステムの上に、構築された第2次のモデリングシステムと考えられるSilverman 1983, 27; Sturrock 1986, 103)。劇映画は、時折、‘画像の言語(graphic language)’という第1次のモデリングシステムの上に構築されている、と考えられてきた(Altman 1999, 175)。しかし、画像の‘言語’が基本的な成分(building blocks)を持つのか、それが何であるのかについては激しく議論されている。

メッセージが、もしそれ自身意味を持つのある要素に分解できれば、分節されるという。全ての記号論的要素は、意味がなければならない。このように、交通標識のトラックは、車輪、シャーシー、キャビン他に分解できるが、これらの部品の存在が記号を修正することにはならない。反面、上着を着ていないことやその代わりジャージーを着ることは、その人の装い方の意味を変える。(Guiraud 1975, 32)
言語単位の組合せで、自由度は大きくなる。音素ごとに独自の意味を付け、それを組合わせるのでは、個々の話し手の自由度は零となる:コードは、その言語で使える可能性を、全て確定してしまう。音素を組合わせて、単語を作る自由度は制限されている:それは、造語という辺境に限られる。言葉を用いて、文章を作る場合は、話し手の制約はより少なくなる。最終的に、文章を組み合わせて発言する時には、強制的な構文規則の作用は消え、新規の文脈を生む個々の話し手の自由度は、本質的に増していくが、‥‥多くの紋切り型の発言も、見過ごされるべきでない。(Jakobson & Halle 1956, 74)
余りに多くの要素がある記号体系(symbolism)、つまり無数の関係は基本単位に分解できない。最小の記号を見出すことや、同じ単位に他の文脈で出会ったとき、その同一性を認識する‥‥のは不可能である。勿論、対象を絵にする技術はあるが、その技術を支配する規則は、厳密には‘統語法’とは呼べない。というのは、隠喩的にも、肖像画の‘単語’と呼べる特徴はないからである。 (ibid., 88).
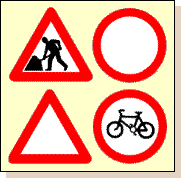 *第1分節しか持たないコードもある。これらの記号システムは、 -システム的に互いに関係付けられかつ意味をもつ要素である- 記号で構成されるが、これらの記号を、最小の意味のない文節へ構造化する第2分節はない。コードにおける、最小の循環的構造単位が意味を持つ場合、そのコードは第1分節のみを持つ。多くの記号学者は、非言語的コミュニケーションや動物のコミュニケーションという種々のシステムには第1分節しかない、と主張している。Nothは、鳥の仲間を呼ぶ声は基本的単位を使うが、それらは一つ一つ、完全なメッセージであるので、鳥の鳴き声には第1分節しかない、と言っている(Noth 1990, 151)。他の例としては、ホテルや事務所の部屋番号がある。最初の一桁はフロアを、二番目はそのフロアの部屋に付けられた一連の番号を示す。一群の交通標識(赤い境界線、△または○の形、標準化され様式化されたイメージ)も、第1分節しかないコードである (Eco 1976, 232)。(クリスチャン・メッツなど)何人かの記号学者は、対象と関連付けられた(motivated)記号を基にした -テレビや映画のような- コードは、第2分節が欠けている、と主張している。メッツは、映画では‘記号表現を、記号内容と同形の切片を得ることなしに分割することは不可能である(記号表現は記号内容と1対1対応しており、記号表現のみを分解できない)’、と宣言している(cited in Noth 1990, 469)。
*第1分節しか持たないコードもある。これらの記号システムは、 -システム的に互いに関係付けられかつ意味をもつ要素である- 記号で構成されるが、これらの記号を、最小の意味のない文節へ構造化する第2分節はない。コードにおける、最小の循環的構造単位が意味を持つ場合、そのコードは第1分節のみを持つ。多くの記号学者は、非言語的コミュニケーションや動物のコミュニケーションという種々のシステムには第1分節しかない、と主張している。Nothは、鳥の仲間を呼ぶ声は基本的単位を使うが、それらは一つ一つ、完全なメッセージであるので、鳥の鳴き声には第1分節しかない、と言っている(Noth 1990, 151)。他の例としては、ホテルや事務所の部屋番号がある。最初の一桁はフロアを、二番目はそのフロアの部屋に付けられた一連の番号を示す。一群の交通標識(赤い境界線、△または○の形、標準化され様式化されたイメージ)も、第1分節しかないコードである (Eco 1976, 232)。(クリスチャン・メッツなど)何人かの記号学者は、対象と関連付けられた(motivated)記号を基にした -テレビや映画のような- コードは、第2分節が欠けている、と主張している。メッツは、映画では‘記号表現を、記号内容と同形の切片を得ることなしに分割することは不可能である(記号表現は記号内容と1対1対応しており、記号表現のみを分解できない)’、と宣言している(cited in Noth 1990, 469)。
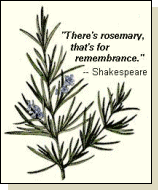
分節を持たないコードは、相互に関連を持たない一連の記号から構成される。これらの記号は、反復して出てくる構成要素に分解できない。民間伝承の‘花言葉’は、それぞれのタイプが、そのコードの他の記号と何ら関連を持たない、互いに独立した記号であり、分節を持たないコードである。分節しないコードは、反復するという特徴を持たないので、‘非経済的’である。
2つの分節は、構文的なレベルでの用語で考えるべきでない。第1分節にも、幾つかのレベルがある:文章、陳述、句(syntagm)、単語、形態素;しかし、これらの複合的な記号も、それぞれのレベルで抽出できる意味の要素を搬送する、基本的記号の連続した組合せである。 (Guiraud 1975, 32)