- テクスト間相互関連性(intertextuality):引用、盗用、言及;
- テクスト副次性(paratextuality):テクストとその‘副次的テクスト’との関係 −それはテクストの主要部分を囲むものである− 例えば、題目、見出し、前書き、題詞、献詞、謝辞、脚注、説明、本カバー等がこれにあたる;
- テクスト指示性(architextuality):ある範疇または複数の範疇の役割としてのテクストの指示(Genetteはテクストそれ自身による指示を言っているが、これは読者による枠取りにも適用できるかもしれない);
- 超テクスト性(metatextuality):あるテクストに対する、他のテクストに基づく明示的または非明示的な批判的論評(超テクスト性は、次の種類と区分が難しいかもしれない);
- ハイポ・テクスト性(hypotextuality)(Genetteの用語はハイパー・テクスト性(hypertextuality)であった):テクストと先行するの‘ハイポ・テクストとのの関係 ’−基礎となるが、変換、修正、推敲または拡張したテクストまたは範疇(それは、パロディー、ごまかし、続編、翻訳を含む)。
- 反射性(reflexivity):テクスト間相互関連性の使用が、如何に再帰的(または、自己意識的)であるか(もし反射性が、テクスト間相互関連であるということが意味することにとって重要ならば、多分、見分けが付かない複製は、テクスト間相互関連であるということを飛び越えてしまうだろう);
- 交替(alteration):出典の交替(より顕著な交替は、多分それをより反射的にテクスト間相互関連を強めるだろう);
- 明示性(explicitness):(例えば、直接的な引用、それに依拠している引用のように)他のテクストを参照していることを詳しくまたはっきりと示す(認識を仮定することは、より反射的にテクスト間相互関連的になるのだろうか);
- 理解への臨界性(criticality to comprehension):読者がそこに含まれているテクスト間相互関連性を認識することがいかに重要であるか;
- 採用の度合い(scale of adoption):テクストの中での、言及/統合の全体的な度合い;そして
- 構造的な限界のなさ(structural unboundedness):より大きな構造の部分として、どの範囲までテクストは提示(または、理解)されているか、または大きな構造に結び付けれているか(例えば、ある分野の、系列の、続き物の、一つの雑誌の、一つの展示の部分として) −それらの要因は、しばしば、そのテクストの著者の管理下にはない。
Semiotics for Beginners
Daniel Chandler (University of Wales)
テクスト間相互関連性(Intertextuality) ソシュールは、記号同士の関係が重要であることを強調しているが、構造主義的記号論の欠点の一つは、それぞれのテクストを離散的かつ孤立した実体として扱い、また内部構造にばかり注目する傾向があることである。複数のテクストが一つの‘集成'(一体となった集合)として研究される場合でさえ、全体的な包括的構造は、それ自身、厳密に区切られているものとして扱われる傾向にある。構造主義では、最初に行うべき分析的な作業は、システムの境界(含まれることと排除されること)を定めることであると記述されている。これは論理的には理解できるが存在論的には問題がある。構造主義的パラダイムに留まるにせよ、コードは構造に優先するということは述べておいた方が良いだろう。ジュリア・クリステヴァによって導入されたテクスト間相互関連性 、という記号論的概念は、主にポスト構造主義の研究者と結び付いている。クリステヴァは、テクストを二つの軸で見ていた;一つは水平軸であり、それはテクストの作者と読者を結び付ける、もう一つは垂直軸であり、テクストを他のテクストと結び付ける(Kristeva 1980, 69)。この2軸を結合するのが、共有されたコードである:テクストとそれを読むことは、全てそれ以前に存在するコードに依存する。クリステヴァは、‘全てのテクストは、最初から、他の談話の管轄下にあり、それはそのテクストに話相宇宙をもたらす'と宣言している (Culler 1981, 105)。彼女は、テクストの構造だけに注目するのではなく、‘構造化(strucration)'(どのように、構造が生じたのか)を研究すべきである、と主張している。これは、テクストを‘以前または現時点のテクスト全体の中に'置くことになり、テクストはある‘変形となる' (Le texte du roman, cited by Coward & Ellis 1977, 52)。
テクスト間相互関連性は、著者相互の‘影響’以上のものを指している。構造主義者にとっては、言語は、個人が制御できないだけでなく、主体性を決める力を有している。構造主義者は、彼らが文学の中に深く根ざす偏見と見ているものや、テクスト及び著者の独自性を強調する美学的思想に反対してきた(Sturrock 1986, 87)。個人主義(それは、著者の‘独自性’、‘創造性’、‘表現性’と関連している)という思想は、ポスト・ルネッサンスの遺産であり、ロマン主義時代に頂点に達し、いまだ大衆的な談話を支配している。‘原作者(authorship)'は歴史的は発明である。‘原作者'や‘盗作(plagiarism)’などの概念は、中世には存在しなかった。‘1500年ごろまでは、読んだり、引用している本の著者が誰かを正確に突き止めることに、今のように重要性を置いていなかった’(Goldschmidt 1943, 88)。ソシュールは、言語は個々の話し手に先行して存在するシステムである、と強調している。構造主義者とポスト構造主義者にとっては、我々は皆、(月並みなアルチュセール流の公式に従えば)‘常に、既に’記号システム −もっとはっきり言えば、言語− により位置付けられている。現在の研究者は、主体を、言語によって話されるものとして見ている。バルトは、次のように宣言している。‘話すのは言語であり、著者ではない;書くことは‥‥言語のみが作用し、“実行する”地点に辿りつくことであり、“私に”ではない’(Barthes 1977, 143)。書き手が書いているとき、彼らはまた書かれているのである。コミュニケーションするためには、今ある概念と慣例を利用しなければならない。 結局、コミュニケーションしようという意図と何を伝えようとするかは、個人としての我々にとって、両方とも重要であるが、意味は著者の‘意図’に帰することはできない。著者の意図という用語で意味を定義することは、文学批評における‘新批評(New Critical)’傾向のW K WimsattとM C Beardsleyによって確認された、いわゆる‘意図的な誤り(intentional fallacy)’である(Wimsatt & Beardsley 1954)。例えば、我々は、そうしていると意識せず、物事を伝えているかもしれない。ミカエル・モンターニュが1580年に書いているように、‘作品は、それ自身の力と運で作者を支援し、時には、彼の意思や知識を越え、彼をはるか後方に、置き去りにしてしまうかもしれない’ (Essays, trans. Charles Cotton: 'Of the art of conferring' III, 8)。さらに、我々の媒体の慣例に順応するうちに、その慣例を永続させるために、我々自身、媒体として、行動してしまうようになる。
テクスト間相互関連性の研究者は、‘原作者’という地位を問題にし、テクストを書いた人を、テクストの創作者としてより、ロラン・バルトが‘既に書かれたもの’として指していたものの編集者として扱う(Barthes 1974, 21)。‘テクストというのは‥‥色々な書物が −そのどれもが独創的でない− 、混ざり合い、衝突する多次元空間である。テクストは、引用を織り交ぜたものである‥‥。作家は、常に先在物があり、決して独創的でないしぐさを模倣するだけである。彼の唯一の力は、書物を混ぜ、その内のどれにも寄りかからず、それらと他のものを対峙させることである’ (Barthes 1977, 146)。バルトは、彼の本S/Zの中で、バルザックの短編サラジーヌ(Sarrasine)を脱構築し、テクストを‘脱創作(de-originate)’しようとした −つまり、バルザックだけでなく、多くの声を反映していることを示そうとした (Barthes 1974)。我々は、言語に先行しているのではなく、それにより生成されているのであり、バルザックが言葉で‘自分自身を表現している’と考えるのは、極端な理想主義であろう。バルトにとって、書くことはあらかじめ形成されている思想や感覚を記録する道具的過程(それは記号内容から記号表現へと作用する)でなく、記号表現とともに作用し、記号内容にそれ自身の面倒を見させる事柄であった(Chandler 1995, 60ff)。C・レヴィ=ストロースは次のように宣言している:‘私は自分の本を書くという感覚を持ったことがなく、本が私を通して書かせる‥‥という感覚を持っている。私は、個人的なアイデンティティを感じるという認識を持ったことがないし、今でも持っていない。自分自身にとって、私は何かが通り過ぎていく場所のように思えるが、“私が”や“私に”があるのではない’ (cited in Wiseman & Groves 2000, 173)。
記号論の基本的テクストの一つ、一般言語学講義、それ自体が原作者の立場を疑問視させる。パリのPayotから出版されたそのテクストは、著者はフェルデナン・ド・ソシュールであったが、それはソシュールが書いたものでない。ソシュールは、一般言語学や彼が記号学と呼んだものに関する詳細な見取り図は何も残さず、1913年に亡くなった。講義は、彼の死後、1916年に最初に出版されたが、それは、シャルル・バイイとアルバール・セシュが(‘アルバール・ライリンガーの協力を得て’)、少なくとも7人の学生のよって取られたノートとソシュール自身によって書かれた幾つかの個人的なノートを基に、編集したものである。学生達のノートは、ソシュールがジュネーブ大学で1906-1911年に教えた、一般言語学に関する3つの別々の講義のものである。ソシュールは、このように、彼の名前が付けられた本を書かなかったし、読まなかったが、我々は、彼の名前をそれに付けることにより、彼がそれをしたのだということをほのめかしている。色々な矛盾、整合性のなさ、一貫性の欠如が目立つのは、驚くにあたらない。事実、何人かの評者は、講義は、ソシュールの考えを‘忠実に反映’したものではない、と示唆している −問題がないとは言えない考えである(Saussure 1983, xii)。これに加えて、英国の読者には、講義の翻訳が二つあり、それぞれ競っている(Saussure 1974; Saussure 1983)。勿論、それぞれの翻訳は、再著作である。 −講義に記されているように− 言語はそれぞれ、異なる価値システムを持つので、‘中立的な’翻訳は不可能である。熟練した翻訳家が、まったく中正無私ということはあり得ない。まして、講義での記号学の扱いは、断片的なものであり、講義を記号論の基本的なテクストと見なす人は、実質的にそれを‘書き直す’ことにより、そうする。最終的には、このテクストと読者である我々を、翻訳者自身の理論に適応させているのだという注釈に事欠かない(例えば、Harris 1987; Thibault 1997)。
このちょっと極端であるが重要な例は、全ての読み物は、常に書き直したものであるということを浮かび上がらせるのに役立っている。それは、決してそれだけの例で終わってはいない。講義でその概要が示されている概念に対する最初の批判は、1929年に、Valentin Voloshinovの名前で、出版されたマルクス主義と言語哲学であった。しかし、その後、この本は、実際は、ミハエル・バフチンが書いたものだと反論され、このテクスの原作者は誰かが論争されている(Morris 1994, 1)。どの場合でも、読者が著者を構築する。読者は、1種のアマチュア考古学者となり、テクストの破片からテクストを再構成し、 一方、同時に、読んだ書物の著者について、‘彼女(または彼)を知っている’という感覚を持つようになる。(例えば)読者の‘ロラン・バルト’は決して、存在しない。もし、人がバルトが書いたもの全てを読んだら、矛盾だらけということが印象付けられるだろう。そのような矛盾を減らすのに役立つもっとも良いことは、‘若い時のバルト’、‘後年のバルト’というように、もっと作者を増やすことである。バルトは、1981年に没したが、彼の名前を唱えることが、もう一人のバルトを作り出していく。
テクスト間相互関連性という概念は、テクストそれぞれは、他のものとの関連で存在するということを、我々に思い起こさせる。事実、テクストはそれ自身の作者より、他のテクストに依るところが大きい。ミシェル・フーコーは次のように宣言している:
テクストは、色々な方法で、他のものにより枠組みされる。もっともはっきりしているのは、形式の枠組である:例えば、テレビ番組は、シリーズものの部分か、(メロドラマやホーム・コメディ(sitcom)のような)ある分野(genre)の部分かもしれない。個々のテクストを理解するということは、どんな場合でも、そのような枠組みと関係している。テクストは、その中で他のテクストが創造されまた解釈されるような文脈を、予め用意している。美術史家Ernst Gombrichはもっと先へ行き、‘自然主義的’な全ての美術は、世界の反映というより‘語彙の操作’だ、と主張している (Gombrich 1982, 70, 78, 100)。テクストは、 −テクスト的また社会的な− より広い文脈から、複数のコードを引き出す。あるテクストに範疇を割り当てることは、テクストを解釈する人に、テクスト間で相互に関連する主要な枠組みを供給することになる。範疇理論(Genre theory) は、それ自体重要な分野であり、範疇の研究者は必ずしも、記号論を採用しているわけでない。記号論では、範疇は記号システムかコードと考えることができる −それは、慣習化されているが動的である。範疇に関するそれぞれの例は、それをその範疇の他の成員と結び付けるという慣習を利用している。そのような慣習は、その範疇の‘からかい(spoof)’版でもっとも明白となる。しかし、テクスト間相互関連性は、範疇の境界の流動性や、'advertorials', 'infomercials', 'edutainment', 'docudrama' and 'faction' ('fact'と'fiction'の混ぜ合わせ)に見られるように、範疇とその機能がぼやけてきていることにも反映されている。
繋がりは、同じ話題を他の範疇で扱うことにより、公式的な枠組みの境界をも横切ってしまう(戦争というテーマは、冒険映画、ドキュメンタリー、ニュース、時事問題など、ある範囲の分野で見出される)。幾つかの範疇は、数種類の媒体で共有される:メロドラマ、ゲーム・ショーそして電話リクエスト(phone-in)といった範疇は、テレビとラジオの両方で見出される;ニュース報道の分野は、テレビ、ラジオ、新聞で見出される;広告は全てのマスメディアの形体に現れる。予告編という分野のテクストは、同じ媒体または他の媒体の特定のテクストに直接、結び付けられる。番組表という範疇の媒体は、(番組雑誌、新聞といった)印刷物であるが、テレビやラジオという媒体を支援するために存在する。等々。
テクスト間相互関連性という概念は、テクストは境界を有するという考えを問題にし、内と外という二分法に疑問を投げかける:テクストはどこから‘始まり’、どこで‘終わる’であろう?‘テクスト’とは?‘文脈’とは?テレビという媒体は、この論点を浮かび上がらせる。テレビを、一連の離散的なテクストとしてよりは、Raymond Williamsが‘流れ’と呼んだ概念で考える方が生産的である。同じことが、ワールド・ワイド・ウエブに適用できる。そこでは、ページ上のハイパー・テクストのつながりが、それを直接、他の多くのものに結び付ける。しかし、どの媒体でも、テクストは同じような用語で考えられる。テクストの境界は透過できる。それぞれのテクストは、種々の分野や媒体における巨大な‘テクストの社会’の中に、存在する:それ自体が、孤立した全体であるテクストはない。一つの有益な記号論的技術は、異なる分野や媒体の内でまたは間で、同じようなテーマをどう異なって扱っているのか(または、異なるテーマを同じように)を比較しまた対比させることである。
通常、テクスト間相互関連性は、他のテクストに言及することを指すのに対して、関連した性質をしているが、‘テクスト内相互関連性(intratextuality)’と呼ばれる言及があるかもしれない −それは、テクスト内の関連を含んでいる。単一のコード(例えば、写真のコード)では、これらは単純な統語的な関係となる(例えば、同一の写真の中での、ある人の像と他の人との関連)。しかし、テクストは数種類のコードを含む:例えば、新聞の写真には、見出しが付く(まさに、そのような例は、分析のため、離散的テクストと見なして選んだものが、明確な境目を欠いているということを思い起こさせる:テクスト間相互関連性という概念は、テクストは文脈を有するのだということを強調する)。
バルトは、テクスト/イメージの補完的関係を記述するために‘中継器(relay)’という用語を使い、それを風刺画、4コマ漫画や劇映画で説明している(ibid., 41)。かれは‘テクストに沿って、イメージが構築されるという逆説的な場合’のために、用語を作ったのではない (ibid., 40)。たとえ、テクストとイメージの関係においては、言葉のテクストが優位であるというのが、1950年代と60年代初期には真実であったとしても、現代社会では広告のような文脈では視覚イメージがずっと重要であり、彼が‘中継器’と呼んだことは、より一般的になっている。イメージの‘説明的な’使用があいまいなテクストに対する係留となっている多くの実例がある −例えば、平たく梱包された家具の組み立て指示書がそれにあたる(‘説明する’や‘見出しをつける’について話す場合、言語中心的に言葉のテクストの方にイメージよりも優位性を持たせていることに注意しよう)。テクスト間相互関連性の重要性を知っていると、テクストの中で密接に関連しているイメージと、書かれたまたは話されたテクストの機能を、それぞれのコードの用語だけでなく、全体の比喩的編成の観点からの用語で検討するようになる。Evelyn Goldsmithは、関連したテクストとイメージの間の関係に関する典型的な研究についての有用な批評を行った(Goldsmith 1984)。
映画、テレビやワールド・ワイド・ウエブのような媒体には、複数のコードが含まれている。映画研究家のChristian Metzが言っているように、‘それらは、‥‥別のものに加えられたり、単に何らかの方法で並置されるのではない;それらは、ある順位に従って、別のものの用語で組織化され、分節されるのである、それらは、一方向の階層を構築するのである‥‥。このように、それ自身、ある意味でもう一つのコードである、コード間の関係という真のシステムが構築される’(Metz 1974, 242)。ヒットランクにチャートされた音楽ビデオでの映像とサウンド・トラックの相互干渉は、相対的主体の関係やパターンの様態の動的特性の良い例を提示する。そのようなテクスト的システムに含まれるコードは、それだけを切り離して考えられないのは明らかである:それらの間での優越的なものの動的なパターンは、意味の生成に寄与する。それらは、常に、互いに完全に調和していると仮定する必要はない −コードの相互作用は、一貫性のなさ、あいまいさ、矛盾や手抜かりを顕わにし、それはテクストを脱構築するための解釈者の視点を提示する。
William Leissと同僚達が言っているように、ある範疇のなかではコードとコードの関係は移っていく:
全て、その効果は商業的メッセージを曖昧にすることであった;それを‘読むこと’は、外部社会から参照するものを引き入れることに依存するとともに、広告の内部構造の要素を互いに関係付けることにも依存していた。(Leiss et al. 1990, 199) Gerard Genetteは、‘テクスト間相互関連性’よりもっと総括的な用語として、‘テクスト間横断性(transtextuality)という用語を提案している (Genette 1997)。彼は、5つのサブ・タイプを挙げている:
そのような目録には、コンピュータでのハイパー・テクスト性を加えるべきである:そこでは、テクストが読者を直接、他のテクストに連れて行ってくれる(出典や位置に関係しないで)。この種のテクスト間相互関連性は、従来のテクストの‘線条性’を瓦解させる。そのようなテクストを読むことは、著者によって前以て決められた標準的な手順に従うということの重要性を軽減させる。
‘テクスト間相互関連性の度合’という論点を考えてみるのも、役に立つかもしれない。‘テクスト間の相互関連がもっとも強い’テクストというのは、他のテクストと区別がつかないような複製であろうか、またはテクスト間相互関連が意味することよりもっと進んだものであるのだろうか?‘テクスト間相互関連がもっとも強い’テクストは、自分自身だけを参照するという不可能なゴールに近づこうとするものなのだろうか?例え、特定のテクストが参照されていなくても、テクストは幾つかの範疇内で書かれ、言語を、著者達が‘発明’したとは言えない方法で使用している。テクスト間相互関連性は、単に単一次元上の連続体のように思えないし、我々が探すべき次元について合意が取れているとも思えない。テクスト間相互関連性はテクストだけの特徴でなく、それを読むことが、その著者と読者で作り上げる契約の特徴でもある。テクストを生産する主要な様態は、それらの負債を隠すように見えることから、反射性は重要な論点になるように思われる −我々は、テクスト間相互関連性が如何に有標化される(markedかを、考察する必要がある。テクスト間相互関連性の幾つかの決定的な特徴は次のようなものである:
実在主義者の‘芸術は人生を模倣する’という備忘録をもじれば、テクスト間相互関連性は、芸術は芸術を模倣するということを示唆する。(代表的なものとしては)オスカー・ワイルドがこの考えをさらに取り入れ、‘人生は芸術を模倣する’と挑発的に宣言している。テクストは、他のテクストの構築だけでなく、経験の構築の助けとなる。世界について‘知っている’ことの多くは、本、新聞そして雑誌で読んだこと、劇映画やテレビで見たこと、ラジオで聞いたことから引き出されたものである。人生は、このようにテクストを介して充実し、我々が通常見聞きする範囲以上の枠組みを、テクストによって持てる。Scott Lashは次のように見ている。‘我々は、認識が“実在物”に向けられるのと同じ頻度で表現に向けられる社会に住んでいる’(Lash 1990, 24)。テクスト間相互関連性は、テクストとテクストの境界を曖昧にするだけでなく、テクストと実際の経験世界の境界をも曖昧にする。まさに、テクスト以前の経験は知らない、といえるかもしれない。我々が知っている世界は、単にその現在の表現である。
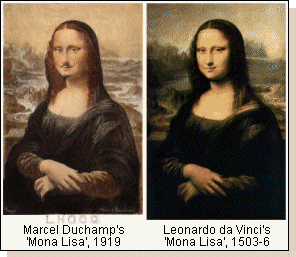 1968年に、バルトは‘作者の死’と‘読者の誕生’を言明し、‘テクストの一貫性はその起源ではなく、その志向するところにある’と宣言した(Barthes 1977, 148)。他のテクストによるそのテクストの枠組は、作者だけでなく、読者にも暗示を与える。Fredric Jamesonは、次のように主張している。‘テクストは、常に、すでに読まれたものとして我々の前に現れる;我々は、テクストを以前の理解の沈殿層を介して理解するか、 −もし、テクストが真新しいものならば− 沈殿している読む習慣と、継承された理解の伝統によって育まれた範疇を介して、理解する’(cited in Rodowick 1994, 286, where it was, with delicious irony in this context, cited from Tony Bennett)。有名なテクストは、読むことの歴史を有している。‘文学作品は、全て‥‥無意識の内に、それらを読んだ社会によって“書き直されている”’(Eagleton 1983, 12)。現代では、テクストが再生産され、作成され、言及され、もじられる文脈を −最初の時でさえ− 、誰も意識せずに、有名な小説や詩を読むことができないし、また有名な絵画や彫刻を見ることも、音楽の有名な章節を聴くことも、有名な演劇や映画を見ることもできない。そのような文脈は、読者がそのテクストを理解する過程で作成するのを避けられない、主要な枠組を構築する。
1968年に、バルトは‘作者の死’と‘読者の誕生’を言明し、‘テクストの一貫性はその起源ではなく、その志向するところにある’と宣言した(Barthes 1977, 148)。他のテクストによるそのテクストの枠組は、作者だけでなく、読者にも暗示を与える。Fredric Jamesonは、次のように主張している。‘テクストは、常に、すでに読まれたものとして我々の前に現れる;我々は、テクストを以前の理解の沈殿層を介して理解するか、 −もし、テクストが真新しいものならば− 沈殿している読む習慣と、継承された理解の伝統によって育まれた範疇を介して、理解する’(cited in Rodowick 1994, 286, where it was, with delicious irony in this context, cited from Tony Bennett)。有名なテクストは、読むことの歴史を有している。‘文学作品は、全て‥‥無意識の内に、それらを読んだ社会によって“書き直されている”’(Eagleton 1983, 12)。現代では、テクストが再生産され、作成され、言及され、もじられる文脈を −最初の時でさえ− 、誰も意識せずに、有名な小説や詩を読むことができないし、また有名な絵画や彫刻を見ることも、音楽の有名な章節を聴くことも、有名な演劇や映画を見ることもできない。そのような文脈は、読者がそのテクストを理解する過程で作成するのを避けられない、主要な枠組を構築する。
ある本の境界は、決して明確でない:題目、最初の出だし、最終行のかなたに、またその内部構成やその自立的形体を越えて、他の本、他のテクスト、他の文章を参照するシステムの中で、それは捉えられる:それは、ネットワークの節(ノード)である‥‥。本は、自由になる客体ではない‥‥。その個体(unity)は可変で相対的である。(Foucault 1974, 23)
 あるテクストの他のテクストへの謝辞は、(学術的書物という学問的体裁を除いては)めったに見られない。これは、著者の‘独創性’という神話を助長する。しかし、いくつかのテクストは、 −映画の‘リメーク’、アニメ化された漫画のように− お互いに、直接語りかける。ザ・シンプソンズ (The Simpsons米国の人気アニメ)におけるメディアへのエクストラ・ダイジェテック(extra-diegetic:物語の世界以外)な参照、そして多くの面白い現代のTV広告(英国では、Boddintonビールの広告が注目に値する)などがそれにあたる。これは、テクスト間相互関連性を、自己認識した形体である:それは、視聴者が、そのようなほのめかしを理解するのに必要な経験を有しているものとみなし、彼らに認識の喜びを提示する。他のテクストや他の媒体に言及することにより、この実践は、我々に次のことを思い起こさせる。我々は、仲介された実在の中におり、それゆえそれは、物語という進行中の実在を視聴者に信じさせようとする、主流の‘実在主義’の伝統に反する行動に出る‘離間’モードであると理解することができる。それは、感情的な関わりよりも、批判的な離間の喜びに訴える。
あるテクストの他のテクストへの謝辞は、(学術的書物という学問的体裁を除いては)めったに見られない。これは、著者の‘独創性’という神話を助長する。しかし、いくつかのテクストは、 −映画の‘リメーク’、アニメ化された漫画のように− お互いに、直接語りかける。ザ・シンプソンズ (The Simpsons米国の人気アニメ)におけるメディアへのエクストラ・ダイジェテック(extra-diegetic:物語の世界以外)な参照、そして多くの面白い現代のTV広告(英国では、Boddintonビールの広告が注目に値する)などがそれにあたる。これは、テクスト間相互関連性を、自己認識した形体である:それは、視聴者が、そのようなほのめかしを理解するのに必要な経験を有しているものとみなし、彼らに認識の喜びを提示する。他のテクストや他の媒体に言及することにより、この実践は、我々に次のことを思い起こさせる。我々は、仲介された実在の中におり、それゆえそれは、物語という進行中の実在を視聴者に信じさせようとする、主流の‘実在主義’の伝統に反する行動に出る‘離間’モードであると理解することができる。それは、感情的な関わりよりも、批判的な離間の喜びに訴える。
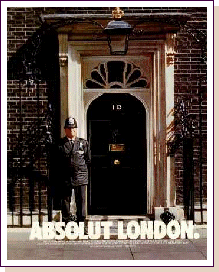 ここに示されているAbsolutウオッカの広告を理解するためには、何を探せば良いかを知る必要がある。そのような期待は、拡張されたシリーズの関連した広告を見るという以前の経験と照らし合わせることにより、確たるものになる。いったん、探しているものがボトルの形だと知れば、その写真の中で、それを認識するのは容易である。このように、現代の視覚的広告は、テクスト間相互関連性を大いに利用している。時には、まったく製品を直接指さないものもある。理解するための適正なコードを即座に確定することは、その広告の理解者が排他的クラブのメンバーであることを明確にするのに、また理解するための行動は、その人の会員資格を更新するのに役立つ。
ここに示されているAbsolutウオッカの広告を理解するためには、何を探せば良いかを知る必要がある。そのような期待は、拡張されたシリーズの関連した広告を見るという以前の経験と照らし合わせることにより、確たるものになる。いったん、探しているものがボトルの形だと知れば、その写真の中で、それを認識するのは容易である。このように、現代の視覚的広告は、テクスト間相互関連性を大いに利用している。時には、まったく製品を直接指さないものもある。理解するための適正なコードを即座に確定することは、その広告の理解者が排他的クラブのメンバーであることを明確にするのに、また理解するための行動は、その人の会員資格を更新するのに役立つ。
 ロラン・バルトは係留(anchorage)という概念を導入した(Barthes1977, 38ff)。言語的な要素は、イメージの優先された読解(preferred readings)を‘係留する’(または強制する)のに役立つ:‘記号内容という浮遊している連鎖を固定するのに役立つ’(ibid., 39)。バルトは、テクストの係留という概念を、主に広告と関連して導入し、‘吹き出し’について考察したが、勿論、これは見出し付きの写真、地図、テレビで放送される物語、ドキュメンタリー映画、風刺画や漫画(北米では‘マンガ本’)などの他の分野への適用できる。バルトは、係留の主たる機能は思想的である、と主張している(ibid., 40)。これは、写真が新聞のような文脈で使われる時、もっとも明白になる。写真の見出しは、表現された世界が自明的に存在することに対する中立的なラベルとして、それ自身を提示するが、実際には参照するべき用語やそれを見る視点を定めることになる。(Chaplin 1994, 270)。例えば、‘報道写真が、我々に言葉で、その話題の表現がどのように読まれるべきかを、正確に語りかけてくる、というのは常識的なことである’ (Hall 1981, 229)。貴方は、毎日の新聞で、この主張を確認できるかもしれない。しかし、そのようなテクストの係留は、もっと破壊的な機能を持つことも出来る。例えば、1970年代に、写真家Victor Burginは、印刷広告からのイメージに彼自身の印刷されたテクストを組合わせて、最初の広告が意図した意味と反対となるポスターを出展したことがある。
ロラン・バルトは係留(anchorage)という概念を導入した(Barthes1977, 38ff)。言語的な要素は、イメージの優先された読解(preferred readings)を‘係留する’(または強制する)のに役立つ:‘記号内容という浮遊している連鎖を固定するのに役立つ’(ibid., 39)。バルトは、テクストの係留という概念を、主に広告と関連して導入し、‘吹き出し’について考察したが、勿論、これは見出し付きの写真、地図、テレビで放送される物語、ドキュメンタリー映画、風刺画や漫画(北米では‘マンガ本’)などの他の分野への適用できる。バルトは、係留の主たる機能は思想的である、と主張している(ibid., 40)。これは、写真が新聞のような文脈で使われる時、もっとも明白になる。写真の見出しは、表現された世界が自明的に存在することに対する中立的なラベルとして、それ自身を提示するが、実際には参照するべき用語やそれを見る視点を定めることになる。(Chaplin 1994, 270)。例えば、‘報道写真が、我々に言葉で、その話題の表現がどのように読まれるべきかを、正確に語りかけてくる、というのは常識的なことである’ (Hall 1981, 229)。貴方は、毎日の新聞で、この主張を確認できるかもしれない。しかし、そのようなテクストの係留は、もっと破壊的な機能を持つことも出来る。例えば、1970年代に、写真家Victor Burginは、印刷広告からのイメージに彼自身の印刷されたテクストを組合わせて、最初の広告が意図した意味と反対となるポスターを出展したことがある。
広告での視覚イメージの優位性が大きくなっていくことは、メッセージの構造に組み込まれた意味を曖昧なものにしていく。初期の広告は、通常、書かれたテクストという媒体を介して、極めてあからさまにそのメッセージを記述していた‥‥、しかし1920年代半ばから、視覚表現がより一般的になり始めると、テクストと視覚イメージの関係は補完的になった −つまり、テクストは視覚なものを説明するようになった。第2次大戦後、特に1960年代から、テクストの機能は視覚的なものを説明するということから離れ、テクストが視覚イメージにとって一種に‘キー’としての様相を呈する神秘的な形式に向かっていく。
 C・レヴィ=ストロースの、手元にある既存の材料を充当して即席の構造を創造する‘器用人(bricoleur)’という考えは、文化研究では比較的良く知られている(Levi-Strauss 1974, 16-33, 35-6, 150n; cf. Levi-Strauss 1964)。レビー・ストロースは、‘神話の思想’を‘一種の器用仕事(bricolage)’と見ていた (Levi-Strauss 1974, 17):‘それは、かって社会的談話であったことの断片から、思想的城を構築する’ (ibid., 21n):器用人は、記号とともに作用し、存在する記号内容を記号表現として用いることにより、新たな配置を構築し、そして −‘限定された可能性’の中からなされる選択により− ‘物という媒体を介して’‘語りかける’(ibid., 20, 21)。‘器用仕事の最初の局面は‥‥、統語的連鎖の断片から範列の体系を構築することであり’、それは新たな体系へと導くことになる(ibid., 150n)。‘出典(authorship)’を同様な用語で考えることも出来る。C・レヴィ=ストロースは確かに、芸術的な創造を、部分的には物質を使った対話と見ていた(ibid., 18, 27, 29)。 (Quintilian=Marcus Fabius Quintilianus (AD 35-95)にしたがえば)論理的には、器用仕事は、数種類の主要な変換を介した操作と見ることができる:その変換は、加え合わせ、削除、代入、転置である (Noth 1990, 341)。
C・レヴィ=ストロースの、手元にある既存の材料を充当して即席の構造を創造する‘器用人(bricoleur)’という考えは、文化研究では比較的良く知られている(Levi-Strauss 1974, 16-33, 35-6, 150n; cf. Levi-Strauss 1964)。レビー・ストロースは、‘神話の思想’を‘一種の器用仕事(bricolage)’と見ていた (Levi-Strauss 1974, 17):‘それは、かって社会的談話であったことの断片から、思想的城を構築する’ (ibid., 21n):器用人は、記号とともに作用し、存在する記号内容を記号表現として用いることにより、新たな配置を構築し、そして −‘限定された可能性’の中からなされる選択により− ‘物という媒体を介して’‘語りかける’(ibid., 20, 21)。‘器用仕事の最初の局面は‥‥、統語的連鎖の断片から範列の体系を構築することであり’、それは新たな体系へと導くことになる(ibid., 150n)。‘出典(authorship)’を同様な用語で考えることも出来る。C・レヴィ=ストロースは確かに、芸術的な創造を、部分的には物質を使った対話と見ていた(ibid., 18, 27, 29)。 (Quintilian=Marcus Fabius Quintilianus (AD 35-95)にしたがえば)論理的には、器用仕事は、数種類の主要な変換を介した操作と見ることができる:その変換は、加え合わせ、削除、代入、転置である (Noth 1990, 341)。