Semiotics for Beginners
−初心者のための記号論−
Daniel Chandler (University of Wales)
記号論的分析に対する批判(Criticisms of Semiotic Analysis) 記号論の視野や方法論について、研究者自身の間で意見が一致しているのは、記号論は‘記号の研究’であるということだけである。ソシュールは、記号論が人文科学の一分野になる日を期待していたが、記号論は統一され、充分成熟した分析法や理論というより、比較的いいがげんに決められた批判的実践である。最悪なことは、‘記号論的分析’として通っていることは、単に主観的な解釈と傲慢な主張に基づく、文学の境界を越えて適用されたもったいぶった形式の文芸批評に過ぎないことである。この種の乱用は、ある分野では、記号論は学術的なホラ吹きの最後の隠れ場であるという芳しくない評価となっている。構造主義記号論に対する批判で、何人かの研究者は記号論をまったく捨てたが、記号論を新しい視点と結び付けようとしている動きもある。移りつつある目標は、動くにつれその形を流動的に変えていくので、それについて批評することは難しい。
記号論は、しばしば‘帝国主義的’と批判されている。というのは、記号論の研究者は、記号論はなんにでもまた全てのものに関与、適用できると考え、全ての学術分野にずけずけと踏み込んでいくように見えるからである。ジョン・スタロックは、次のようにコメントしている。‘記号論の適用範囲を、文化の全てを含むように劇的に拡張することは、我々の生活を意味で溢れさせようとする一種の知的テロリズムではないか、という疑いの目で見られている’ (Sturrock 1986, 89)。記号論的分析は、記号の実践を探索するために使われる多くの技術のうちの一つに過ぎない。媒体によって、記号は変わってくる −タイプが異なれば、研究する方法も変える必要があるかも知れない。媒体化の過程については、記号論は他の方法より適している。しかし、たとえば、記号論は定量化には役立たず、内容分析(content analyasis)の方が、ずっと適している(多くの記号論者が仮定しているように、この二つの方法は両立しないということを示唆しているのではない)。記号論的主張に対する経験的検証は、他の方法を必要とする。記号論的接近は、他の方法より、ある種の質問を発するのを容易にする;それら自身では、特定の社会的文脈で、人々がどのようにテクストを解釈するかということは、明らかにすることはできず、民族誌学的そして現象学的接近を必要とするだろう (see McQuarrie & Mick 1992)。
記号論者は、彼らの技術の限界を明示するとは限らず、時によっては、記号論は汎用的道具として、あいまいに提示される。ソシュール流の記号論は、言語学的モデルを基礎としているが、例えば写真や映画を‘言語’として扱うことが生産的であると誰もが認めているわけではない。Paul Messarisは、我々は写真や音声−視覚媒体の公式的なコードを‘読む’ことを学習する必要があるということに反論し、それらのイメージが観測可能な実在物に似ているというのは、単なる文化的慣習 ということではないと主張している:‘静止画や動画で出会う公式的な慣例は、最初に見た人でも、本質的な度合いまで、よく分かるに違いない’と主張している(Messaris 1994, 7)。John Cornerは、記号論者がなんでもコードとして扱うのに、その詳細は明示しないこと(特に、思想的コードの場合)を非難している (Corner 1980)。
時によっては、記号論者は、彼らの分析は主観的な解釈ではなく、純粋に客観的で‘科学的’な説明であるかのごとく提示する。しかし、特定の説明に対して、経験的に証拠立てることが必要だと感じている記号論者はいまだに少ないし、記号分析の多くは漠然としており、印象的でありとてもシステム的とは言えない(別の言い方をすれば、明確で実際的な応用をしないで、精巧な分類学を生み出している)。記号論者の何人かは、記号論的分析を広い範囲の実例に適用しないで、彼らが作り出したい論点を説明するために適した例題を選び出している(Leiss et al. 1990, 214)。William Leissと彼の僚友たちは、記号論の大きな欠点は、‘個々の分析者の能力に大きく依存する’ことだと主張している。あまり才能のない実践者は、‘当たり前のことを、複雑そうにまたしばしば思い上がった流儀で述べているに過ぎない’ (Leiss et al. 1990, 214)。確かに、いくつかのケースでは、記号論的分析は、大部分の人々が加われないようなたわごとを使って、解説者が熟練者のようにように見せる弁解に過ぎないように思われる。実際には、記号論的分析は、個々の解釈から構成されている。同じテクストに対する、複数の分析者による論評が提示されることはめったにないし、いわんや、異なる記号論者の間で何らかの同意があったという証が提示されたことはない。分析の戦略を、使われた例題や他のものに適用できるほど明示する記号論者は少ない。構造主義記号論者は、他の解釈を許容せず、彼ら自身の解釈は一般的な合意を反映しているかまたは‘彼らのテクスト解釈は記号構造に内在するもので、クロスチェックは必要ない’と仮定する傾向にある(McQuarrie & Mick 1992, 194)。他の人の解釈を研究しようとしない記号論者は、‘エリート解釈者’と呼ばれているものに特権を与えている −一方、社会指向の記号論者は、人々の解釈行為を探求することが、記号論の基礎であると主張するだろう。
記号論的分析は、抽象的で分類に余念のない‘無味乾燥な形式主義’以上の何者でもない、と非難されることもある。Susan Haywardは、構造主義記号論は‘理論的枠組みに重点をおくことにより、美学的反応を押しつぶす’ことにもなりかねない、と宣言している (Hayward 1996, 352)。記号論的分析は、しばしば感情的領域を軽視する傾向にある −しかし、共示義は、高度に変わりやすくまた主観的かつ感情的ニュアンスを、繊細に探求することも含まれているはずである
構造主義記号論では、(ソシュールの用語で)パロールよりもラングに、記号の使用や生成の過程よりもシステムに焦点をあてている。構造主義的探求は、純粋にテクスト的分析になる傾向にあり、記号論者がテクスト分析の領域から踏み出した場合でさえ、‘次の時点では、テクスト分析に戻っている’、と示唆されている。(Johnson1996, 98)。記号論は、意味はテクストの構造を決めることにより純粋に説明できる、と示唆しているように見える。 そのような立場は、言語決定主義と同じ非難を受ける。システムの決定力を優先させると、それは根本的に保守的だと捉えられる。純粋な構造主義記号論は、記号生成の過程、 視聴者の解釈または著者の意図ということにさえ取り組もうとしない。それは、特定の実践、直感的な枠組み、社会的、経済的、政治的文脈を無視する。テクストは、主流となる階級の興味を書き立てる読み方を奨励するように成文化される、と主張したロラン・バルトさえ、彼の注意をテクスト内部の構造に固定し、解釈の社会的文脈に取り組もうとしなかった(Gardiner 1992, 149-50)。優先される読み方が問題ではなくなっている、ということは仮定できない(Hall 1980)。 社会学者は構造主義記号論の機能主義(functionalism)を批判し、‘テクストを読むこと’のような物質的な実践は、‘文化的実践の政治的かけひき’を引き起こす社会的関連に関係づけられるべきだ、と主張している。機能主義は、‘決定という問題へのまったく内部的な解決法としてなら認められる余地がある’、と彼はコメントしている(Slater 1983, 259). David Buxtonも、構造主義的接近法は‘社会的決定を否定いる‥‥’、と論じ、‘テクストはそれ自身の構造以外のなにものかと関係づけられるべきである’、と主張している:言い換えれば、どのように‘構造化されたか’を説明しなければならない (Buxton 1990, 13)。我々は、記号がどのように意味するか(つまり、構造的に)だけでなく、何故意味するか(つまり、社会的に)、を考察すべきである;構造は、原因でない。記号表現と記号内容の関係は、存在論的には恣意的であるが、社会的には恣意的でない。記号は恣意的であるという概念は、媒体は中立であるという神話を助長しかねない、ことに気付くべきである。
Dominic Strinatiは次のように言っている:
フェミニストの研究者は、構造主義記号論はある側面では、フェミニストにとって有用であるが、それは‘主流と下位の族長支配の形のように、差異の構成の中にある力の関係を被い隠す’と示唆している(Franklin et al. 1996, 263)。
共時的分析は、ある現象がある時、凍りついたように見なしてそれを分析する。;経時的分析は時間的変化に注目する。これまで、記号論は、(ソシュール流記号論がそうしてるように)経時的分析より共時的分析に焦点をあてる傾向があったので、媒体の慣例の動的性質を過小評価している(例えば、テレビの慣例は、書かれた英語における慣例に較べると、ずっと速く変化する)。それはまた、意味作用がそれに言及し、形成するのを助ける文化的神話の動的変化も過小評価することにもつながる。純粋な構造主義記号論は、過程と歴史性を無視する −それは、歴史的理論がマルクス主義を好むのと異なっている。
HodgeとTrippが言っているように、‘徹底的な記号論分析は、殆どあり得ない‥‥、というのは、“完全な”分析は、特定の社会的また歴史的環境の中に位置付けられるからである’ (Hodge & Tripp 1986, 27)。これは、我々は我々の意味システムからは踏み出すことが出来ないという、ポスト構造主義の立場からも強化される。記号論者は、脱順応化(denaturalization)を指向した戦略により、主要なコードから、自分自身を遠ざけようとする。‘馴質異化、異質順化’というという考えは、美術的また写真的声明や色々な分野での創造的な‘ブレイン・ストーミング’のセッションでたびたび見かけられる特徴である。この言葉づかい自体は、ドイツの詩人Novalis (1772-1801, aka Friedrich von Hardenberg)によるものであり、彼はロマン主義の真髄は‘馴質異化、異質順化’であると宣言している。この考えは、ワーズワースやコールリッジのようなロマン主義者の間でも見出される。この考えは、超現実主義(Surrealism)やブレヒト流の‘異化(alienation)’とも密接に関連している。しかし、それが、記号学者によって用いられるようになったのは、多分に、ロシア・フォーマリズムの論評に依るところが大きい(Lemon & Reis 1965)。ビクター・シコルスキー(Victor Shklovsky)は、1916年に、美術の機能は、離間(estrangement)、熟知していることから脱け出すこと(defamiliarization)または‘異化すること’(異質にすること(ostranenie))であると主張している −つまり、あまりにも慣れ親しんでいるため、それに対する認識が定型化している日常的な出来事を、更新することである(Hawkes 1977, 62-67)。ロシア・フォーマニズムは、東欧における記号論の発達に大きな影響を与え、‘異質順化’という遺産は、記号論にとって重要なものとなった。しかし、Simon Watneyが言っているように、‘熟知していることから脱け出すこと’という戦略自体が思想的であり、驚きという戦術は‘ゆがみ’を追放し、それにより、我々は‘客観的に’‘実在’を知覚できるという考えにも関連してくる(Watney 1982, 173-4)。明らかに、‘馴質異化’という戦略は、それによって一群の慣例を避けて通ることが出来るかもしれないが、決して慣例による経験の枠取りから逃れられない、という認識と結び付けておく必要がある。
記号論者のうちには、コミュニケーションを単なる‘記号解読(decoding)’の過程として表現する傾向があると、Guy Cookは言っている:
Cookは、‘記号論的接近法の弱点は、相似性への独特の愛着と、相似性が見出されれれば、その独自性には目をつぶるきっぱりした態度にある’、と加えている (ibid., 70)。 Rosalind CowardとJohn Ellisはまた、‘構造分析は、テクスト間の差異を考慮するのに適していないことがわかった’とコメントしている (Coward & Ellis 1977, 5)。プロップ、グレマス、C・レヴィ=ストロースなどの研究者の構造的公式化を特徴付ける‘下に潜む構造’へ焦点をあてることは、それ自身が重要なことであるかもしれない‘表面の形状’を軽視することになる (Cook 1992, 71)。これは文芸批評にとって、文体上の差異という事柄を無視するように見えるので、特に厄介な問題となる。
Varda Langholz Leymoreは、彼自身は構造主義的接近法を採用しているが、次のように論じている:
現代の研究者の何人かは、純粋な構造主義記号論を拒否している。しかし、記号論全てを拒否している訳ではない。以前は大きな影響力があったかもしれないが、構造主義分析は記号論への一つの接近法に過ぎない。記号論に対する批判の大部分は、現在、固執する記号論者が余りいない記号論の形式に向けられている。(主に、物語、映画やテレビの編集の詳細な研究に焦点をあてている)形式的システムへの構造主義的関心を保持している記号論者は何人かいるが、多くの研究者は‘社会的記号論’に関心を持っている(Hodge & Kress 1988)。 社会記号学者の主な関心事は、Stephen Heathが‘特定の意味行為’と呼んだものにあるLapsley & Westlake 1988, 55)。そのような‘リフォームされた’記号論者は、‘ポスト構造主義’記号論を実践し、‘位置付けられた社会的記号論’と呼ばれるものに注目している。 (Jensen 1995, 57)。少なくとも、これは社会記号論者の修辞であるが、社会記号論と社会学者の興味が、どの範囲まで一致するかは議論のあるところである。しかし、まだ初期の段階である:‘社会記号論’はまだ構築途上である。この開発に関与している現代の研究者には、Gunther Kress, Robert Hodge、Theo van Leeuwen、Klaus Bruhn Jensen、Paul J Thibault、Jay Lemkeがいる (Hodge & Kress 1988; Jensen 1995; Lemke 1995; Kress & van Leeuwen 1996; Thibault 1997)。
Victor Burginは、次のように言っている。幾つかの説話に関して、‘マルクス主義と心理分析[後者は、 ジャック・ラカンの業績から派生したもの]が、歴史の決定や意味を生産する主体を把握するように[ポスト構造主義]記号論が動くことに、もっとも影響を与えた’ (Burgin 1982b, 144-5)。 Strinatiは、次のように言っている。記号論は、‘思想としてのマルクス主義理論の決定論的また道具的側面を弱めるために使われた。しかし、これでもまだ、生成されたこと自体が意見の不一致や妥協の産物であり、また生産された意味が不均一、整合性が取れていず、曖昧であり、首尾一貫した支配的な思想へ還元できないということを、過小評価している’(Strinati1995, 127; see also Tagg 1988, 23ff, 153-83)。記号論のもう一つの変調が、フーコー流である −それは‘推論的実践(discursive practices)の強力な効果’を強調している 記号論に対する批判の多くは、その分野の人たちによる自己批判の形をとっている、と指摘しておくのが公平だろう。記号論の理論的文献は、記号論の世界の枠組みに対して新しい理論を包含しようとする、多くの記号論者による不断の試みを反映している。さらに、現代の擁護者は、記号論の社会的次元を強調するのは、何も新しいことではないと言っている。社会記号論の源は、初期の理論家までさかのぼることができる。ソシュールもパースも、記号の社会的利用は研究しなかった。しかし、ソシュールは、記号論を‘社会的生活の要素としての記号の役割を研究する科学’として、記号論を思い描いていた。また、パースにとって、対話プロセスとしての記号過程という観念は、彼の思想の中心であった。記号は、解釈者なしでは存在せず、記号論的コードは、当然、社会的慣習である。しかし、記号論の社会的次元を、特定の意味生成の実践の形で、強調することは、専門化された学術誌に比較的最近、現れたきたものであり、記号論研究者の活動の中心部では、まだ目立った動きになっていないということを認識する必要がある。
記号論が、正統な資格で学術的な一分野となったことはなかったし、今でもなく将来もないであろう。今は、文化的形体の‘科学’というより、いろいろある分析の一つの様態であることは、広く認められている。
一束のバラが情熱を意味することを、送り手の意志と受け取った人の反応また彼らが組み込まれている関係を知らなければ、どうやって知ることができるだろう。彼らが恋人同士で、愛の証として花をやり取りする習慣を受け入れるなら、我々は[この]解釈を認めるだろう‥‥。しかし、もしそうするなら、それは記号に基づいてではなく、我々が記号を位置付ける社会的な関係を基礎としたものである。バラは、冗談、侮辱、祝福の記号等々として、贈られたのかもしれない。それは、贈り手に代わって情熱を示し、しかし受け手に代わって、嫌悪を示しているのかもしれない;それは恋人同士の関係というより、祖父と孫という家族関係を意味しているのかもしれない、等々。バラの花束は、性的嫌がらせさえも共示しているかもしれない(Strinati 1995, 125)。
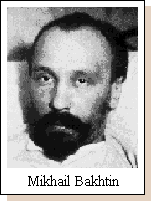 John Sturrockは、次のように言っている。ミハエル・バフチン −文学研究者− のような、何人かの注釈者は社会を‘脱神秘化’する‘暴露的な’政治目的に記号論を使用している。そしてそのような接近法は、ある社会的階級の他の階級に対する思想的たくらみとして、社会の‘積み込まれた’‘読み方’へと繋がっていった(Sturrock 1986, 91)。Sturrockは‘多少、中立的な’接近法を好んでいたが、そのような中立性が可能であることを受容する研究者は余りいない。特に、マルクス主義者は、‘意味作用の政治学’を強調する −意味作用は中立(‘価値から独立している’)では、あり得ない。John Taggは、次のようにコメントしている。彼は、‘純朴な“真理”の操作を暴露することや、陰謀を暴くことには関心がなく、“真理”の“生産の様態”がその中で働く特定の“政治の経済性”に関心がある’ (Tagg 1988, 174-5)。構造主義者は、、我々は記号論分析を、記号の向こうにある、‘下に潜む’あらかじめ与えられている実在を見渡すために、使用できると仮定する傾向にあるが、ポスト構造主義者はそれは不可能である −我々は、我々の記号システムの外に立つことはできない− と主張している。
John Sturrockは、次のように言っている。ミハエル・バフチン −文学研究者− のような、何人かの注釈者は社会を‘脱神秘化’する‘暴露的な’政治目的に記号論を使用している。そしてそのような接近法は、ある社会的階級の他の階級に対する思想的たくらみとして、社会の‘積み込まれた’‘読み方’へと繋がっていった(Sturrock 1986, 91)。Sturrockは‘多少、中立的な’接近法を好んでいたが、そのような中立性が可能であることを受容する研究者は余りいない。特に、マルクス主義者は、‘意味作用の政治学’を強調する −意味作用は中立(‘価値から独立している’)では、あり得ない。John Taggは、次のようにコメントしている。彼は、‘純朴な“真理”の操作を暴露することや、陰謀を暴くことには関心がなく、“真理”の“生産の様態”がその中で働く特定の“政治の経済性”に関心がある’ (Tagg 1988, 174-5)。構造主義者は、、我々は記号論分析を、記号の向こうにある、‘下に潜む’あらかじめ与えられている実在を見渡すために、使用できると仮定する傾向にあるが、ポスト構造主義者はそれは不可能である −我々は、我々の記号システムの外に立つことはできない− と主張している。
広告を解読する(Decoding Advertisements)というよく知られた言い方は、最初に、1978年に出版された本の題目として、Judith Williamsonによって使われ、それ以来、大学の授業や出版で広く繰り返されてきた(Umiker-Sebeok 1987: 249-335)。Williamsonの接近法の要点は、分析を通じて、彼女が言葉と広告のイメージの‘真の’意味と呼ぶものや広告の‘現実でない’イメージが指す‘現実世界’を明らかにすることである(Williamson 1978: 47)。これには、‘現実’は‘虚構’とは切り離せることができるだけでなく、真に上位にある‥‥という、明確な仮定がある。デコーディングによる接近法は、時には、興味ある結果をもたらすが(実際には、しばしば自明のものだが)、その方法の弱点は、そのような等価性が完璧な分析を構成するという性急な満足感にある。これは、談話の表層に特有なことや特定の記号表現に関する全ての考察を放棄し、複雑さ、才能、ユーモアを見逃すことになる。(Cook 1992, 63-4)
記号学の研究は、言語学から多くの啓示を受けているが、多くの場合、最も革新的な側面、つまり基本的規則が持っている無限の創造性には対応できていない。殆どの場合、記号学の研究では、構造の同定は、そのシステムの全ての成員が、ある規則に従って組み入れられる形式的な輪郭を創造することに等しい。しかし、その逆は真ではない。チョムスキーが文章を生成できるという意味では、システムは、その談話の宇宙に属するたった一つの例も作ることができない。言い換えれば、深層構造から表層構造へ‘逆に変換する’ことができる規則が規定されていない。この意味では、記号学の研究は、生成的でなく、静的である。
(Langholz Leymore 1975, 15)