Semiotics for Beginners
−初心者のための記号論−
Daniel Chandler (University of Wales)
記号論的分析の長所(Strengths of Semiotic Analysiss) 記号論は、日常生活だけでなく学術分野における理論上の仮定を変性させるのに役立つ;このように、理論上の新たな論点を浮かび上がらせることになる(Culler 1985, 102; Douglas 1982, 199)。記号論に出会った多くの学者がそれを不安定なものと考えていることを意味しているが、とても面白いと思う学者もいる。‘言語との相似システムを文化全体に拡張する’記号論的技術は、‘それ以前の文化理論を制約していた、多くの実証主義者や経験的伝統からの本質的突破’を表現していると見なすことができる(Franklin et al. 1996, 263)。Robert HodgeとGunther Kressは、次のように論じている。多くの学術分野と異なり、‘記号論は、コミュニケーション現象を個々にではなく、全体としてシステム的、総合的にまた首尾一貫して研究できるのではないかという希望を提示している’(Hodge & Kress 1988, 1)。記号論は、潜在的に持っている統一的な概念の枠組み、そして身振り、態度、衣装、書き物、話、写真、テレビ、ラジオなどの充分広い範囲の意味作用の実践に使える、一群の方法や用語を提供する。記号論は、それ自体、一つの分野ではないかもしれないが、少なくとも、従来の学術分野が周辺として扱ってきた意味を作る実践を中心課題とした探求に焦点をあててきた。David Slessが記しているように、‘我々は、言語学者には言語の研究、美術史家や批評家には絵画を研究することを、そして人類学者には、異なる種族の人が身振り、衣装や装飾品により、どうやって交信するかあきらかにすることを期待してきた。しかし、これらの異なること全てが、共通して持ってていることを知りたいと思ったら、記号論的視点つまり高い見地から我々の世界を調べられる人を見つける必要が出てくる’(Sless 1986, 1)。 例えば、David Mickは‘記号論のように表現に厳密に関わろうとしている分野はない’(Mick 1988, 20; my emphasis)。記号論は、表現の過程に焦点をあてまた問題にする。
伝統的な構造主義記号論は、主にテクスト分析に適用されてきたが、現代の記号論を構造主義と同一視するのは誤りである。社会記号論への転回は、読み手の役割への関心が増大していくことに反映されている。いずれの形でも、テクストに書かれた内容を越えて何かを見たいと思ったとき、記号論はその価値を発揮する。構造主義記号論は、現象の下に潜む組織を見つけるため、観察されたものの表面の裏や下を見る。テクストやコードの構造的組織が明らかであるように見えるほど、そのような表面上の特徴の向こうを見ることは難しくなる(Langholz Leymore 1975, 9)。‘明白な’ものの下にある‘隠された’ものを探すことは、実りある洞察へと導く。記号論はまた、共時的意味を探すのに適している。社会的記号論は、同一のテキストであっても、異なる読者層に対しては異なる意味が生成されることを警告してくれる。
我々にとって、‘自明’で、‘自然’で、普遍的で、所与で、永久的で、疑いのないように見えるようなどのような主張であっても、我々の談話の共同体で記号システムが作用する流儀で、生成されることを確認するのに、記号論は役立つ。美術史家Keith Mosleyは次のようにコメントしている:
‘常識’や実証的実在主義は、実在はそれを指している記号から独立していると主張し、記号論は実在の構築にあたっての記号システムの役割を強調する。ものは記号とは独立に存在するかもしれないが、それを知るのは記号の仲介を介してである。我々は、我々の記号システムが認めてよいと言ったものだけを認める。
記号論は、世界を表現するのに当たり前のように使っているものに気付かせてくれる。我々はなにものにも媒介されない客観的実在を扱っているのではなく、記号を扱っていること、また記号システムは、意味の構築の中に組み込まれていることを思い起こさせてくれる。Victor Burginが言っているように、‘思想というのは、日常生活で当たり前と思われている実在の総計である’から、上に述べたことは、思想的なことがらである(Burgin 1982a, 46)。 Valentin Voloshinovは、‘記号が存在する時はいつも、思想も存在している’ と宣言している(Voloshinov 1973, 10)。思想的に‘中立な’記号システムはない:記号は、指示するのと同時に、信じさせる機能がある。意味を作る実践においては、思想による操作は大部分が隠されるが、記号システムは‘ものごとのありよう’に関する特定の枠組みをもともとあるものとしまた強化する。結果として、記号論的分析は、いつも思想的分析を含むことになる。もし、記号が実在を反映しているだけではなく、その構築に組み込まれているならば、記号システムを管理している人が、実在の構築を管理することになる。 しかし、‘常識’は、一貫性のなさ、曖昧さ、矛盾、手抜かり、溝そして沈黙を包含し、それが潜在する社会的変化へのてこの支点となる。思想の役割は、それらを主流派の利益となるように抑圧してしまうことである。その結果、実在の構築は、‘闘争の場’で生じる。John Hartleyがコメントしているように、‘社会の力を主張することは、それぞれの記号の意味する可能性を、彼らの特定の利益に資するような点を強調するものに“固定”しようとする’、そして同時に、事実上差異を、評価可能な差異として提示しようとする(Hartley 1982, 23, 24)。 ロラン・バルトにとって、色々なコードは中産階級(ブルジョア)の思想を再生産し、それをもともとあったもので、固有のものでありそして必然的なものに見せるようにするものであった。実在に関して、誰の見方がその過程で優先されるかを知るようになることが解放されることであると認めるのに、マルクス主義者である必要はない。多くの記号論者が、自分の主たる任務は、記号やテクストやコードを変質させることだと考えている。記号論は、このように、思想が作用していることを示し、‘実在’は挑戦できることを論証する。
媒介の過程は、定型的な日常の実践では、透明性の中に引きこもる傾向があるが、記号論的接近は、Catherine Belseyが特定のテクストの分析で、‘意味作用過程の構築’と呼んだことに、我々が加わるのを支援する (Belsey 1980, 47)。これは、記号論的分析を、メディア教育者にとって、とくに魅力的なものとする。マス・メディアの研究においては、記号論的接近は、一般向け映画やテレビでいまだに主流の編集スタイルである‘見えない編集(invisible editing)というハリウッド流の慣習として認知されている実践に、我々の眼を向ける。記号論的な処理は、映画やテレビで‘当然のもの’として受容するように学習してきた慣習が、操作可能なことを気付かせてくれる。ピエール・ギローは、より広く、次のように論じている。‘意味作用という反システム的様態の中に、システムの存在を確定するのが、疑いもなく記号学の主な仕事の一つである’ (Guiraud 1975, 30)。マス・メディアに関しては、記号論は独特の貢献をしてきた。心理分析と提携して、記号論は‘主体の位置づけ’(幽霊)という理論を、映画のテクストに関して、導入してきた。この構造主義者の立場は、メディアの影響には太刀打ちできないという神話を強化して来たかもしれないが、社会記号論者は(社会的母数内での)解釈の拡散ということを強調し、‘内容’と意味を等しく捉えまたこれを直接、‘メディアの効果’へ移す傾向に反対してきた。
意味と解釈に焦点を絞ったコミュニケーションへの接近法に関しては、記号論は、意味と‘メッセージ’(または内容)が同じものであるとする還元法的伝達モデル(transmission model)に挑戦してきた。記号はただ意味を‘運搬’するのではなく、その中で意味が構築される媒体を構成する。記号論は、意味は受動的に吸収されるのではなく、解釈という能動的な過程の中でのみ生じてくるのだ、ということを実感させてくれる。印刷された広告に関連して、William Leissと彼の同僚は言っている:
他の範疇や他の媒体のテクストについても、同じようなことが言える。一つの記号から、多重の意味が生成される。記号論は、‘記号がそれに向かって開かれていること、解釈は無限に豊かであること’に光をあててくれる (Sturrock 1986, 101)。Voloshinovは、記号には、複数のアクセントがあることに言及している −特定の社会的また歴史的文脈によって、同じ記号でも解釈はどんどん広がっていく可能性がある (Voloshinov 1973, 23)。
個人の創造性や‘作者’の‘新規性’(例えば、 (監督至上主義に合致する)映画監督(auteur))といったロマンチックな神話は、記号論を構成する種々のより糸により、崩されていく:記号システムと言語によって作り出される、我々自身の優位性に関する構造主義者の強調;テクストの解釈者の役割に関する社会記号論の強調;そして、テクスト間相互関連性 (それは、テクストは他のテクストに依存していることに焦点をあてている)というポスト構造主義的記号論の概念。個人は、意味を構築する際、なんらかの拘束を受けている。スチュアート・ホールが言っているように、我々の‘記号システムは、‥‥我々がその中でまたそれを介して話しかけるのと同じくらい我々に話しかけてくる’ (Hall 1977, 328)。‘常識’は、‘私’は安定し統一したアイデンテテイと自分固有の考えを持つ唯一の個人である、と示唆する。しかし、そのような概念は、記号システムと我々との契約で作り出され、維持されているのだということを記号論は確認させてくれる:アイデンテテイという我々の感覚は、記号を介して確立されるのである。我々は‘自我’という感覚を、自分自身で創造したのではない記号やコードが入っている、慣例的で先在する貯えの上に書かれた図、から引き出す。このように、我々は記号システムを使いこなしている単純に道具的な‘使用者’になるというよりも、その‘臣下’となる。我々は、記号過程によって決定されているわけではないが、自分で実感しているよりずっと強く、それらによって形成されている。ピエール・ギローはさらに先に進んでいる:‘人間[sic]は記号の負荷体であり、本体であり、記号表現であり記号内容でもある;実際、人間は記号であり、このため慣例である’ (Guiraud 1975, 83)。粉砕され、位置がずらされたアイデンテテイというポスト・モダン主義の概念は、統一した自己という神話に対する有効な矯正といえる。しかし、過激な相対主義を単純に賛美するポスト・モダン主義の立場と異なり、記号論は、我々が自分自身をどうやって知るようになるのかという点に焦点をあてさせるようにする。一方、社会記号論は、アイデンテテイや記号システムの、そのような過程の中で果たす役割の構築における位置付けられた(situated)実践の研究に、我々を係わらせようとする。Justin Lewisは次のように記している。‘我々は、予め配置された記号論的世界の一部である。ゆりかごから墓場まで、特定の方法で意味内容の世界に関与した、決まった輪郭の環境から力を得ている’(Lewis 1991, 30)。
Guy Cookは次のような論じている。‘40年前、その方法は革新的であり、分析にそれが持ち込んだ複雑性のためだけでなく、その政治的そして哲学的意味からも知的想像力を捉えた。文化や文化が創ったものに対する視点は、例え表面的的にはいかに異なろうとも基本的には相似であり、民族主義や文化的な愛国主義に対抗する強力な武器となり、人間の文化に共通した抽象的な構造を見出せるのではないかという希望を与えた’(Cook 1992, 70-71)。フェミニストの理論家は次のように言っている。構造主義記号論は、還元主義や原理主義に対する批判の道具として、フェミニストにとって重要なものであり、‘矛盾する意味とアイデンテテイの分析を促進する’ (Franklin et al. 1996, 263)。記号論は、どんな種類の文化的作品や実践でも、統一的な原理に基づく研究を目指し、うまくいけば媒体や文化の研究にある程度の首尾一貫性をもたらす。記号論的分析は文学、美術また音楽のミサに広く適用されているが、一方、色々な大衆文化現象の‘解読’にも適用されてきた。このように、大衆文化のまじめな研究を刺激するのに貢献してきた。
*Anthony Wildenは、‘全ての言語はコミュニケーションであるが、コミュニケーシンのうちで言語の占める割合は小さい’ (Wilden 1987, 137)。 視覚的世代が増えているので、記号論は、ロラン・バルトからさらに進んで、言語的な記号とともに視覚的記号に関しても、特に広告、写真さらに視覚−映像メディアの文脈で、重要な寄与をするようになった。記号論は、特定の媒体を、その他のものより価値が低いといって、排除しないようにしてくれる:文学批評や映画評論は、テレビを小説や‘芸術的’映画より価値の低いものと見ている。もちろん、エリート主義の文学批評 にとってみれば、これは記号論の弱点となる。潜在的には、記号論は、色々な媒体間の相似性とともに差異を確認するのを支援してくれる。また、書き言葉に対する話し言葉、また言語的なもの非言語的なものに対して見られるような、一つの記号的様態のその他のものに対する日常的な優位性を避ける、のを助けてくれる。Gunther KressとTheo van Leeuwenが言っているように、‘視覚的言語、身振り‥‥のような異なる記号論的様態は、可能性も限界も持っている’、ことを認識する必要がある (Kress & van Leeuwen 1996, 31)。そのような確認は、変化していく記号論的生態学の新しい読み書き能力の重要性を認識させてくれる。現在、‘映像に関しては、大部分の社会の大部分の人々が、他の人々の作品の見学者の役割に縛り付けられている’ (Messaris 1994, 121)。大部分の人々は、絵を描けないと感じているし、ビデオ・カメラを持っている人でも、皆がその効果的な使い方を知っているわけではない。これは、一種の象徴的読み書き能力(言葉の言語のそれ)の獲得に、他の記号的な様態(特に、類像的モード)を犠牲にして、力を入れている教育システムの遺産である。この直感的な偏りは、純粋には言語的とは言えないような表現活動に従事する仕事から、多くの人を排除するだけでなく、生活を介して人々がそれに曝されているテクストへの批判的な読者の力を弱めることになる。記号論の主要概念の実用的な理解は −それは実際問題への応用も含めてであるが− 、我々の生活の中にある複雑で動的なコミュニケーションの生態系を理解しようとしている全ての人にとって、必須のものであると見ることができる。そのような環境を理解できない人には、それをできる人にうまく操られる大きな危険が待っている。パースにとって、‘宇宙は記号のみで構成されていないとしても、それは‥‥記号でみなぎっている’ (Peirce 1931-58, 5.449n)。記号から逃れることは、できない。Bill Nicholsが言っているように、‘記号が生成される限り、それらを理解しなければならない。それが生き残るということである’ (Nichols 1981, 8)。
それにより、世界を知ることができる文化的価値は、文化の成員によって世代から世代へ受け継がれてきた慣習のかたまり(tissue)であることを、記号論は我々に気付かせてくれる。それは、我々の価値について、‘当然な’ことはなにもない、ことに気付かせてくれる;それらは、時間の流れとともに大きく変わるだけでなく、文化によっても劇的に異なる社会的産物である。 (cited in Schroeder 1998, 225)
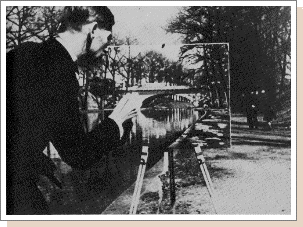 ソシュール流の記号論者は、言葉の言語を、言葉でないか、あまり言葉とは言えない媒体にモデルとしてに押し付けようとしていると非難される。しかし、言語モデルを用いる利点は、全ての記号は、ある範囲まで、恣意的かつ慣例的である、と扱う点にある −記号をもともとあったように思わせる思想の力に気付くようにさせる (Culler 1985, 92)。 記号はその記号内容と、我々が学ぶ慣習によって関連付けられていると記号論者は主張する。色々な媒体を使うにあたって、そのような慣例にあまりにも慣れてしまっているので、それらは‘もともとあった’ように見え、我々がそのような関連の慣例的な性質を真に理解するのは、難しくなる。これらの関係を当たり前のことと思うようになった時、その記号内容がなにかに媒介されていず、透明なものと見なすようになるが、それはテレビや写真を‘世界への窓’と思うことにも表れている。記号論は、‘媒体’の‘透明性’は幻覚であることを教えてくれる。
ソシュール流の記号論者は、言葉の言語を、言葉でないか、あまり言葉とは言えない媒体にモデルとしてに押し付けようとしていると非難される。しかし、言語モデルを用いる利点は、全ての記号は、ある範囲まで、恣意的かつ慣例的である、と扱う点にある −記号をもともとあったように思わせる思想の力に気付くようにさせる (Culler 1985, 92)。 記号はその記号内容と、我々が学ぶ慣習によって関連付けられていると記号論者は主張する。色々な媒体を使うにあたって、そのような慣例にあまりにも慣れてしまっているので、それらは‘もともとあった’ように見え、我々がそのような関連の慣例的な性質を真に理解するのは、難しくなる。これらの関係を当たり前のことと思うようになった時、その記号内容がなにかに媒介されていず、透明なものと見なすようになるが、それはテレビや写真を‘世界への窓’と思うことにも表れている。記号論は、‘媒体’の‘透明性’は幻覚であることを教えてくれる。
記号学的接近法は‥‥次のことを示唆している。広告の意味は、見る人によって内部化されるのを待って、表面に浮遊しているのではない。広告の内部でまた外部のより広汎な信用システムを参照することを介して、異なる記号を組織化また互いに関連付ける、という方法により作り上げられる。もっと明確に言えば、意味を創造するように広告するためには、読者や見る人が何らかの‘行為’をしなければならない。意味することはそのページに横たわっているのではなく、人はそれをつかみ出すように努力しなければならない。 (Leiss et al. 1990, 201-2)